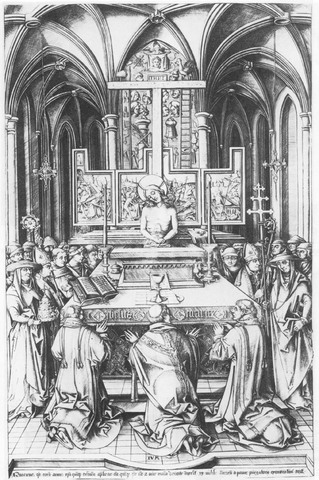アディロンダック山地とR・L・スティーヴンソン Robert Louis Stevenson in the Adirondacks [Daddy-Long-Legs]
前の記事「ジーン・ウェブスター/『あしながおじさん』関連地名 Place Names in Daddy-Long-Legs」のオマケに「アディロンダック」関連のオークションを要請した結果を見て、ちょっとびっくりして――こんなに出品があるとは思わなかった――思い出しました。あくまで個人の好奇心でヤフオクの検索をときどき入れてみているのですが。アディロンダックはインディアンの部族名ということで、ブランド名として利用価値があるということなんすかね。・・・・・・
ロバート・ルイス・スティーヴンソンが、父親の死により英国との絆を 解かれて、奥さんの故国であるアメリカにやって来て、それから西へ進んで、サンフランシスコを突き抜けて南洋へ向かったことを、9月12日の記事「スティーヴンソン、ヴァイリマ Stevenson, Vailima」では次のように書きました。――
1887年父親が亡くなり、それ以前に体調を崩して英国内のいろいろな土地での生活を試していたスティーヴンソンは、医者の勧めにしたがって大胆な転 地療養を考えます。1880年に結婚していた年上の妻ファニー・オズボーン Fanny Osbourne の故郷であるアメリカへ渡ったのです。ニューヨークに滞在後、奥さんの郷里である西海岸サンフランシスコに移り、1888年6月、ヨット Casco 号をチャーターして南洋へ航行します(伝記参照 <http://www.archive.org/stream/novelstalesofrob26steviala#page/46/mode/2up>)。 ハワイ群島やタヒチやニュージーランドを訪れて帰米。さらに1889年、義理の息子ロイド・オズボーン Lloyd Osbourne, 1868-1947 も伴って再度航海。1890年4月にシドニーからJanet Nichol 号で3度目の航海に出て、サモア島に400エーカーの土地を購入。Vailima の村に家を建て、1894年脳溢血で急死するまでその地に住みます。
たぶん、話のネタをあとにとっておこうという姑息な気持ちがあったのではなかったか、と思われるのですけれど、最初のニューヨークの滞在というのは、実はアディロンダック山地だったのでした。10月4日の記事「スティーヴンソンの手紙 Letters of Robert Louis Stevenson [Marginalia 余白に]」に挙げた、アメリカのスクリブナーズ社版のスティーヴンソン全集(シッスル版)の第24巻の書簡集II――[Letters II] [Letters and Miscellanies of Robert Louis Stevenson] Letters to His Family and Friends, Selected and Edited with Notes and Introduction by Sidney Colvin II (1899) ――の、9章は "The United States Again: Winter in the Adrondacks" というタイトルで、1887年8月から翌1888年10月までの手紙がおさめられています (pp. 63-127)。8月と9月の手紙は、まだイギリスにいたときのものと、ニューヨーク市からのものですけれど、くわしく書くと、1887年8月21日、スティーヴンソンは、妻、妻の連れ子、未亡人となった自分の母親、そして召使のValentine Roch と5人でロンドンを出航しました。そのころ、アメリカでも、スティーヴンソンは、『宝島』と『ジキル博士とハイド氏』によって、よく知られた作家となっていました。最初友人であったCharles Fairchild のいる Newport に滞在し、まもなくスクリブナーズ社主の Charles Scribner や編集者の E. L. Burlingame と知己を得て、それがその後の仕事につながるようです。スティーヴンソンはコロラドで冬を過ごすことを考えたのですが、冬の厳しい天候を危惧した周囲のアメリカ人がかわりに薦めたのが、ニューヨーク州アディロンダック山地のSaranac Lake 湖畔でした。この土地は保養地として比較的最近知られるようになった場所でした。土地の医者 Dr. Trudeau という人の監察を受けて、1887年9月末から1888年4月までの7ヶ月、スティーヴンソンたちはアディロンダックで過ごすことになります。緯度が高いために、奥さんはあんまり具合いがよくなかったようですが、スティーヴンソンの健康は改善されます。ここでスティーヴンソンは "A Chapter on Dreams" とか "Pulvis et Umbra" など10を超える文章を執筆し、Scribner's Magazine に掲載し、あるいは The Master of Ballantine の大部分を執筆し、息子のロイド・オズボーンがドラフトを書いた The Wrong Box を拡張して書いたりしました。
『あしながおじさん』のなかでアディロンダック山地は、同室のサリー・マクブライドの一家(実家はマサチューセッツ州のウスター)が避暑のキャンプに毎年やってくる場所です。ジュディーは2年生の夏の休暇のはじめにサリーに誘われる ("The McBrides have asked me to spend the summer at their camp in the Adirondacks!" [6月2日の手紙:Penguin Classics, p. 73])のだけれど、あしながおじさんが強引な指示をして、代わりにロック・ウィローへ行くことになるわけです。
そして、入選した短篇小説の賞金で買ったスティーヴンソン全集をもっていったロック・ウィローから、ヴァイリマの話やら、スティーヴンソンの手紙の引用やら、詩の引用やら、宝島の話やらを書き送るのが、この2年生の夏だったのでした。

The Cottage at Saranac Lake Occupied by Robert Louis Stevenson, image from Letters to His Family and Friends, Selected and Edited with Notes and Introduction by Sidney Colvin II (1899), pp. 80-81
女子大のカタログ Vassar College Catalogue [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』の1年生の10月中旬の水曜日、ジュディーは名前を変えてジュディーになったことを書き送っています。――
I've changed my name.
I'm still "Jerusha" in the catalogue, but I'm "Judy" every place else.
(わたし名前を変えました。カタログではまだ「ジェルーシャ」ですけれど、ほかはどこでも「ジュディー」です。)
この catalogue というのは何なのか? 邦訳はだいたい「名簿」と訳しているみたいです。辞書を引くと、「アメリカニズム(アメリカ英語)」として、大学で出す便覧や要覧、大学便覧のことだと記載されています。便覧に学生の氏名が載っているということがある(あった)のでしょうか?
作家のジーン・ウェブスターが1897年から1901年まで通ったヴァッサー女子大学のヴァッサー百科 Vassar Encyclopedia を見ると、"Original Course Catalogue" という項目があります。これは大学創立初年度の、やっぱり「授業要綱」みたいなものなのでしょうか。しかし、個人情報というか alumni のプライヴァシーへの配慮なのか、名簿的なものは載せていませんでした。
"Original Course Catalogue" <http://vcencyclopedia.vassar.edu/curriculum/original-course-catalogue/index.html>
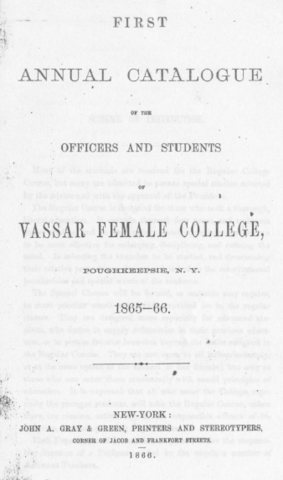
First Annual Catalogue of the Officers and Students of Vassar Female College, Poughkeepsie, N. Y.: 1865-66 ヴァッサー女子大学の最初の「カタログ」 image via Vassar Encylopedia
"Original Course Catalogue Page 1-11"
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
「1」ページ目には "Conditions of Admission" (入学資格)が、「2」「3」が "Scheme of Instruction" 、「3」が "Collegiate Departments" ――I. (英)文学、II. 古典・独仏文学、III. 数学・自然科学・化学、IV. 天文学、V. 博物学、VI. 生理学、VII. 歴史学・経済学、VIII. 哲学、というような分類みたい ――、「3」の下から「7」まで、エクステンションみたいな感じで音楽学科と芸術学科と体育学科の説明があって、そのあと、年次編成や、教科書と参考書のリスト(「9」「10」)など、当時のカリキュラムがうかがわれる記載があります。
で、名簿はなくて、不明なままだったのですが、先日あらためてInternet Archive を漁っていたら、ありました。同じオリジナルの1865-66年版ではなくて、1890-91年のものですけれど。――
Twenty-Sixth Annual Catalogue of the Officers and Students of Vassar College, Poughkeepsie, N. Y.: 1890-91 <http://www.archive.org/stream/annualcatalogue00collgoog#page/n7/mode/2up>
Twenty-Sixth Annual Catalogue of the Officers and Students of Vassar College, Poughkeepsie, N. Y.: 1890-91
この、オリジナルから25年後の版は、全部で96ページあり・・・・・・あ、今ページをめくっていたら、この年のだけではなくて、何年かの分が合冊になっておりました。あ、あ゛。1897年もあるぅ~♪
ちょっと、出直してきます。つづく~♪
デートと万年カレンダーによるジュディーの誕生日の推定はほんとにあっていたのか? Was the Supposition of Judy's Birthday from Dates and the Perpetual Calendar True [Daddy-Long-Legs]
ヴァッサー女子大学の『要覧 Catalogue』に掲載されている「学年暦 Calendar」を眺めながら、作家のジーン・ウェブスターはこのカレンダーを眺めながら『あしながおじさん』を書いたのかしら、などとぼんやり考えていたのですが、ふと暗い疑念がもたげてきて、調べたところ、過去の記事を訂正する必要が生じました。
8月末の記事「デートと万年カレンダー――ジュディーの誕生日 Dates and the Perpetual Calendar: Judy's Birthday」で、『あしながおじさん』の作品中で一箇所だけ日付と曜日の組み合わせが特定される、4年生の3月5日の手紙(手紙の冒頭で、明日が3月最初の水曜日だとジュディーはいう)から、4年生のカレンダーが何年だったのかを推定しました。以下が推定と結論の部分です――
ふと、思いついたように、ジーン・ウェブスターが卒業した1901年を調べてみます(この年のカレンダーは1878年、1889年、1895年、1907年、1918年、1929年、1935年、1946年、1957年などと同一です)――(1) [The Perfect Perpetual Calendar ] <http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/calendar/F.htm>。
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ビンゴ♪ 1901年の3月5日は火曜日、翌6日は月の第一水曜日でした。
そこで1年前の3年生の11月を確認します。
1900年11月の暦
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat __ __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ジュディーが、「私先週21になりました」と書いた11月9日は、作者ジーン・ウェブスターがカレンダーに忠実であったならば、日曜日でした。そうすると、単純には11月2日から8日まで。そして昨日や一昨日を「先週」とはふつうは呼ばないでしょうから(わかりませんが、日本人の感覚ではそうでしょう)、11月2日~6日までのあいだにしぼられるのではないでしょうか。
この推論は基本的に間違ってはいないと思うのですけれど、万年カレンダーが教える、(ウェブスターの卒業した1901年の暦は)「1878年、1889年、1895年、1907年、1918年、1929年、1935年、1946年、1957年などと同一」という情報につい目が曇って別の可能性に目が行かなかったのです。
それは1912年、すなわち、10月に『あしながおじさん』の初版がニューヨークのセンチュリー出版社から刊行される年のカレンダーです。下のは、Perpetual Calendar の日本語版というか、「あの日は何曜日? 10000年カレンダー」(「万年」じゃなくて「10000年」なんですが)というサイトの情報です。――
<http://www5a.biglobe.ne.jp/~accent/kazeno/calendar/1912.htm>
1年間の日付のすべてが1901年と同じであるのではありません。閏(うるう)月2月のあとの3月から同一です。1912年の3月5日は火曜日、翌6日は月の第一水曜日なのでした。
ですから、可能性としては、ウェブスターは1912年が卒業の年だったというリアルタイムの物語として『あしながおじさん』の時間を設定していたかもしれないのです。もちろん、その裏側で、自身のヴァッサー在学時のカレンダーと重ねていた可能性もありますけれど。 時代設定ということでいえば、スカートの長さから考えると、自身が大学生だった頃ではなくて、たかだか15~11年位かもしれませんけれど20世紀の1910年代のナウい丈にしているのではなかろうかと思われ〔スカート丈については「ジュディーとパティーのスカート丈 Skirt Length」参照〕。
1912年がオリンピックの開かれるうるう年であること、そして、ついでに言えば、1900年がオリンピックが開かれるけれど100年に1回の非うるう年だったことによって、カレンダーが乱れるとともにモーリちゃんの父の頭も乱れていたようなのでした。
なお、3年生の11月のカレンダーはつぎのようにだいぶズレていますです。――
1911年11月の暦
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| __ | __ | __ | 1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
21 |
22 |
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
__ | __ |
えーと、 3年生になったジュディーが、「私先週21になりました」と書いた11月9日は、作者ジーン・ウェブスターがカレンダーに忠実であったならば、木曜日でした。しぼりなおされるジュディーの誕生日は10月30日から11月4日でしょうか。
『あしながおじさん』でのシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』からの引用は明示してあるのになんで違っているんだろう [Daddy-Long-Legs]
間があいて、なんだか『あしながおじさん』から離れているなあ、とちょっと反省した師走です。
で、謎が解決されていないままの問題箇所をばーんと出して、冬休みの課題としたいと思います(わけわかめ)。2年生5月4日の手紙は、体育祭の報告から始まるのですが、前の夜に半分徹夜して『ジェーン・エア』を読んでいたことが途中で書かれています。ブロンテ姉妹については、『嵐が丘』を書いたエミリー・ブロンテについては1年生の春の手紙で言及があって、作家の置かれた環境と、作品を生み出す能力について、思索がちょっとだけ巡らされていましたが、孤児の娘を主人公とした『ジェーン・エア』はジュディーの生涯と響きあうところがあり(また、メタなレヴェルでは狂気の奥さんの存在を知るというジーンの生涯と重なるところもあり)、いよいよか、という感じがなきにしもあらず(しかし、あれこれ言うのは今回は控えます)。
さて、引用は、引用符つきと引用符なしと、二箇所あります。
<http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/150/mode/2up>
I sat up half of last night reading Jane Eyre. Are you old enough, Daddy, to remember sixty years ago? And, if so, did people talk thatway?
The haughty Lady Blanche says to the footman, "Stop your chattering, knave, and do my bidding." Mr. Rochester talks about the metal welkin when he means the sky; and as for the mad woman who laughs like a hyena and sets fire to bed curtains and tears up wedding veils and bites―it's melodrama of the purest, but just the same, you read and read and read. I can't see how any girl could have written such a book, especially any girl who was brought up in a churchyard. There's something about those Brontes that fascinates me. Their books, their lives, their spirit. Where did they get it? When I was reading about little Jane's troubles in the charity school, I got so angry that I had to go out and take a walk. I understood exactly how she felt. Having known Mrs. Lippett, I could see Mr. Brocklehurst.〔赤字・太字強調付加〕
(昨日の夜の半分は『ジェーン・エア』を読んで夜更かししました。ダディーって、六十年前を覚えているくらいのおとしですか? もしそうならば、昔の人ってあんなふうに話したのですか?
横柄なレディー・ブランチは従僕に言います――「無駄口は叩くでない、下男風情が。言いつけ通りにするのじゃ」 ミスター・ロチェスターは、空を意味して金属の雲居が云々なんて言ってるしー。それからあの狂女、ハイエナのように高笑いしたり、ベッドのカーテンに火をつけ、婚礼の衣装を引き裂き、人に噛みつくだなんて――これは純然たるメロドラマです、が、それでも、読んで読んで読まずにいられません。どうして女の子がこんな本を書けたのか、わたしにはわかりません。特に、教会の敷地から出ることなく育った娘なんかには。このブロンテ姉妹には、あたしを魅了するものが何かあります。彼女たちの本も、彼女たちの生涯も、彼女たちの精神も。彼女らはその精神をどこで得たのでしょう? 慈善学校でまだ小さいジェインが苦労するのを読んでいると、あんまり腹が立って、外に飛びだして散歩せずにいられませんでした。あの子がどんなふうに感じたか、わたしには痛いほどわかる。ミセス・リペットを知っているので、ミスタ・ブロックルハーストの姿をまざまざと目に浮かべられます。)
英語を赤字にした二箇所は、前後しますが、18章と15章に出てきます。なんとなく長めに引いておきます。関連部分を茶色の太字にしておきます。――
"You never felt jealousy, did you, Miss Eyre? Of course not: I need not ask you; because you never felt love. You have both sentiments yet to experience: your soul sleeps; the shock is yet to be given which shall waken it. You think all existence lapses in as quiet a flow as that in which your youth has hitherto slid away. Floating on with closed eyes and muffled ears, you neither see the rocks bristling not far off in the bed of the flood, nor hear the breakers boil at their base. But I tell you―and you may mark my words―you will come some day to a craggy pass in the channel, where the whole of life's stream will be broken up into whirl and tumult, foam and noise: either you will be dashed to atoms on crag points, or lifted up and borne on by some master-wave into a calmer current―as I am now.
"I like this day; I like that sky of steel; I like the sternness and stillness of the world under this frost. I like Thornfield, its antiquity, its retirement, its old crow-trees and thorn-trees, its grey facade, and lines of dark windows reflecting that metal welkin: and yet how long have I abhorred the very thought of it, shunned it like a great plague-house? How I do still abhor―"
He ground his teeth and was silent: he arrested his step and struck his boot against the hard ground. Some hated thought seemed to have him in its grip, and to hold him so tightly that he could not advance. (Chapter 15) 〔茶字・太字強調付加〕
"Indeed, mama, but you can―and will," pronounced the haughty voice of Blanche, as she turned round on the piano-stool; where till now she had sat silent, apparently examining sundry sheets of music. "I have a curiosity to hear my fortune told: therefore, Sam, order the beldame forward."
"My darling Blanche! recollect―"
"I do―I recollect all you can suggest; and I must have my will―quick, Sam!"
"Yes―yes―yes!" cried all the juveniles, both ladies and gentlemen. "Let her come―it will be excellent sport!"
The footman still lingered. "She looks such a rough one," said he.
"Go!" ejaculated Miss Ingram, and the man went.
Excitement instantly seized the whole party: a running fire of raillery and jests was proceeding when Sam returned.
"She won't come now," said he. "She says it's not her mission to appear before the 'vulgar herd' (them's her words). I must show her into a room by herself, and then those who wish to consult her must go to her one by one."
"You see now, my queenly Blanche," began Lady Ingram, "she encroaches. Be advised, my angel girl―and―"
"Show her into the library, of course," cut in the "angel girl." "It is not my mission to listen to her before the vulgar herd either:
I mean to have her all to myself. Is there a fire in the library?"
"Yes, ma'am―but she looks such a tinkler."
"Cease that chatter, blockhead! and do my bidding."
Again Sam vanished; and mystery, animation, expectation rose to full flow once more.
"She's ready now," said the footman, as he reappeared. "She wishes to know who will be her first visitor."
"I think I had better just look in upon her before any of the ladies go," said Colonel Dent. (Chapter 18) 〔茶字・太字・大字強調付加〕
15章のメタル・ウェルキンのほうは原文のままのフレーズで引用されています。welkin は、辞書を見ると、文語とか詩語で、「空」「大空」「上空」「天」「天空」とか書いてあります(ドイツ語のWolke (雲)と語源が同じで、古英語までさかのぼる古い言葉らしい)。小説のなかでは、その表現に至るまでにsky of steelという表現があったりして、金属のメタルの突飛さがやわらいでいるようです。
しかし、この、レディー・ブランチのセリフのブレ・ズレはなんなんでしょうか。a) ジーン・ウェブスターの記憶違い、b) ジーン・ウェブスターの意図的な改変、c) このように表記しているリトールド版みたいな別の版があった。
謎〔灰字・太字・大字強調付加〕
パックス・ティビ Pax Tibi [Daddy-Long-Legs]
朝からの会議に出たあと午後早くに帰宅し、osawa さんの残した更新日記(同時進行多方面のWEB作業の記録)をビール(ほんとうは発泡酒)を注ぎながら、あらためて感心しつつ飲んで、いや読んでいた師走の夕方でした。
2年生1月20日の手紙(バシュキルツェフの天才=狂気に言及した手紙のつぎの手紙)の〆の文句は独・仏・羅が並んでいます。それは外国語の勉強成果の開陳であるだけでなく、手紙本文で、自分の素性のわからなさをあらためて問題にし、ひょっとすると自分はアメリカ人ではないかもしれない(もっとも多くの人々がアメリカ人ではない)という移民の国アメリカに思いをはせる言葉があったり、ロシア人の子孫かもしれないし、ヴァイキングの娘かもしれないし、古代ローマ人の直系かもしれない、みたいなことをあれこれ書いたからでもあるでしょう。
Jean Webster, Daddy-Long-Legs (New York: Century, 1912) <http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/126/mode/2up>
「すごくおもろい手紙を今回は書くつもりだったので、申し訳ないです。」と言っているのは、孤児院時代の「スキャンダル」――クッキーを盗んだと責められて脱走を試みたけれど、4マイル走ったところで捕まり、一週間庭で見せしめに棒くいに縛られたという事件――を告白し、そしてそれを書いたところで鐘が鳴ってしまい、委員会に出るため手紙を〆たからです。(でも、あとから続けてもよかったわけですから、これは言い訳であり、それくらい、悲しいことを書いてしまった自分がいた、ということなのでしょうが。)
あと、追伸の、「完璧に確信していること」として、「自分は支那人ではない」というのが、どういう含みなのか、よくわかりません。が、当時は "Chinaman" という言い方自体は、derogatory (侮蔑的)ではなかったのは確かです(世紀末のフランク・ノリスの『マクティーグ』にも出てくるし、1920年代のフィッツジェラルドの小説にも出てくる)。
Auf wiedersehen アウフ・ヴィーダーゼーン(ではまた、さようなら(独))
Cher Daddy シェール・ダディー(親愛なる(仏)ダディー)
Pax tibi! パックス・ティビ!((羅))
で、つぎのようなノートを読んで、意外な読みに半分は感心したのでした――
- パックス・ティビ
- 訳注にも書きましたが、pax tibi=「脛骨の平和」の意味で、脛骨(tibia)は足長さん(Daddy-Long-Legs)の脚(leg)にひっかけた冗談です。
始めはなんのことだかさっぱり分からずじまい。 paxから、足長さんへのいたわりの言葉なのは予想がつくのですが、ラテン語、英語、フランス語の辞書をみても、tibiに類した言葉はtibiaしか見あたらず、成句としての意味も見つかりません。脛骨にからんだ言い伝えや民間信仰などがあるのか調べてみたけど、それらしいものもなし。最後にジュディの冗談の線で考えていたら、布団の中で眠りに着く直前、足長さんのlegとの関連にようやく気がつきました。でもそこで目がさえてしまって、しばらく眠れませんでしたけど。英語で考えていればすぐ気付くのでしょうね。
ちなみに、Pocket版のOxford Latin Dictionaryには、 tibi=reed-pipe(リードパイプ、オーボエ系の楽器)の意味しか載ってなくて、全くの役立たず。安物の辞書は百害あって一利なしです。値段だけは一人前なのに...
急いで手に取った翻訳がたまたま福音館の坪井郁美訳(1970)で、それはたまたまAuf wiedersehen にルビで「さようなら」、とCher Daddy に「おじさん」と振られて、その二行のあとは、「ジュディー」だけ。なぜかPax tibi が落ちていたのでした。
けれども続けて手にした恩地三保子訳は「いずれまた」にルビ「アウフ・ヴィーダゼーエン」、「だいすきなおじさま」にルビ「シェール・ダディ」、そして「ごきげんよう」に「パックス・ティビ」と書いています。角川文庫の厨川圭子訳はAuf wiedersehenに割注で(さようなら)〔Auf wiedersehen(さようなら)〕、「Cher(親愛なる)おじさん」、「Pax tibi(ご安泰を祈ります)」と、日本語に置き換えているのでした。
で、モーリちゃんの父の大学時代に途中で挫折したラテン語(ギリシア語も同様に挫折しました)の知識だと、tibi は二人称単数形人称代名詞の与格(目的格)です〔「あなたに」/to you〕。主格はフランス語と同じでtu。Pax は、Pax romana とか Pax americana とか言われるように、peace (平和)。
そして、あれこれ調べると、"Pax tibi" というフレーズはキリスト教がらみで見つかるようです。――
Pax tibi!: (Lt.) Peace (be) unto thee [you]! Long before the founding of the city, however, St. Mark is said to have traveled to the north of Italy and founded the first Christian community there. When he was traveling back to Rome by sea, his ship stopped at the islands which would one day become Venice. An angel appeared to him saying “Pax tibi, Marce, evangelista meus. Hic requiescet corpus tuum” (Peace unto you, Mark, my Evangelist. Here your body will rest). (http://www.catholicmatch.com/pl/pages/community/articles/details.html?ra=1;id=542)でもマルコの専用ではなくて、カトリックの洗礼式にも入っています。
| Deus omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum (hic inungit), ipse te liniat Chrismate salutis in eodem Christo Iesu Domino nostro in vitam æternam. R7 : Amen. Sacerdos: Pax tibi. R7 : Et cum spiritu tuo. | May Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given you new life through water and the Holy Ghost, and forgiven you all your sins (here he anoints the child) himself anoint you with saving Chrism in the same Jesus Christ our Lord, that you may have eternal life. R7 : Amen. Priest: Peace be with you. R7 : And with you. |
(http://members.aol.com/Genesis27Life/TradRiteBaptism.html)
「平和があなたに(あらんことを(願います))」 という意味だと思われ。複数だとPax vobis。浄罪界から10000年免除に値する Deserving Ten Thousand Years Out of Purgatory [Daddy-Long-Legs]
前の記事の Pax tibi がカトリックの祭式の文言なのかどうかは不確かですけれど、『あしながおじさん』に出てくるカトリック的なイメジとして気になっていた箇所(4年生4月12日)――
12th Jan.
Dear Mr. Philanthropist,
Your cheque for my family came yesterday. Thank you so much! I cut gymnasium and took it down to them right after luncheon, and you should have seen the girl's face! She was so surprised and happy and relieved that she looked almost young; and she's only twenty-four. Isn't it pitiful?
Anyway, she feels now as though all the good things were coming together. She has steady work ahead for two months―someone's getting married, and there's a trousseau to make.
'Thank the good Lord!' cried the mother, when she grasped the fact that that small piece of paper was one hundred dollars.
'It wasn't the good Lord at all,' said I, 'it was Daddy-Long-Legs.' (Mr. Smith, I called you.)
'But it was the good Lord who put it in his mind,' said she.
'Not at all! I put it in his mind myself,' said I.
But anyway, Daddy, I trust the good Lord will reward you suitably. You deserve ten thousand years out of purgatory.
Yours most gratefully,
Judy Abbott(慈善・家人《じぜん・いえと》様へ
例の家族のための小切手は昨日届きました。ありがとうございます! 昼食後に、体育の授業をサボってさっそく持って行きました。あの娘《こ》の顔を見せてあげたかった! あまりびっくりしたのと、幸せなのと、安心したので、若返ったみたいに見えたわ。 といってもまだ二十四歳でしかないんだけど。可哀想でしょ?
とにかく、まるで幸運があるだけまとめて舞い込んできたかのような気でいます。 二ヶ月先までずっと仕事もあるし -- どなたかもうすぐ結婚するので、その嫁入り仕度なの。
「ありがとうございます、恵み深き神よ!」と、お母さんはそう叫びました。 あの小さな紙切れが百ドルになるんだとようやく納得してくれたわけ。
「恵み深い神さまじゃなくて」とあたし、「足長父さん《メクラグモ》のおかげです。」 (ミスタ・スミスのおかげ、ちゃんとそう言ったわよ。)
「でも恵み深い神さまが、そう思いつかせて下さったんだわ」とお母さん。
「まさか!思いつかせたのはこのあたしです」とあたし。
それはともあれ、「父さん」、恵み深い神さまなら、きっと相応しく報いて下さることでしょう。 これで煉獄行きの一万年分くらいは儲けたわね。
ありがたく感謝している
ジュディ・アボット
〔osawa さん訳 <http://web.archive.org/web/20040915032219/www.sm.rim.or.jp/~osawa/AGG/daddy/daddy-67.html>〕)
煉獄(purgatory)というのは、ダンテの『神曲』で有名かもしれませんけれど、Heaven と Hell の中間にあって、地上の罪を浄める(そして最後の審判と「永遠の救済」(=いわゆる「選ばれし人」となる)を待つ)場所なので、浄罪界とも呼ばれます。ウィキペディアを引いておきます。――
煉獄(れんごく ラテン語: purgatorium)とは、キリスト教、カトリック教会の教義のひとつ。 すなわち、煉獄とは死後地獄へ至るほどの罪はないが、すぐに天国に行けるほどにも清くない魂が、その小罪を清めるため赴くとされる場所であるとする。第2バチカン公会議以降の教会の現代化の流れにより、現代のカトリック教会においても煉獄について言及されることはほとんどない。
煉獄の教義は、教会の東西分裂以降のカトリック教会にて成立した。このような経緯のため正教会では煉獄を認めない。またプロテスタント教派もルターを始めとして煉獄の教義を認めない。古くは「浄罪界」とも訳される。〔「煉獄」 Wikipedia < http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%89%E7%8D%84 >〕
贖宥状(しょくゆうじょう)とは16世紀、カトリック教会が発行した罪の償いを軽減する証明書。免償符、贖宥符とも。ラテン語の "indulgentia" の訳で、日本ではかつて「免罪符」と訳されていたが、"indulgentia" には免罪という意味はない上、贖宥状が「罪のゆるし」を与えるのではなく、「ゆるしを得た後に課せられる罪の償いを軽減する」ものであるため、「免罪符」 という訳語は適当ではないことに注意する必要がある。〔Wikipedia〕
/////////////////////////////////////////////
「贖宥状」 Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%96%E5%AE%A5%E7%8A%B6>
"Indulgence" Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Indulgence>
『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(1) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs [Daddy-Long-Legs]
天国煉獄地獄問題はむつかしいので先送りにします。そして、『あしながおじさん』の重箱のスミツツキは順序は適当なのですけれど、4年生1月12日の煉獄に言及する手紙の次の2月15日の手紙はサミュエル・ピープスなので、そちらに話を移してしまいます。
まずは、テキストを並べてみますか。
15th Feb.
May it please Your Most Excellent Majesty:
This morning I did eat my breakfast upon a cold turkey pie and a goose, and I did send for a cup of tee (a china drink) of which I had never drank before.
Don't be nervous, Daddy--I haven't lost my mind; I'm merely quoting Sam'l Pepys. We're reading him in connection with English History, original sources. Sallie and Julia and I converse now in the language of 1660. Listen to this:
"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition." And this: "Dined with my lady who is in handsome mourning for her brother who died yesterday of spotted fever."
Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? A friend of Pepys devised a very cunning manner whereby the king might pay his debts out of the sale to poor people of old decayed provisions. What do you, a reformer, think of that? I don't believe we're so bad today as the newspapers make out.
Samuel was as excited about his clothes as any girl; he spent five times as much on dress as his wife--that appears to have been the Golden Age of husbands. Isn't this a touching entry? You see he really was honest. 'Today came home my fine Camlett cloak with gold buttons, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it.'
Excuse me for being so full of Pepys; I'm writing a special topic on him.
What do you think, Daddy? The Self-Government Association has abolished the ten o'clock rule. We can keep our lights all night if we choose, the only requirement being that we do not disturb others--we are not supposed to entertain on a large scale. The result is a beautiful commentary on human nature. Now that we may stay up as long as we choose, we no longer choose. Our heads begin to nod at nine o'clock, and by nine-thirty the pen drops from our nerveless grasp. It's nine-thirty now. Good night. (Daddy-Long-Legs [Penguin Classics] 117-118)
Samuel Pepys (1633-1703)は、1660年から69年に書かれた Diary 、特に、Great Plague of London (1665-66) の疫病の記録で有名な英国の官僚、政治家です。仕立て屋に生まれますが、ケンブリッジ大学を卒業し、役人になり、1660年の王政復古下で、親戚のエドワード・モンタギューに推薦されて海軍の長官秘書(書記官)という地位にまで昇ります。妻のエリザベスはフランスから亡命してきたたプロテスタントの娘でした。
ピープスのE-text はいろいろあるみたいですけれど、注釈が挿入されている19世紀末の版が良いかな、と思います(Project Gutenberg)。もしかするとジュディー=ジーンが使用した版かもしれませんし。――THE DIARY OF SAMUEL PEPYS M.A. F.R.S. /CLERK OF THE ACTS AND SECRETARY TO THE ADMIRALTY /TRANSCRIBED FROM THE SHORTHAND MANUSCRIPT IN THE PEPYSIAN LIBRARY MAGDALENE COLLEGE CAMBRIDGE BY THE REV. MYNORS BRIGHT M.A. LATE FELLOW AND PRESIDENT OF THE COLLEGE (Unabridged) /WITH LORD BRAYBROOKE'S NOTES /By Samuel Pepys /Edited With Additions By
Henry B. Wheatley F.S.A. (London: George Bell & Sons, 1893) <http://www.gutenberg.org/files/157/157.txt> <http://www.gutenberg.org/files/4118/4118.txt>
<http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>
DIARY OF SAMUEL PEPYS.SEPTEMBER 1660
6th. This morning Mr. Sheply and I did eat our breakfast at Mrs. Harper's, (my brother John' being with me,) [John Pepys was born in 1641, and his brother Samuel took great interest in his welfare, but he did not do any great credit to his elder.] upon a cold turkey-pie and a goose. From thence I went to my office, where we paid money to the soldiers till one o'clock, at which time we made an end, and I went home and took my wife and went to my cosen, Thomas Pepys, and found them just sat down to dinner, which was very good; only the venison pasty was palpable beef, which was not handsome. After dinner I took my leave, leaving my wife with my cozen Stradwick,--[Elizabeth, daughter of Richard Pepys, Lord Chief Justice of Ireland, and wife of Thomas Stradwick.]--and went to Westminster to Mr. Vines, where George and I fiddled a good while, Dick and his wife (who was lately brought to bed) and her sister being there, but Mr. Hudson not coming according to his promise, I went away, and calling at my house on the wench, I took her and the lanthorn with me to my cosen Stradwick, where, after a good supper, there being there my father, mother, brothers, and sister, my cosen Scott and his wife, Mr. Drawwater and his wife, and her brother, Mr. Stradwick, we had a brave cake brought us, and in the choosing, Pall was Queen and Mr. Stradwick was King. After that my wife and I bid adieu and came home, it being still a great frost.
25th. To the office, where Sir W. Batten, Colonel Slingsby, and I sat awhile, and Sir R. Ford[Sir Richard Ford was one of the commissioners sent to Breda to desire Charles II. to return to England immediately.] coming to us about some business, we talked together of the interest of this kingdom to have a peace with Spain and a war with France and Holland; where Sir R. Ford talked like a man of great reason and experience. And afterwards I did send for a cup of tee [That excellent and by all Physicians, approved, China drink, called by the Chineans Tcha, by other nations Tay alias Tee, is sold at the Sultaness Head Coffee-House, in Sweetings Rents, by the "Royal Exchange, London." "Coffee, chocolate, and a kind of drink called tee, sold in almost every street in 1659."--Rugge's Diurnal. It is stated in "Boyne's Trade Tokens," ed. Williamson, vol. i., 1889, p. 593 "that the word tea occurs on no other tokens than those issued from 'the Great Turk' (Morat ye Great) coffeehouse in Exchange Alley. The Dutch East India Company introduced tea into Europe in 1610, and it is said to have been first imported into England from Holland about 1650. The English "East India Company" purchased and presented 2 lbs. of tea to Charles II. in 1660, and 23 lbs. in 1666. The first order for its importation by the company was in 1668, and the first consignment of it, amounting to 143 lbs., was received from Bantam in 1669 (see Sir George Birdwood's "Report on the Old Records at the India Office," 1890, p. 26). By act 12 Car. II., capp. 23, 24, a duty of 8d. per gallon was imposed upon the infusion of tea, as well as on chocolate and sherbet.] (a China drink) of which I never had drank before, and went away. Then came Col. Birch and Sir R. Browne by a former appointment, and with them from Tower wharf in the barge belonging to our office we went to Deptford to pay off the ship Success, which (Sir G. Carteret and Sir W. Pen coming afterwards to us) we did, Col. Birch being a mighty busy man and one that is the most indefatigable and forward to make himself work of any man that ever I knew in my life. At the Globe we had a very good dinner, and after that to the pay again, which being finished we returned by water again, and I from our office with Col. Slingsby by coach to Westminster (I setting him down at his lodgings by the way) to inquire for my Lord's
OCTOBER 1660
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
JULY 1661
3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed.
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
JULY 1660
July 1st. This morning came home my fine Camlett cloak, [Camlet was a mixed stuff of wool and silk. It was very expensive, and later Pepys gave L24 for a suit. (See June 1st, 1664.)] with gold buttons, and a silk suit, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it. I went to the cook's and got a good joint of meat, and my wife and I dined at home alone. In the afternoon to the Abbey, where a good sermon by a stranger, but no Common Prayer yet. After sermon called in at Mrs. Crisp's, where I saw Mynheer Roder, that is to marry Sam Hartlib's sister, a great fortune for her to light on, she being worth nothing in the world. Here I also saw Mrs. Greenlife, who is come again to live in Axe Yard with her new husband Mr. Adams. Then to my Lord's, where I staid a while. So to see for Mr. Creed to speak about getting a copy of Barlow's patent. To my Lord's, where late at night comes Mr. Morland, whom I left prating with my Lord, and so home.
うわっ。字が多すぎて見にくいですね。色付けをしてなんとか対応をわかりやすくしてみます。
と書いたときには真っ黒だったのですけれど、色とりどりにしても距離がありすぎてわからんですねー。出直してきます。
あ、最後っ屁的にひとつだけ注釈をば・・・・・・ピープスがチャリング・クロスで処刑を目撃したMajor Harrisonというのは、Thomas Harrison (1608[06?]-October 13, 1660).というピューリタン革命の際の海軍軍人で、国王Charles 1世の死刑執行令状に署名したひとりでしたが、Cromwell に対する反乱を疑われて投獄(1655)され、王政復古の際にも妥協も亡命も拒んで処刑されたのでした。quarter という動詞は「四」に関係ありそうですけれど、辞書を見ると《古》罪人の死体を四つ裂きにする」「手足をばらばらにする(dismember)」などと書かれています。絞首して死んだ後に四つ裂きにするのですね。
『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(2) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (2) [Daddy-Long-Legs]
重箱の隅をつつくという姿勢を忘れていたことに気づきました。細かくいきます。
4年生2月15日の手紙。
15th Feb.
May it please Your Most Excellent Majesty:
This morning I did eat my [←our] breakfast upon a cold turkey[-]pie and a goose, and I did send for a cup of tee (a china drink) of which I had never drank before.
(謹みてやんごとなき陛下にお伺い申し上げ候
今朝まっこと私は七面鳥の冷製パイと鵞鳥をば朝食にいただき、かつて飲したことのない茶(支那の飲料)を一杯まっこと所望いたしました。)
この本文の最初のパラグラフは、サミュエル・ピープスの1660年9月6日の日記と同月25日の日記の飲食の文章の貼りあわせでできています。9月6日の日記では、Sheply 氏(この人は、ピープスの親戚で彼を重用してくれたエドワード・モンタギューの使用人です)と一緒に、かつ弟のJohn も伴って、Harper's (これは店で、はーパー夫人というのがおかみではないかと思うのですが不詳)で朝飯から肉類を食ってから仕事場に行って兵士に給料を手渡し、帰宅後妻のエリザベスといとこのトマス・ピープスの家へ行き、ちょうど昼飯(dinner) のところで、どうやらそれを相伴して、いとこのストラドウィックのところに妻を残してウェストミンスターにヴァインズ氏を訪ね、ヴァイオリンを弾き(? fiddled)、でもハドソン氏が来なかったので家に戻って女中とランタンを伴って再びいとこのストラドウィックの家に行って、たらふく〔昼飯も "good" と言っているので、単純に「おいしい」かも。それだと、語彙不足の感いなめず〕夕食を食い、そこには父と母と兄弟と妹といとこのスコットとその妻とドローウォーター氏とその妻とその弟と、ストラドウィック氏がいて、立派なケーキをもってこさせた。それから暇乞いをして我が家に戻った、みたいなことがダラダラと書かれています。へたくそな英語だこと。
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
SEPTEMBER 16606th. This morning Mr. Sheply and I did eat our breakfast at Mrs. Harper's, (my brother John being with me,) upon a cold turkey-pie and a goose. From thence I went to my office, where we paid money to the soldiers till one o'clock, at which time we made an end, and I went home and took my wife and went to my cosen, Thomas Pepys, and found them just sat down to dinner, which was very good; only the venison pasty was palpable beef, which was not handsome. After dinner I took my leave, leaving my wife with my cozen Stradwick, and went to Westminster to Mr. Vines, where George and I fiddled a good while, Dick and his wife (who was lately brought to bed) and her sister being there, but Mr. Hudson not coming according to his promise, I went away, and calling at my house on the wench, I took her and the lanthorn with me to my cosen Stradwick, where, after a good supper, there being there my father, mother, brothers, and sister, my cosen Scott and his wife, Mr. Drawwater and his wife, and her brother, Mr. Stradwick, we had a brave cake brought us, and in the choosing, Pall was Queen and Mr. Stradwick was King. After that my wife and I bid adieu and came home, it being still a great frost.
25th. To the office, where Sir W. Batten, Colonel Slingsby, and I sat awhile, and Sir R. Ford coming to us about some business, we talked together of the interest of this kingdom to have a peace with Spain and a war with France and Holland; where Sir R. Ford talked like a man of great reason and experience. And afterwards I did send for a cup of tee (a China drink) of which I never had drank before, and went away. Then came Col. Birch and Sir R. Browne by a former appointment, and with them from Tower wharf in the barge belonging to our office we went to Deptford to pay off the ship Success, which (Sir G. Carteret and Sir W. Pen coming afterwards to us) we did, Col. Birch being a mighty busy man and one that is the most indefatigable and forward to make himself work of any man that ever I knew in my life. At the Globe we had a very good dinner, and after that to the pay again, which being finished we returned by water again, and I from our office with Col. Slingsby by coach to Westminster (I setting him down at his lodgings by the way) to inquire for my Lord's coming thither (the King and the Princess.
そして9月25日の日記では、職場で国際情勢について談話した後、中国茶を注文にやった、みたいに書かれています。このtee は、Braybrooke(ならびにHenry B. Wheatleyの追補)の注釈で、以下のように詳しい歴史的説明があります。――
[That excellent and by all Physicians, approved, China drink, called
by the Chineans Tcha, by other nations Tay alias Tee, is sold at the
Sultaness Head Coffee-House, in Sweetings Rents, by the "Royal
Exchange, London." "Coffee, chocolate, and a kind of drink called
tee, sold in almost every street in 1659."--Rugge's Diurnal. It is
stated in "Boyne's Trade Tokens," ed. Williamson, vol. i., 1889,
p. 593 "that the word tea occurs on no other tokens than those
issued from 'the Great Turk' (Morat ye Great) coffeehouse in
Exchange Alley. The Dutch East India Company introduced tea into
Europe in 1610, and it is said to have been first imported into
England from Holland about 1650. The English "East India Company"
purchased and presented 2 lbs. of tea to Charles II. in 1660, and 23
lbs. in 1666. The first order for its importation by the company
was in 1668, and the first consignment of it, amounting to 143 lbs.,
was received from Bantam in 1669 (see Sir George Birdwood's "Report
on the Old Records at the India Office," 1890, p. 26). By act 12
Car. II., capp. 23, 24, a duty of 8d. per gallon was imposed upon
the infusion of tea, as well as on chocolate and sherbet.]<http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>
オランダの東インド会社が茶をヨーロッパにもたらしたのが1610年、オランダからイギリスに最初に輸入されたのが1650年ごろといわれているとか、あれこれ薀蓄が書かれています(詳細の訳は省略)。ピープスはコーヒーハウスに茶を注文に人をやったということなんでしょうか。そのあとの "and went away" って誰なんでしょう。わからず。一度仕事場を離れたということなのでしょうか。でも会見を約束していた人間がそのあとやってきます。いやあ、まったくわかりません。で、また飯を食っています。
ともあれ、こういう次第で、ジュディー=ジーンは、違う日付の日記エントリーを合成し、代名詞を変えたり、あるいはなぜか大文字のChinaを小文字のchina に変えたりしています(これは編集者のミス・誤解による改変かも知れず――ふつう「中国の」の意味の形容詞はChinese でしょうし、china だと形容詞としては「陶磁器製の」の意味ですから)。
あと、目に付くのは、"did eat" と "did send" という、今の英語だと「強調」とされる動詞の過去形のつくりかたで、明らかにジュディー=ジーンはそのへんを面白がっているとまっこと思われました。
それから、冒頭の "May it please Your Most Excellent Majesty" もピープスの日記から引いてきたものです。これは、1660年10月7日の手紙で、国王に手紙を書こうとしている人間に添削の相談を受けたことを書き記し、記憶に残っている手紙の文言を日記に書き留めているなかに出てくるのです。――
[. . .] And as much of the letter as I can remember, is thus:
"May it please your Most Excellent Majesty," and so begins. (「謹みてやんごとなき陛下にお伺い申し上げ候」とかなんとかいうふうに始まる)
"That he yesterday received from General Monk his Majesty's letter and direction; and that General Monk had desired him to write to the Parliament to have leave to send the vote of the seamen before he did send it to him, which he had done by writing to both Speakers; but for his private satisfaction he had sent it thus privately (and so the copy of the proceedings yesterday was sent him), and that this come by a gentleman that came this day on board, intending to wait upon his Majesty, that he is my Lord's countryman, and one whose friends have suffered much on his Majesty's behalf. That my Lords Pembroke and Salisbury are put out of the House of Lords. That my Lord is very joyful that other countries do pay him the civility and respect due to him; and that he do much rejoice to see that the King do resolve to receive none of their assistance (or some such words), from them, he having strength enough in the love and loyalty of his own subjects to support him. That his Majestyhad chosen the best place, Scheveling, for his embarking, and that there is nothing in the world of which he is more ambitious, than to have the honour of attending his Majesty, which he hoped would be speedy. That he had commanded the vessel to attend at Helversluce--[Hellevoetsluis, in South Holland]--till this gentleman returns, that so if his Majesty do not think it fit to command the fleet himself, yet that he may be there to receive his commands and bring them to his Lordship. He ends his letter, that he is confounded with the thoughts of the high expressions of love to him in the King's letter, and concludes, "Your most loyall, dutifull, faithfull and obedient subject and servant, E. M."
ということで、ピープスの日記のなかの、手紙について(引用的に)書かれている部分を、手紙になかば引用的に利用している、ジュディーなのでした。
『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(3) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (3) [Daddy-Long-Legs]
細かく刻んで進みます。
4年生2月15日の手紙の全文はその1に載せました(日本語訳は付けませんでしたが)。つづく第2・第3段落です。
あ、ここではセンチュリー初版(1912) のファクシミリを載せておきます、やっぱり。
(クリックで拡大)
あら。最初の"May it . . ." のところってイタリック(斜体)だったのね。 ・・・・・・うわっ。直さなくっちゃ。
Don't be nervous, Daddy―I haven't lost my mind; I'm merely quoting Sam'l Pepys. We're reading him in connection with English History, original sources. Sallie and Julia and I converse now in the language of 1660. Listen to this:
"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition." And this: "Dined with my lady who is in handsome [←some] mourning for her brother who died yesterday of spotted fever."
(心配なさらないで、ダディー――わたしは気がヘンになってはいません。サミュル・ピープスを引用しているだけです。「英国史」がらみでわたしたちはピープスを読んでいます、原典を。サリーとジュリアとわたしはいま1600年の言葉で会話をしています。聞いてみてください――
「チャリング・クロスに、ハリソン少佐が絞首され引き回され〔臓腑を抜かれ drawn の意味については「Hanged, Drawn and Quartered」で検証しました〕四つ裂きにされるさまを見物に出かけた。彼はかような状況で可能な限り陽気そうに見えた。」 それからこれ――「昨日発疹チフスで死んだ兄のためたっぷり喪に服している夫人と外食をした」)
この英語は、特に古い文体という感じはしないと思われますし、死を平然と扱うさまに違和感を覚えて引いているのではないかと思われます(がよくわかりません)。特殊なスタイルの英語を会話に入れて遊ぶというのは、以前の、スティーヴンソンの海賊・海事用語をジャーちゃんと言い合いした夏のエピソードを思い起こさせます。 osawaさんは工夫しておもしろみが出るように訳していました――「チャリング・クロスにまかり越し、ハリソン少佐が絞首の後、四肢を四つ裂きにされる様を見届けたり。かくの如き立場にありし者に比し、愉しげなること是に過ぐる者なかるべし。」それからこれも。「喪中にて見目麗しく装ひたる奥方と夕餉を共にす。奥《あれ》の兄が昨日、斑点熱で死におほせたればなり。」 ©osawa
もとになったピープスの日記の文章は1660年10月13日(トマス・ハリソンの処刑)と1661年7月3日の、それぞれ冒頭近くです。
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
OCTOBER 1660
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
JULY 1661
3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed.
「四つ裂き」がどういう形式か調べがついていませんが、ピープスの日記のつづく部分では、切り刻まれたハリソンのクビ(頭)と心臓が人々に示され、歓喜の声があがったこと、死ぬ前にハリソンが、自分を裁いたものを裁くべく、キリストとともに必ず再臨すると言ったそうだということなど書かれています。あと、カキを食ってから家に帰ったら、ものが散らかっているので奥さんに怒って、腹立ちまぎれにオランダ土産のカゴを蹴飛ばして壊してしまってまいった、など書かれています。
7月3日の手紙のmy Lady というのは、その奥さんのエリザベスですが、〔間違えていました。二日記のなかでmy Lady と呼ばれるのはさまざまな奥方です――my Lady Wrightとかmy Lady Pickeringとかmy Lady Monkとか〕フランスから移民してきたプロテスタント(ユグノー)の娘でした(1655年、Elisabeth de St. Michel が14歳のときにSamuel と結婚)。〔Crewe という注も考えあわせると、この夫人はJohn Crewe の娘で、Sir Edward Montagu (1625生まれ) の妻のJamima [Jemima, Jamimah] と考えて間違いないと思います。要するに、 Edward Montagu が名指されているので、my Lady はその夫人となるのでした〕日記では、the Wardrobe (これは1666年のロンドンの大火で焼けおちたthe Great Wardrobe という建物のことだと思われ)に行き、そこで (there) 奥方と夕食をとった、と書かれており、それを、ただ「奥方と食事をした Dined with my lady 」だけにするのは、なんだか文章として変だと思います(情報がふつうすぎるから)。それから、日記の原文は "in some mourning" と、曖昧なことばづかいになっているのを、ジュディー=ジーンは、some を handsome に改変しています。おちゃめです。
spotted fever はおそらく発疹チフスだと思うのですが、エリザベスもtyphoid fever にかかってサミュエルはおおいに心配します。ふたりの関係は、少なくともサミュエルには愛人が複数おり、いっぽうサミュエルは妻を疑って嫉妬に燃えたりしていたようです。エリザベスは1669年で若死にしてしまいます。

Elisabeth Pepys, c.1666 (1640-69) image via Wikimedia <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizabeth_Pepys.jpg>

Samuel Pepys, c.1666 (1633-1703) image via Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Samuel_Pepys.jpg>
/////////////////
1660年の日記 <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>
1661年の日記 <http://www.gutenberg.org/files/4131/4131-h/4131-h.htm>
"Elizabeth Pepys (wife, b. St Michel)" in The Diary of Samuel Pepys: Dairy entries from the 17th century London diary <http://www.pepysdiary.com/p/150.php>
Hanged, Drawn and Quartered――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(4) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (4) [Daddy-Long-Legs]
〔直前の記事「『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(3) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (3)」の補足的な記事です〕
サミュエル・ピープスの日記におけるトマス・ハリソンの処刑目撃のくだりは有名で、英語のウィキペディアの "Thomas Harrison" にもピープスが言及され、また、ピープスの言葉に由来するパブが紹介されています。――
Samuel Pepys wrote an eyewitness account of the execution at Charing Cross, in which Major General Harrison was dryly reported to be "looking as cheerful as any man could do in that condition". This account is also quoted on a large plaque on the wall of the Hung, Drawn and Quartered public house near Pepys Street, where the diarist lived and worked in the Navy Office. In his final moments, as he was being led up the platform, the hang-man asked for his forgiveness. Upon hearing his request Thomas Harrison replied, "I do forgive thee with all my heart... Alas poor man, thou doith it ignorantly, the Lord grant that this sin may be laid to thy charge." Thomas Harrison then gave all of the money that remained in his pockets to his executioner and was thereafter executed. [“Thomas Harrison,” Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Harrison_(soldier) >]
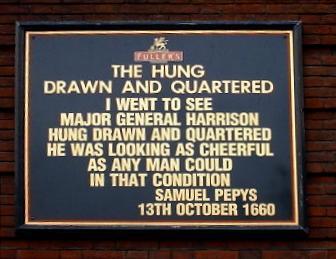
image via Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hdq.png>
ピープス・ストリートのパブ "The Hung Drawn and Quartered" の plaque (看板)にはジュディーが引いているのと同じ箇所が引かれています。が、ちょっとまた英語が編集されているようです。
ピープスの日記原文――"I went out to Charing Cross, to see Major-general Harrison hanged, drawn; and quartered; which was done there, he looking as cheerful as any man could do in that condition."
ジュディーの手紙――"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition."
看板――"I went to see Major General Harrison hung drawn and quartered /He was looking as cheerful as any man could in that condition"
ところで、ピープスの日記のつづく一文、"He was presently cut down, and his head and heart shown to the people, at which there was great shouts of joy." (彼はまもなく(絞首のロープを切って)降ろされ、首と心臓とが人々に示され、大きな歓喜の叫びがあがった)を昨日の夜読んで、眠っている間に自分の間違いに気づきました。 "cut down" は「切り刻まれ」ではないような気がしますが、行なわれていることは死体の切断であることは確かです。で、 "drawn" の意味を、辞書でいうと「《史》(罪人を)すのこそり(hurdle) などに載せて刑場に引いていく」という、我が国の「引き回し」みたいに考えていたのですが、それだと時間の順序があいません。となると、「引き抜く」「抜き取る」のほうのdraw で、リーダーズ英和辞典だと「〈鳥など〉のはらわたを抜く」というのと類推的に、内臓を抜くことかな、と。
オックスフォード英語辞典を見ます。「引き回し」については4番の "To drag (a criminal) at a horse's tail, or on a hurdle or the like, to the place of execution; formerly a legal unishment of high treason." とあるものです。1568年の用例――"Because he came of the bloud royal.. he was not drawne, but was set upon an horse, and so brought to the place of execution, and there hanged." 王家の血筋(bloud royal) なので "draw" はされず馬に乗せられて処刑場まで行き、そこで絞首された、ということです。1769年の用例――"That the offender [in cases of high treason] be drawn to the gallows, and not be carried or walk." 大罪の場合には罪人は絞首台まで "draw" される、ということです。そして1890年の用例(伝記辞典の記載)――"[Garnett] was sentenced to be drawn, hanged, disembowelled, and quartered." ガーネットさんの刑は、"draw" そして"hang" そして "disembowel" そして "quarter" という内容です。
この最後の用例のなかの "disembowel(led)" というのが「はらわたを抜き出す」「腹を裂く」という意味であって、draw はやっぱり「引き回し」ですねー。
そうして、「わたぬき」のほうのdraw は50番に出てきます。――
To draw out the viscera or intestines of; to disembowel (a fowl, etc. before cooking, a traitor or other criminal after hanging). 〔内臓や腸を抜き取る;はらわたを抜き出す(disembowel) (調理の前に家禽など、絞首のあとに謀反人や罪人を)
そして、この定義には、腑に落ちる説明がポイントを落として添えられているのでした。――
In many cases of executions it is uncertain whether this, or sense 4, is meant. The presumption is that where drawn is mentioned after hanged, the sense is as here.〔処刑の多くの事例で、この意味か、あるいは4番の意味なのか、確かでない。絞首 (hanged)のあとに drawn が言及されているならば、この意味であると推定される〕
なるほどね。
ということで hanged, drawn, and quartered は絞首、臓物引き抜き、四つ裂き、でした。翻訳を見たら、drawn を訳し落としているものもあるけれど、遠藤寿子も厨川圭子も、臓腑を引き抜く、とちゃんと訳しておりました。失礼。
あら、ウィキペディアの Thomas Harrison を読み直していたら、"hanged, drawn and quarterd" のフレーズが青くなってリンクがありました。げげげー。項目が立っています。 "Hanged, drawn and quartered" <http://en.wikipedia.org/wiki/Hanged,_drawn_and_quartered> 。しかも日本語のウィキペディアにも「首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑」として対応記事がありました。失礼。
なお、英語のほうには免責的な注記はありませんが、日本語のほうは「この項目には暴力的または猟奇的な記述・表現が含まれています。」と冒頭に掲げられているので、よい子は見ないほうがいいです。
しかし、自分は読んでたいへん腑に落ちました。英語のほうには、ここでもまたパブのプラックとピープスの日記が合わせて引用されています。
なお、トマス・ハリソンは国王チャールズ1世の処刑執行令状に署名したひとりで、それによってあとから王政復古後に、"regicide" (国王殺し; 弑逆罪,大逆罪)に問われたのです。英国史で大文字で the Regicides というとチャールズ1世を死刑に処した高等法院判事たちのことを指すのだそうです。フランス史だとルイ16世を死刑に処した国民公会のメンバーたち。
Handsome Mourning と Some Mourning――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(5) (Hand)Some Mourning: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (5) [Daddy-Long-Legs]
Don't be nervous, Daddy―I haven't lost my mind; I'm merely quoting Sam'l Pepys. We're reading him in connection with English History, original sources. Sallie and Julia and I converse now in the language of 1660. Listen to this:
"I went [out] to Charing Cross to see Major Harrison hanged, drawn and quartered: he looking as cheerful as any man could do in that condition." And this: "Dined with my l [←L]ady who is in handsome [←some] mourning for her brother who died yesterday of spotted fever."
(心配なさらないで、ダディー――わたしは気がヘンになってはいません。サミュル・ピープスを引用しているだけです。「英国史」がらみでわたしたちはピープスを読んでいます、原典を。サリーとジュリアとわたしはいま1600年の言葉で会話をしています。聞いてみてください――
「チャリング・クロスに、ハリソン少佐が絞首され引き回され〔臓腑を抜かれ drawn の意味については「Hanged, Drawn and Quartered」で検証しました〕四つ裂きにされるさまを見物に出かけた。彼はかような状況で可能な限り陽気そうに見えた。」 それからこれ――「昨日発疹チフスで死んだ兄のためたっぷり喪に服している夫人と外食をした」) [Penguin Classics 117]この英語は、特に古い文体という感じはしないと思われますし、死を平然と扱うさまに違和感を覚えて引いているのではないかと思われます(がよくわかりません)。
[・・・・・・]
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
JULY 1661
3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed.〔「『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(3) Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (3)」〕
自分の前の記事を引用しちゃったりして、父としていや遅々として進みませんがご容赦を。
ジュディーはサミュエル・ピープスの日記原文の "in some mourning for her brother" を"in handsome mourning for her brother" に変更しています。この改変によって何が起こったのか、気になって気になって。
というのも、自分は "some" という、漠然とした量を、"handsome" (=considerable) というたっぷりした量の「喪」に変更したとばかり考えておったのですけれど、『あしながおじさん』の翻訳の多くは、ピープスの奥さんが派手な喪服で着飾っているさま、ととっておるからです。
mourning という言葉は抽象的に「喪」の意味と、具象的に「喪服」の意味があります。 だから、"handsome mourning" というフレーズになったとたんに「喪」ではなくて「喪服」という具体性を帯びて読まれるのは、わかります。以下はなかばひまつぶしに "handsome mourning" の具体例の列挙です。個人的には葬式・埋葬関係の歴史への興味をひきずっており。
.jpg)
1860年代の喪服 image via 19th Century Mourning Clothing <http://19thcenturyartofmourning.com/19th_century_mourning_clothing.htm>
(1) イギリスの女性作家 Elizabeth Gaskell (1810-65) の小説 Ruth (1853) の第36章 "The End"――
Mrs. Farquhar had comforted the bitterness of Sally's grief by giving her very handsome mourning. At any rate, she felt oddly proud and exulting when she thought of her new black gown; but, when she remembered why she wore it, she scolded herself pretty sharply for her satisfaction, and took to crying afresh with redoubled vigour. She spent the Sunday morning in alternately smoothing down her skirts and adjusting her broad hemmed collar, or bemoaning the occasion with tearful earnestness. But the sorrow overcame the little quaint vanity of her heart, as she saw troop after troop of humbly-dressed mourners pass by into the old chapel. They were very poor--but each had mounted some rusty piece of crape, or some faded black ribbon. The old came halting and slow--the mothers carried their quiet, awe-struck babes. <http://books.google.co.jp/books?id=2PZxjZYnNQUC&pg=PT296&lpg=PT296&dq=%22handsome+mourning%22&source=bl&ots=gXtlbYyUPv&sig=ZCJQXHwZdohieVBW7xpUBenTGDs&hl=ja&ei=4642S9WLI43e7AOXxeD2CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CC4Q6AEwBw#v=onepage&q=%22handsome%20mourning%22&f=false>
ファーカー夫人 (Mrs. Farquhar) の新調の黒のガウンは、粗末ななりをした貧しい弔問者たちの 一団 (troop after troop of humbly-dressed mourners) と対比されていて、 "handsome mourning" は、やはり喪服の立派さにかかわるのでしょうか。あ、つうか、giving とあるので、サリーに与えた喪服が mourning ですか。ですね。
(2) イギリスの女性児童作家 Charlotte Yonge (1823-1901) のThe Two Sides of the Shield の第6章 "Persecution"――
Nor had her [Dolores'] handsome mourning been taken from her and old clothes of her cousin substituted for it. No, but she had been cruelly pulled about between Mrs. Halfpenny and the Silverton dressmaker with a mouthful of pins; and Aunt Lily had insisted on her dress being trimmed with velvet, instead of the jingling jet she preferred. <http://www.archive.org/stream/twosidesofshield00yonguoft#page/86/mode/2up/search/mourning>
いとこの古着に替えられなかった "it" が handsome mourning なので、明らかに喪服の意味です。
(3) 1802年Mount Vernon のMartha Washington という女性がしたためた遺言状――
Item it is my will and desire that Anna Maria Washington the daughter of my niece be put into handsome mourning at my death at the expense of my estate and I bequeath to her ten guineas to buy a ring. (一つ。私の姪の娘アンナ・マライア・ワシントンが私の死に際して私の遺産からの出費により "handsome mourning" に服せるよう希望し遺言する。また、指輪を一個買うために10ギニーを遺贈する。) <http://www.fairfaxcounty.gov/courts/circuit/pdf/mwtranscript.pdf>
「服せる」と訳しましたが "put into" は「着せる」の意味でやっぱり服なんでしょうか。指輪は喪とは別件なのか不明。
(4) Romance Readers and Romance Writers: A Satirical Novel (BY THE AUTHOR OF ‘A PRIVATE HISTORY OF THE COURT OF ENGLAND, &C.’) (London, 1810) の第16章 "New Character" ――
She was immediately put in possession of a beautifully decorated dressing-room and bed-chamber, which, with all her native sweetness and polish of manners, Mrs. Davenport desired her, while she gave her at the same time a kind embrace, to consider her own.
Margaret had been put into very handsome mourning for her uncle, at Mrs. Davenport’s expence: she was now in a fine black cloth riding-habit, and being in sables, her dress she knew would be soon adjusted for their seven o’clock dinner, and throwing off her hat, she sat down on a superb sofa-bed, to admire all around her, and feast her eyes with the beauty of that apartment, which she had been told to consider as her own.
The beautifully devised little fire-screens, the emigrant bellows, and the portable book-cases, all shewed the opulence of their possessors, and the elaborate skill of the artist; they were not only tasteful trifles, they were costly; of the most expensive materials, and of the choicest and most difficult to be obtained foreign wood that could be purchased. <http://www.chawton.org/library/novels/files/Romance2.html>
このロマンス批判ノヴェルに出てくる "handsome mourning" は前置詞 for と一緒になっているのですけれど、服なのでしょうね。ダヴェンポート夫人がお金を出してくれて、おじさんのための喪服を身につけたという。
(5) Recollections of a French Marchioness (London, 1846) 第7章――
She preceded us as far as a sort of throne-room filled with ecuyers, pages, and other gentlemen belonging to her, all dressed in handsome mourning, as well as their mistress, on account of the King's death; for the innovations of the Duchesse de Berry had not penetrated the gilded and emblazoned gratings of the Hotel de Lesdiguieres. <http://www.archive.org/stream/recollectionsoff01londiala/recollectionsoff01londiala_djvu.txt>
やっぱり服なのかしら。
(6) Charlotte M. Brame (Charlotte Monica), 1836-1884 の Dora Thorne 第19章――
[. . .] She wrote to the Elms, telling Dora of her husband's death, and announcing her own coming; then the little household understood that their quiet and solitude had ended forever.
The first thing was to provide handsome mourning. Dora was strangely quiet and sad through it all. The girls asked a hundred questions about their father, whom they longed to see. They knew he had left home in consequence of some quarrel with his father--so much Lady Earle told them--but they never dreamed that his marriage had caused the fatal disagreement; they never knew that, for their mother's sake, Lady Earle carefully concealed all knowledge of it from them. <http://www.sveninho.com/book/1871137/Dora-Thorne/num_218.html>
(7) Hesba Stretton の小説 Carola 第4章 "The Book and Its Captive"――
"You ought to go to your parish priest," the chaplain at the cemetery had said to her; he who had given her the book. This she would do at once; and in eager haste she dressed herself in the handsome mourning she had not worn since the day of the funeral. She descended the ladder into the room, where Matthias was ceremoniously washing his hands up to the elbow, before sitting down to the frugal supper. Her face was pale, but her dark eyes shone with suppressed excitement. <http://www3.shropshire-cc.gov.uk/etexts/E000423.htm>
この一節では、めずらしく冠詞 the がくっついていて(「葬儀の日から着ていなかった」という限定が関係代名詞(省略)節で就職修飾〔2010.11.29訂正〕されて限定されているからです)、"dressed" や "worn" という動詞とのつながりもあるし、ああ、やっぱり服なのね、と納得します。
(8) ヨークシアの女性の1824年9月の記述――
from Celebrating women's history [From History to Her Story: Yorkshire Women's Lives On-Line, 1100 to the Present]<http://www.historytoherstory.org.uk/article_pdf/42.pdf?PHPSESSID=40ebb91ee76dd8398f57769b18be3c6e>
この文章は読みにくくてよくわからないのですけれど、"all the English were in handsome mourning" とされているけれど、Sorteval氏が実際に言ったのは "all the English were in mourning" だった、ということです。ここにおける "mourning" は、喪服ではなくて「喪」の意味なのでしょうか?
(ようやく)ひるがえって、ピープスの日記の原文の "in some mourning for his brother" のmourning は服の意味なのでしょうか? 喪服の場合に "some" というのはなんだかヘンです(とモーリちゃんの父には最初から思われたわけです)。もっとも「ちょっとした」とか「けっこうな」みたいな、informal な "some" というのもありますけれども。
ともあれ、ジュディー=ジーン・ウェブスターは、"some mourning" を "handsome mourning" とおちゃめに変更することによって、「喪」の抽象的・精神的意味から、喪服の立派さ・派手さという具象的な意味に変化させてしまったらしいことはいちおう納得した次第です。
(ついでながら、「"dined with" 誰々」、というより、"dined with my Lady" という文はピープスの日記に頻出する記述であり、特に盛大な晩餐とかいう含みはまったくないでしょう。それでも、『あしながおじさん』のコンテクストを忖度して、少し色をつける必要を感じたので、日記の内容にしたがって、「外食」という言葉にしましたけれど。だから、日記原文は、ルースに書き記した情報なのであって、少なくともピープス自身に「食事」と「喪」をなんらかの意味をもって結びつける意図はまったくなかったと思われます。)
そして、そのことは、外見(衣装)は嘆いていても、内面はそうでもなく、だから、がっつり飯を食う、という外と内の違和、それと冒頭に書いたような、昔の死生観の現代との違和、みたいなことが頭の中にあったのかもしれません。もっとも、前者については、そう考えると、トマス・ハリソンについては、もう一回ねじれて、鷹揚とした態度の裏側に別のものが隠されているということになって、ぐるぐるぐるぐる頭が回ってしまいそうですけれどw。いや、そうではなくて、やはり死を cheerful に捉えるという一点ですかね。
以下ただのメモ・・・・・・
アメリカの女性作家Mary Wilkins Freeman (1852-1930) の By the Light of the Soul 第27章――
Ida had obtained a very handsome mourning wardrobe for both herself and Evelyn, and had superintended Maria's. Maria paid for her clothes out of her small earnings, however. Ida had her dress-maker's bill made out separately, and gave it to her. Maria calculated that she would have just about enough to pay her fare back to Amity without touching that sacred blood-money in the
savings-bank. <http://www.bookpages.org.ua/book/2953521/By-the-Light-of-the-Soul-A-Novel/num_417.html>
この不定冠詞の a の付加は、mourning を形容詞として wardrobe という可算名詞が用いられたことにより出現したものと思われます(つまり名詞の mourning はuncountable――喪服でも、なの?)。
2009年12月28日付記
my Lady をとりちがえていたことに気づきました。人妻でした。恥ずかしいです。
//////////////////////////////
Elizabeth Gaskell, Ruth E-text at Guteberg <http://ia301536.us.archive.org/0/items/ruth04275gut/gruth11.txt>
Charlotte Mary Yonge, The Two Sides of the Shield E-text at Gutenberg <http://www.gutenberg.org/dirs/etext04/twsss10h.htm>
"The Author of 'A Private History of the Court of England, &c.", Romance Readers and Romance Writers: A Satirical Novel (London, 1810) E-text <http://www.chawton.org/library/novels/files/Romance2.html>
"19th Century Mourning Clothing" <http://19thcenturyartofmourning.com/19th_century_mourning_clothing.htm> 〔19th Century Art of Mourning <http://19thcenturyartofmourning.com/index.htm>〕

Giotto, The Mourning of Christ (c.1305) image via Web Museum, Paris <http://www.dl.ket.org/webmuseum/wm/paint/auth/giotto/mourning-christ/index.htm>
人をもてなす――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(6) Entertaining: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (6) [Daddy-Long-Legs]
まっこと遅々とした歩みです。
実のところ、『あしながおじさん』の続く一文 ("Seems a little early to commence entertaining, doesn't it?") も意味が定かではなく、わざと以前の引用に含めておらなんだのでした。
しかし、さきほど(昨日)の記事「ジェマイマとサミュエル姉弟 Jemima Montagu and Samuel Crewe」で書いたように自分のすごい勘違いがわかったので、わかったような気になっています。実は下の翻訳の抜き書きはわかるまえに書きとめていたので、わかったあとからだとなかば徒労だとわかりましたし、取ろうかとも思ったのですけれど、なにかの参考にとそのままにしておきます。
[. . .] "Dined with my lady who is in handsome mourning
for her brother who died yesterday of spotted fever."
Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? [Penguin Classics 117]
いちばんきっぱりとした訳は松本恵子(新潮文庫)かもしれません――
「余は奥方様のご招待にあずかり、晩餐を共にいたしたが、奥方様は弟君が昨日脳脊髄炎にて逝去されたので、いとも美々しき喪服を召しておいであった」
弟が昨日死んだ今日お客をするなんて、少し早すぎるんじゃございませんかしら? (183)
遠藤寿子(岩波文庫)の訳――
「奥方のお召しにてごちそうになりぬ。奥方は、きのう脳脊髄膜炎にてみまかられし弟君のために、美しき喪服を召したまえり。」
喪中なのにお客様を招ぶなんて、少し早過ぎますわね。 (244-5)
谷口由美子(岩波少年文庫)の訳――
「奥方のお召しで、晩餐を共にせり。弟君が昨日、髄膜炎で亡くなられたため、美しい喪服を召したまえり。」
人を呼んで食事だなんて、少し早すぎませんか? (249-50)
厨川圭子(角川文庫)の訳――
「拙者が晩餐の相伴にあずかりたる姫君は、昨日、脳脊髄膜炎にてみまかりし兄君のために、いとも美わしき喪服を召しておられた」
それじゃ、まだ楽しむには早すぎるじゃありませんか、ねえ? (185)
坪井郁美(福音館古典童話シリーズ)訳――
「美しき喪服に身をつつみしわが奥方とともに晩餐を囲みたり。喪は昨日はっしんチフスで死亡せし奥方の弟君のためなり。」
宴をはるにはちょっとばかり早すぎるんじゃないかしら? (217)
曾野綾子(講談社青い鳥文庫)訳・白木茂(正進社名作文庫)訳――割愛部分。
早川麻百合(金の星社世界の名作ライブラリー)訳――
「奥方さまよりご招待にあずかり、晩さんをともにす。奥方、いと美しき喪服をめしたまいぬ。聞けば、弟君が昨日、脳脊髄膜炎にてみまかられた由。」
弟さんが亡くなった翌日に晩さんをもよおすなんて、ちょっと早すぎると思いません? (278)
岡上鈴江(春陽堂くれよん文庫)訳――
「余は、貴婦人のご招待にあずかり、晩餐を共にせしが、婦人は弟君を昨日、脳脊髄炎にて失いしため、美しき喪服姿でいられた」
それじゃ人をもてなすにはまだ早すぎるじゃありませんか。ねえ? (243)
野上彰(ポプラ社世界の名著)訳――
「奥方と食事をともにせり。きのう、弟ぎみの点状熱(脳せきずいまく炎)にてみまかりたまいしとて、うるわしき喪服を召されたり。」
昨日弟が死んだのなら、お客を呼んで楽しむのは、少し早すぎるんじゃないでしょうか? (176)
osawaさん――
「喪中にて見目麗しく装ひたる奥方と夕餉を共にす。奥《あれ》の兄が昨日、斑点熱で死におほせたればなり。」
余興を始むるには、いさゝか早うござらうか?
あとは本が見当たらないのですけれど、まあ、だいたいの感じはわかると思います。もう一度原文を見ていただきたいのですが、"Dined with my lady who is in handsome mourning
for her brother who died yesterday of spotted fever." ¶Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? です。
要するに、原文はとりあえずは謎めいている、といってもよい。のではなかろうか。だって、ただ (1) [I] Dined with my lady ――(私は)奥様と夕食をとったということ、 (2) who is in handsome mourning――奥様は(立派な)喪服を着ていた〔あるいはどっぷり喪に服していた〕こと〔この部分、ピープスの日記原文は "some" であったことについては「Handsome Mourning と Some Mourning――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(5) (Hand)Some Mourning: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (5)」を参照〕、(3) for her brother who died yesterday of spotted fever――それは昨日死んだ兄弟のためだということ、が書かれているだけで、それに対して、(4) Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? ――"entertain"しはじめるには早すぎるように思えませんか、というコメントが付されているのです。
正直を申さば、自分は坪井さんやosawa さんの線で考えておったのでござりました。
(一般に)翻訳はそれなりに意味がとおるように仕立てられねばならないものですから(いちおう)、(この場合)それぞれの訳者は想像をたくましくして(あるいはやはりついピープスの原典にあたって)、それぞれのパフォーマンスを展開することになります。小説のジャンル上、読者をentertain せねばならぬ、ということもあります。
英語に「ご招待」とか「お召し」みたいな、奥様のほうで招いたことをにおわせる言葉はありません。それは "entertain" を「人を招いてもてなす」というような意味にとって、対応を考えての説明的で補足的な訳語でしょう。
さらに、(しつこいですが)ジュディー=ジーンは "my Lady who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of spotted fever" を "my lady who is in handsome mourning for her brother who died yesterday of spotted fever" と変えてます。(しつこいですが)これって、「喪服を着ていた」という叙述だったら、やっぱり過去時制になるんじゃないでしょうか――who was (dressed) in handsome mourning みたいに。"who is in some mourning" というのは、「喪に服している」「服喪中」という意味でしょうし、それはもしかすると "handsome" なっても変わらないかもしれず。いや、それはジュディー=ジーンもわかっていたかもしれず。論理的には、近親者が亡くなったばかりで服喪中→人と一緒に晩餐をするのは早い、というのがまんなかにあって、そのときの服装の様子はおまけみたいなものでしょうから(もちろん服喪者の態度を表現することにはなりますけれど・・・・・・対比による強調みたいな)。handsome とすることで(日本語の翻訳者たちでいうと)「見目麗しく」とか「美しき喪服」とか取られることを予測しての改変だったらアイロニーですかね、作家がねらった効果は。
結局、この場合に問題なのは、ジーン・ウェブスターが引いているピープスの日記の一節が、『あしながおじさん』において獲得するコンテクストと、一節がピープスの日記の中でもっているコンテクストと、の齟齬みたいなものです。
クリスマスでなんとなくミュージカルの "Stranger in Paradise" の記事を書いたので、その類推でいえば、ミュージカルの中に置かれた "Stranger in Paradise" の歌詞の意味と、そこから切り離されて、礼服を着た日本人に歌われたり、さらにrefrain部だけ切り離されて女性ひとりによって歌われたりすることで歌詞がもってしまうイメジと、『あしながおじさん』におけるこのような引用の効果は似たところがあるのでしょうか。
似たところはあるかもしれないけれど、引用という一点において異なるような気もします。
***********
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
JULY 1661
3rd. To Westminster to Mr. Edward Montagu about business of my Lord's, and so to the Wardrobe, and there dined with my Lady, who is in some mourning for her brother, Mr. Saml. Crew, who died yesterday of the spotted fever. So home through Duck Lane' to inquire for some Spanish books, but found none that pleased me. So to the office, and that being done to Sir W. Batten's with the Comptroller, where we sat late talking and disputing with Mr. Mills the parson of our parish. This day my Lady Batten and my wife were at the burial of a daughter of Sir John Lawson's, and had rings for themselves and their husbands. Home and to bed. <http://www.gutenberg.org/files/4131/4131-h/4131-h.htm>
前の記事で書いた、引用の背景のコンテクストを入れておきます。1861年7月3日にピープスが一緒に御飯をいただくmy Lady は、もともとピープスの雇い主であり、縁戚でもあるエドワード・モンタギューの奥さんのジェマイマで、ピープスの8つほど年上の女性ですが(1861年に夫人は36歳くらい、ピープスは28歳)、幼なじみであり、家族同然の交際をしている間柄です。よくモンタギュー邸でご飯を食べる記述がしょっちゅう日記にでてきます(印象的なのは、だんなのモンタギューがいなかったけれど夫人とごはんを食べることにして、食べ終わったらだんなが帰ってきて、でもそのときには召使いたちも食事を全部たいらげていて食べるものが何も残っておらず、だんなが怒った、みたいな記述ですw)。そして、この日も、ご招待があって出向いていったわけではない。なんか外で、しかもモンタギュー邸で食いすぎじゃねーの、という心配はありますが。
あと、あれこれ読んでいてわかったのですが、dinner はもっぱら昼食のようですし、dined も日記の記述からして(ぜんぶがぜんぶとは言えないですけれど)お昼のようです。この一節でも、そのあとDuck Lane にスペイン語の本を探しに行ったり、さらに職場に戻ったりしていますし。(いっぽう、自身の奥さんはジョン・ローソン氏の娘さんの葬儀に参列していたようで)。
それを、ジュディー=ジーン・ウェブスターは、"Mr. Saml. Crew" という固有名を抜かし、言葉を詰めたり足したりして、そして、もちろん日記のコンテクストを提示せずに、引用して、「entertain しだすには早すぎる」とのコメントを付与するわけです。
やっぱり周到な改変ですね、handsome は。おちゃめだけど。
*******************************
大掃除をしていたら、東健而の訳(世界大衆文学全集『世界滑稽名作集』)が見つかりました。健ちゃんは "handsome mourning" をモーリちゃんの父と同じようにとっていました♪――
「わしはハリソン少佐殿が首を縊(くく)られ、臓腑(はらわた)を引き出され、手足を八つ裂きにされるのを見に参りましたが、そのやうな目に遭うても、あの人はまあケロリンかん[ケロリンかんに傍点]として居りましたわいなあ」
それから斯んなことを言ふのよ。
「奥様よりのお招きにて、御馳走様になりましたが昨日弟子様が脳脊髄膜炎で御亡くなりなされたとやら、奥様には御いたはしくも喪に服して居られました」
昨日弟さんが死んだのにもう宴会をするなんてまあ随分早いわねえ? (197)
遠藤寿子から「喪服」になったのですね。(まちがっているとは言っていません)。
/////////////////////////////////////////////
1660年の日記 <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>
1661年の日記 <http://www.gutenberg.org/files/4131/4131-h/4131-h.htm>
"Elizabeth Pepys (wife, b. St Michel)" in The Diary of Samuel Pepys: Dairy entries from the 17th century London diary <http://www.pepysdiary.com/p/150.php>
女の子のように洋服にエキサイトする――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(7) Excited about His Clothes As Any Girl: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (7) [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』4年生2月15日の手紙のつづきです。
Seems a little early to commence entertaining, doesn't it? A friend of Pepys devised a very cunning manner whereby the king might pay his debts out of the sale to poor people of old decayed provisions. What do you, a reformer, think of that? I don't believe we're so bad today as the newspapers make out.
Samuel was as excited about his clothes as any girl; he spent five times as much on dress as his wife--that appears to have been the Golden Age of husbands. Isn't this a touching entry? You see he really was honest. "Today came home my fine Camlett cloak with gold buttons, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it."
Excuse me for being so full of Pepys; I'm writing a special topic on him. 〔下のピープスの日記原文と参照のため太字強調付加〕
(人のおもてなしを始めるには少し早すぎるように思えませんか? ピープスの友人にたいへん狡猾な手段を考案した人がいて、国王の負債を支払えるように古くなって痛んだ食料を貧しい人々に売りつけたのです。社会改良家として、これをどう思いますか? 新聞が喧伝するほど今日の私たちは悪くないとわたしは思うのですけれど。
サミュエルは、自分の服装について、女の子みたいに胸躍らせました。妻の五倍も自分の服にお金をかけました――夫たちの黄金時代だったみたいです。日記の次の箇所は感動的じゃないでしょうか? 彼がまじ正直だったのがわかります。「今日、金ボタン付きの私の見事なキャムレットのマントが宅に届けられる。高額であった。神様、自分が代金を支払えますようお祈りします。」
ピープスだらけで失礼します。ピープスについて特殊研究レポートを書いているのです。)
"Seems a little early to commence entertaining, doesn't it?" になぜか改行せずに続いている、貧民に痛んだものを政府が売りつける話については調べがついていません。宿題です。ただ、ここで、ピープスを出してきた理由の少なくともひとつが示されています。貧しい人々と社会改良の問題です。ことにおじさんを "reformer" とわざわざ呼ぶことによって、前の月の貧しい人に小切手100ドルを送って救った話とつながってきます。
段落があらたまって、服に金をかける話について。ジュディーはモノであふれた物質文明への疑問をときどきは口にしますけれど、女の子としていろいろなものに惹かれているのも確かで、この一節に金持ち(前の段落の貧者と対照的に)への批判みたいなものがあるようには感じられません。むしろ皮肉があるとすれば、現代は妻の衣装に金がかかって、夫は自分の服に金はかけられない、という諷刺でしょう。ジーン・ウェブスター自身は、活動家がしばしば禁欲的な生活をするのに対して、ファッションや食事を大事にした人として知られているようです(これは確かエレイン・ショーウォーターもペンギン版の序文で書いていた)。
この日記のエントリーは1860年7月1日です。昼食を "dine" したり、あちゃこちゃ行く(とくに my Lord のところに何度も行く)記録もあるので、この日の全文を引用します。――
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
JULY
1660
July 1st. This morning came home my fine Camlett cloak, with gold buttons, and a silk suit, which cost me much money, and I pray God to make me able to pay for it. I went to the cook's and got a good joint of meat, and my wife and I dined at home alone. In the afternoon to the Abbey, where a good sermon by a stranger, but no Common Prayer yet. After sermon called in at Mrs. Crisp's, where I saw Mynheer Roder, that is to marry Sam Hartlib's sister, a great fortune for her to light on, she being worth nothing in the world. Here I also saw Mrs. Greenlife, who is come again to live in Axe Yard with her new husband Mr. Adams. Then to my Lord's, where I staid a while. So to see for Mr. Creed to speak about getting a copy of Barlow's patent. To my Lord's, where late at night comes Mr. Morland, whom I left prating with my Lord, and so home.
いちおう書きとめておきますと、(1) This morning を Today に変え、(2) cloak だけではなくて絹のスーツもあったの ("and a silk suit") を削除し、(3) その勢いで "cloak, with" のところのコンマを削除しています。
『日記』の注釈は、camlett がウールとシルクを織りあわせた高級な生地でたいへん高価であることと、のちの1664年6月1日の日記にあるように、スーツに24ポンド支払った、と書かれています("[Camlet was a mixed stuff of wool and silk. It was very expensive, and later Pepys gave L24 for a suit. (See June 1st, 1664.)] <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>)。が、その日の日記を見てもそういう記述はないので、不詳です。
camlett は 英和辞典には "camlet" の綴りででています。語源的にはラクダのcamel と関係する(実際に中世のアジアでつくられた、ラクダ(やアンゴラヤギ)の毛からつくられた織物として知られていた)けれど、この東洋の織物を西洋風にアレンジ(模倣)してスベスベにした平織りの服地みたいです。しかし、イギリスにおいてもいろいろと時代によって変化した可能性もあります。
Naergi's Costuming Site は "Rococo women's clothing at the V&A (Victoria and Albert Museum, London)" のページ <http://www.naergilien.info/research/london1/VandA/Rococo/womens/index.htm> の中に1860年代の女性の乗馬服としてキャムレットを使った服の画像を挙げて、"Camlet (silk and camel hair)" と記述しています。これがヴィクトリア・アルバート博物館の記述なら、ほんとにラクダの毛が織られていたのかもしれません。
Daddy-Long-Legs, Century 初版 (1912) <http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/266/mode/2up/search/camlett>
////////////////////////////////
E-text Works by Samuel Pepys at Project Gutenberg <http://www.gutenberg.org/browse/authors/p#a1181>
部屋の照明と就寝時間 Room Lamps and Lights Out [Daddy-Long-Legs]
えーと、書けばいいというものではないというのはわかっているのですが、つい細かく刻みだしたら、なんかテキストを容易に飛ばせない自分がいたりします(飛ぶのが怖い)。
4年生2月15日の手紙。サミュエル・ピープスについてさんざん書いたあと、大学の話題(まあ、ピープスも英国史の授業とレポートにからんでいるということではありましたが)に戻ります。
What do you think, Daddy? The Self-Government Association has abolished the ten-o'clock rule. We can keep our lights all nights if we choose, the only requirement being that we do not disturb others―we are not supposed to entetain on a large scale. The result is a beautiful commentary on human nature. Now that we may stay up as long as we choose, we no longer choose. Our heads begin to nod at nine o'clock, and by nine-thirty the pen drops from our nerveless grasp. It's nine-thirty now. Good night. (Century 267-268; Penguin Classics 117-118).
(どう思いますか、ダディー。自治会が10時ルールを撤廃しました。我々は我々が望むなら一晩中でも灯りをつけておけます。唯一の必要条件は他の人たちに迷惑をかけないことです――大規模に人をもてなすことは想定されていないわけです。その結果は、人間性についての美しい注釈となっています。自ら選ぶだけ夜更かししてよくなった今、わたしたちはもはやそれを選びません。9時になるとこっくりしはじめ、9時半には握力を失なった手からペンが落ちます。9時半です、いま。おやすみなさい。)
消灯時間については、1年生になりたての、ほんとに最初の手紙で書かれていました。――
The ten o'clock bell is going to ring in two minutes. Our day is divided into sections by bells. We eat and sleep and study by bells. It's very enlivening; I feel like a fire horse all of the time. There it goes! Lights out. Good night.
Observe with what precision I obey rules―due to my training in the John Grier Home. (Penguin Classics 14)
(10時のベルがあと2分で鳴ろうとしています。わたしたちの一日はベルでセクション分割されています。わたしたちはベルに従って眠り、勉強するのです。とても活気付けられます。いつも消防馬みたいな気持ちです。さあ、鳴ってる! 消灯~。おやすみなさい。
いかに精確にわたしがルールに従うか、おわかりでしょう――ジョン・グリアー・ホームでの訓練のおかげです。)
最初の日の記事については9月に「女子寮の話から火馬、火の車馬、火事馬、消防馬、消防馬車馬へ Fire Horses」であれこれ書きました。モデルになっているヴァッサー女子大学の時間に厳しい規則とか。
その後にわかったことも含めて、ちょっとだけ書いておきます。
1年生12月19日の2信というか、夜9時45分づけのほうの手紙で、他の女子に追いつくために、寝る前に本をいろいろと読んでいることが書かれている、そこで自室での読書の様子が描かれています。――
[. . .] Now, I know all of these things and a lot of others besides, but you can see how much I need to catch up. And oh, but it's fun! I look forward all day to evening, and then I put an "engaged" on the door and get into my nice red bath robe and furry slippers and pile all the cushions behind me on the couch, and light the brass student lamp at my elbow, and read and read and read. One book isn't enough. I have four going at once. [. . .]
(Ten o'clock bell. This is a very interrupted letter.) (Penguin Classics 24)
(今、こういうことはみんな知っているし、その他にもたくさんのことを知ってますけれど、それでも、追いつくのにどれだけたくさん自分には必要かおわかりと思います。それにしても、ああ、楽しい! 夕方になるのが朝から一日待ち遠しいです。そしたらドアに「勉強中」を掲げ、素敵な赤のバスローブを着てふかふかのスリッパを履いて、クッションをありったけ背中に積みかさねて長椅子に寝転がると、ひじのところに真鍮の学生用ランプ (student lamp) を灯し、そして読んで読んで読みまくる。1冊じゃ足りないわ。4冊いっぺんに読むんです。
(10時のベルです。とても中断の多い手紙になっています。))
ここで出てくる student lamp は、ヴァッサー女子大の、19世紀末のジーン・ウェブスターが通った頃ですと、まちがいなくガスランプでした。
ヴァッサー・エンサイクロペディアの "electricity" のページには、1905年ごろのガスランプを囲んで勉強する女子学生たちの写真が掲載されています。どういう空間なのかはわかりませんが。昼間かもしれません。――

"Studying around a Welsbach gas burner in Main building, circa 1905," image via Vassar Encyclopedia <http://vcencyclopedia.vassar.edu/buildings-grounds/technology/electricity.html>
Welsbach ウェルズバハというのは発明者であるオーストリアの化学者 Freiherr von Welsbach (1858-1929) の名をとったバーナー(あるいはマントル)の商標名です。酸化トリウムと酸化セリウムの混合物を付着させたマントルを過熱して白熱光を得られるようにしたのだそうです。
このページを読むと、1870年代くらいまでは、学生の部屋には2フィートのガス燈が入っていて、勉強は8フィートの明るいガス燈のあるパーラーで行なうことが期待されていたのですけれど、実際は学生の多くは個室での勉強を好み、自室のガスの出をよくしようとバーナーをいじったり、場合によってはパンチをくれたりして、問題となったために4フィートに量を上げた。けれどもなお光量は不足して、視力低下や二酸化炭素中毒など健康の問題や火災の危険など懸念された。1873年には新聞が大学の管理を批判する記事を書きます。
で、記事はその後の19世紀末のことがなにも書かれてなくて、つぎの段落では1911年にとんでいます。1911年から12年にかけてオール電化(というよりガスに加えて電力の導入)が行なわれた、という話です。――
Once Vassar's plan was approved, Lord & Co. began installation early in 1911. By the commencement of the 1911 fall semester, electrical lighting and heating had been effectively installed in Main building. The rest of the campus, including residence halls, academic buildings, and the library followed soon after, as electrical outfitting quickly reached completion by the early months of 1912. Once electrical lighting had become fully installed in the hallways of Main, students were provided with a gooseneck lamp in addition to the gas lamp, allowing them to arrange the light in almost any position. The gooseneck lamp also allowed for a sleepy roommate to rest as working students could direct the light to the corner of the room, effectively illuminating one side of the room and leaving the other in relative darkness. Instead of having to cope with the overhead flickering of the gas lamp, students began to prize the convenience and utility of electric light in their dormitory rooms [. . .].
この電気導入は、先月「ガス・プラント Gas Plant」で書きました。建学当初からキャンパス内に設計されて、アメリカ初の大規模セントラル・ヒーティング施設として建物に暖房と照明用の熱とガスを供給していたガス・プラントでしたが、逆にそれゆえにアメリカの他大学等に遅れたかというとそうでもなくてだいたい同時期のようですけれど、さらに自家発電というかたちで電気をキャンパスに入れたのでした。
上の引用には、1911年の秋学期が始まるまでには(commencement はここでは「卒業式」の意味ではなくて「開始」の意味だと思われます。confusing です)メイン・ビルディングには電気が入り、ついで学生寮や図書館など1912年の春には電化が完成したと書かれています。そこで学生たちはこれまでのガスランプに加えて "gooseneck lamp" (日本でアームライトとかフレーキスタンドとか言われるもの) を与えられ、ルームメートの迷惑にならないように角度を変えることもできるし、暗いガス燈をいじる必要もなくなって、明るい電気照明を享受したのでした。
こうして、実質的に初代学長(1864-78) だったジョン・レイモンドが、学生がバーナーのガス量を増やそうといじったりなぐったりして細工するさまを “licht, mehr licht” (光を、もっと光を)と(ゲーテの臨終のことばとされているものでしたっけ)揶揄した時代から40数年を経てようやくもっと光が与えられたのでした。
エーと。何の話でしたっけ。就寝・消灯時間の規則については調べておりません。1912年というのは『あしながおじさん』が出版された年です。この作品は単行本になるまえに雑誌に連載されていたのですけれど、母校の電化の話はジーン・ウェブスターにも伝わっておったのではないかと思われます。で、あれこれ懐かしんでるのかなあ、というふうにも思われます。

"A student in her newly electrified room in Main Building, circa 1912" image via Vassar Encyclopedia
新たに電化された自分の部屋で本を読む学生、1912年ごろ。
貧しい、干からびた説教(またピープス)―――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(8) Poor, Dry Sermon (Pepys Again): Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (8) [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』4年生2月15日付けの手紙に付された「日曜日」の手紙(の前段)。日曜の礼拝から戻ってきたジュディーは、牧師の説教についてコメントします。――
Just back from church―preacher from Georgia. We must take care, he says, not to develop our intellects at the expense of our emotional natures―but methought it was a poor, dry sermon (Pepys again). It does n't matter what part of the United States or Canada they come from, or what denominaton they are, we always get the same sermon. Why on earth don't they go to men's colleges and urge the students not to allow their manly natures to be crushed out by too much mental application?
(いまさっき礼拝から戻ったところです――ジョージアから来た牧師さんの説教でした。わたしたちは情緒的本性を犠牲にして知性を発達させることのないように注意しなければならない、というのです――さりながら、我思うに、貧しい、干からびた説教であった(またピープス)。合衆国でもカナダでもどこの地域から来ようが、あるいは宗派がなんだろうが関係なく、わたしたちは同じ説教を聞かされます。いったい、どうしてあのかたたちは、男子大学に行って、過度の知的傾注によって男性性をしぼりとられないようにしなさいと説得しないのでしょうか?)
ここで "church" は「教会」の意味ではなくて「礼拝」 (service) の意味でしょう。大学内のチャペルで日曜日の説教が行なわれるのだと考えられます。(自信60パーセント)
ピープスはLord's day (日曜日)には毎週説教を聞いて、 "good sermon" とか "excellent sermon" とか "eloquent sermon" とか "flattering sermon" とか "gallant sermon" とか "honest sermon" とか "indifferent sermon" とか "impertinent sermon" とか "cold sermon" とか "dull sermon" とか、あるいはさらに形容詞を増やして、 "lazy poor sermon" (1659年1月22日)とか、"good honest sermon" (1660年2月5日)とか、"tedious long sermon" (1660年8月26日)とか "poor dull sermon" (1661年1月27日)とか "boyish young sermon" (1661年12月21日)とか書いたりもします。ただ説教を聞いたとだけ書き記している場合も多いのですけれど。(変わったヴァリエーションとして、"a good honest and painfulll sermon" (1661年3月17日)。"a lazy sermon, like a Presbyterian" (1661年4月14日, Easter)。"a sad sermon, full of nonsense and false Latin" (1662年4月27日)。いちばん形容詞が多いのは1661年2月17日の "A most tedious, unreasonable, and impertinent sermon, by an Irish Doctor" かも)。
DIARY OF SAMUEL PEPYS. October 16607th (Lord's day). To White Hall on foot, calling at my father's to change my long black cloak for a short one (long cloaks being now quite out); but he being gone to church, I could not get one, and therefore I proceeded on and came to my Lord before he went to chapel and so went with him, where I heard Dr. Spurstow preach before the King a poor dry sermon; but a very good anthem of Captn. Cooke's afterwards. Going out of chapel I met with Jack Cole, my old friend (whom I had not seen a great while before), and have promised to renew acquaintance in London together. To my Lord's and dined with him; he all dinner time talking French to me, and telling me the story how the Duke of York hath got my Lord Chancellor's daughter with child, and that she, do lay it to him, and that for certain he did promise her marriage, and had signed it with his blood, but that he by stealth had got the paper out of her cabinet. And that the King would have him to marry her, but that he will not. So that the thing is very bad for the Duke, and them all; but my Lord do make light of it, as a thing that he believes is not a new thing for the Duke to do abroad. Discoursing concerning what if the Duke should marry her, my Lord told me that among his father's many old sayings that he had wrote in a book of his, this is one--that he that do get a wench with child and marry her afterwards is as if a man should----in his hat and then clap it on his head. I perceive my Lord is grown a man very indifferent in all matters of religion, and so makes nothing of these things. After dinner to the Abbey, where I heard them read the church-service, but very ridiculously, that indeed I do not in myself like it at all. A poor cold sermon of Dr. Lamb's, one of the prebends, in his habit, came afterwards, and so all ended, and by my troth a pitiful sorry devotion that these men pay. So walked home by land, and before supper I read part of the Marian persecution in Mr. Fuller. So to supper, prayers, and to bed.
スパーストウ博士が国王の前で "poor dry sermon" をしたけれど、そのあとのキャプテン・クック(誰やねん)の讃美歌はたいへんよかった、と書かれています。チャペルをあとにして my Lord (エドワード・モンタギュー)と一緒に昼を食べて (dined)、昼食のあいだずっと (all dinner) モンタギューがフランス語をしゃべっていたとも。そしてモンタギューは宗教的な問題に関心を失なっていることが記されていますけれど、ピープスは午後にまた教会 (Abbey=Westminster Abbey)に行って聞いたラム博士の "poor cold sermon" が言及されます。dry も cold もダメですが、 "hot sermon" というのはホメことばのようです(いつの日記か忘れました)。
poor と dry のあいだのコンマの挿入はジュディー=ジーンによる編集と思われます。うーん。あんまり深い意味はないような。なんで入れたのでしょう。形容詞のたたみかさねは、論理と集合を書き手がどう考えるかによるのでしょうけれど(インフォーマルな文章でコンマが落ちがちなのは事実です)。Methought とか擬古的な感じが強いので、さらっと読まれないようにちょっと重々しさを出したかったのかしら。
あ、いま検索をe-text でかけていたら、別の日記エントリーがヒットしました――
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
May 166112th. My wife had a very troublesome night this night and in great pain, but about the morning her swelling broke, and she was in great ease presently as she useth to be. So I put in a vent (which Dr. Williams sent me yesterday) into the hole to keep it open till all the matter be come out, and so I question not that she will soon be well again. I staid at home all this morning, being the Lord's day, making up my private accounts and setting papers in order. At noon went with my Lady Montagu at the Wardrobe, but I found it so late that I came back again, and so dined with my wife in her chamber. After dinner I went awhile to my chamber to set my papers right. Then I walked forth towards Westminster and at the Savoy heard Dr. Fuller preach upon David's words, "I will wait with patience all the days of my appointed time until my change comes; " but methought it was a poor dry sermon. And I am afeard my former high esteem of his preaching was more out of opinion than judgment. From thence homewards, but met with Mr. Creed, with whom I went and walked in Grayes-Inn-walks, and from thence to Islington, and there eat and drank at the house my father and we were wont of old to go to; and after that walked homeward, and parted in Smithfield: and so I home, much wondering to see how things are altered with Mr. Creed, who, twelve months ago, might have been got to hang himself almost as soon as go to a drinking-house on a Sunday
こちらが引用元ですね、明らかに。でもコンマはないっす。それはそれとしてダヴィデの言葉(ちょっと自分は無知ですぐに調べがつきません)として "I will wait with patience all the days of my appointed time until my change comes;" とあって、セミコロンが引用符の内側にあってつぎのbut 節につながっているのは、なんかイレギュラーが感じがします。英国式の句読法なのかしら。
////////////////////////
付記
1) この手紙でほのめかされている女子(高等)教育への偏見については別の記事を書きます。
⇒ 2010年1月11日追記――「女性の高等教育への偏見――貧しい、干からびた説教 (2) Prejudice toward Women's Higher Education: Poor, Dry Sermon (2)」を書きました。
2) アメリカの大学での宗教(教育)問題についてはもしかすると別の記事を書けるかもしれません。
最も誠実にして忠順、徳義に篤く素直なしもべたるJ・アボット――『あしながおじさん』のなかのサミュエル・ピープス(9) Your Most Loyall, Dutifull, Faithfull Servant, J. Abbott: Samuel Pepys in Daddy-Long-Legs (9) [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』4年生2月の日曜日の手紙の後半です。
It's a beautiful day―frozen and icy and clear. As soon as dinner is over, Sallie and Julia and Marty Keene and Elenor Pratt (friends of mine, but you don't know them) and I are going to put on short skirts and walk 'cross country to Crystal Spring Farm and have a fried chicken and waffle supper, and then have Mr. Crystal Spring drive us home in his buckboard. We are supposed to be inside the campus at seven, but we are going to stretch a point to-night and make it Eight.
Farewell, kind Sir.
I have the honour of subscribing myself,
Your most loyall, dutifull, faithfull
and obedient servant,
J. ABBOTT.
(すばらしい日です――霜と氷と澄んだ空気。昼食が終わりしだい、サリーとジュリアそしてマーティー・キーンとエリナー・プラット(ふたりともわたしの友だちですけど知りませんよね)とわたしは、ショート・スカートをはいて、田舎道を「クロスカントリー」でクリスタル・スプリング農場まで歩いてって、そこでフライドチキンとワッフルを夕食にいただくつもりです。帰りはクリスタル・スプリング氏に荷馬車で送ってもらいます。7時にはキャンパスに戻ってないといけないのですが、今宵はちょっと延長して、8時にします。寛大なるサァ、これにて失礼つかまつります、
御許に我が身を仕えまいる栄誉に浴しつつ、
最も誠実にして忠順、徳義に篤く素直なしもべたる、
J・アボット)
DIARY OF SAMUEL PEPYS.
MAY 1660
4th. I wrote this morning many letters, and to all the copies of the vote of the council of war I put my name, that if it should come in print my name maybe at it. I sent a copy of the vote to Doling, inclosed in this letter:
"SIR,
"He that can fancy a fleet (like ours) in her pride, with pendants
loose, guns roaring, caps flying, and the loud 'Vive le Roys,'
echoed from one ship's company to another, he, and he only, can
apprehend the joy this inclosed vote was received with, or the
blessing he thought himself possessed of that bore it, and is"Your humble servant."
About nine o'clock I got all my letters done, and sent them by the messenger that came yesterday. This morning came Captain Isham on board with a gentleman going to the King, by whom very cunningly, my Lord tells me, he intends to send an account of this day's and yesterday's actions here, notwithstanding he had writ to the Parliament to have leave of them to send the King the answer of the fleet. Since my writing of the last paragraph, my Lord called me to him to read his letter to the King, to see whether I could find any slips in it or no. And as much of the letter as I can remember, is thus:
"May it please your Most Excellent Majesty," and so begins.
"That he yesterday received from General Monk his Majesty's letter and direction; and that General Monk had desired him to write to the Parliament to have leave to send the vote of the seamen before he did send it to him, which he had done by writing to both Speakers; but for his private satisfaction he had sent it thus privately (and so the copy of the proceedings yesterday was sent him), and that this come by a gentleman that came this day on board, intending to wait upon his Majesty, that he is my Lord's countryman, and one whose friends have suffered much on his Majesty's behalf. That my Lords Pembroke and Salisbury are put out of the House of Lords. That my Lord is very joyful that other countries do pay him the civility and respect due to him; and that he do much rejoice to see that the King do resolve to receive none of their assistance (or some such words), from them, he having strength enough in the love and loyalty of his own subjects to support him. That his Majesty had chosen the best place, Scheveling, for his embarking, and that there is nothing in the world of which he is more ambitious, than to have the honour of attending his Majesty, which he hoped would be speedy. That he had commanded the vessel to attend at Helversluce till this gentleman returns, that so if his Majesty do not think it fit to command the fleet himself, yet that he may be there to receive his commands and bring them to his Lordship. He ends his letter, that he is confounded with the thoughts of the high expressions of love to him in the King's letter, and concludes,"Your most loyall, dutifull, faithfull and obedient subject and servant, E. M."
The rest of the afternoon at ninepins. In the evening came a packet from London, among the rest a letter from my wife, which tells me that she has not been well, which did exceedingly trouble me, but my Lord sending Mr. Cook at night, I wrote to her and sent a piece of gold enclosed to her, and wrote also to Mrs. Bowyer, and enclosed a half piece to her for a token. After supper at the table in the coach, my Lord talking concerning the uncertainty of the places of the Exchequer to them that had them now; he did at last think of an office which do belong to him in case the King do restore every man to his places that ever had been patent, which is to be one of the clerks of the signet, which will be a fine employment for one of his sons. After all this discourse we broke up and to bed. In the afternoon came a minister on board, one Mr. Sharpe, who is going to the King; who tells me that Commissioners are chosen both of Lords and Commons to go to the King; and that Dr. Clarges is going to him from the Army, and that he will be here to-morrow. My letters at night tell me, that the House did deliver their letter to Sir John Greenville, in answer to the King's sending, and that they give him L500 for his pains, to buy him a jewel, and that besides the L50,000 ordered to be borrowed of the City for the present use of the King, the twelve companies of the City do give every one of them to his Majesty, as a present, L1000. <ftp://ftp.archive.org/pub/etext/4/2/0/4200/4200.txt >
| Su | Mo | Tu | W | Th | Fr | Sa |
| __ | __ | __ | __ | __ | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | __ | __ |
1912年 February
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
//////////////////////////////////////
E-text Works by Samuel Pepys at Project Gutenberg <http://www.gutenberg.org/browse/authors/p#a1181>
1660年の日記 <http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/4/1/2/4125/4125.htm>
"Friday 4 May 1660" The Diary of Samuel Pepys <http://www.pepysdiary.com/archive/1660/05/04/>
![]()
どなたか押してくださらんだろうかw
3月5日の手紙 The Letter of March Fifth [Daddy-Long-Legs]
サミュエル・ピープスへの言及にみちていた4年生2月の手紙のつぎは翌月3月5日の手紙です。4年ともなるとジュディーも落ち着いてきて月に一通のペースで書くようになってしまっていますが、それはこのあとのクライマックスにむかって印象的な手紙を集中的にじっくり書く(作家がです)ということのほかに、(1) 手紙に書かれていない時間の経過のなかでジュディーが成長を示し(なかなかあやうい感じもしますが)、(2) 手紙が減ることでジャーヴィー坊ちゃまは不安と疎外感を増すかもしれず、いや、そんなことは最初の読者は知らないことですけれど、なんとなしにサスペンスが漂うような気もします(うそかも)。
あー、そう適当なことを書いていて思い出したのでけれど、3年生の冬に(冬から?)、ジャーちゃんは「あしながおじさん」としてでなくジャーヴィスとして手紙をジュディーに書き送るようになっているようですし("I have been receiving beautiful long letters this winter from Master Jervie (with typewritten envelopes so Julia won't recognize the writing)" (「わたし[ジュディー]はこの冬、マスター・ジャーヴィーからすてきな長い手紙を受け取っています(ジュリアが筆跡でわからないようにタイプで打った封筒に入れて」)[3年生3月22日ごろの手紙: Penguin Classics 13])、同時にサリー・マクブライドの兄でプリンストン大学の学生のジミーも毎週のようにジュディーに手紙を書いていた(いる)ようです("And every week or so a very scrawly epistle, usually on yellow tablet paper, arrives from Princeton")[同じ3年3月の手紙]。このふたりとの手紙のやりとりは、ジュディーからあしながおじさんへの手紙にはもちろん引用されずに、ずっと続いているのだと考えられます(だって二人は恋のライヴァルだから)。
と、書いて、なんでこんな(4年生の3月まで)進んでしまったのだろう、となぜの嵐が????? ま、クライマックスへ行く前に戻りますわ~。
3月5日の手紙は、既に前に「デートと万年カレンダー――ジュディーの誕生日 Dates and the Perpetual Calendar: Judy's Birthday」で触れたように、大学生活の終わりが近づきつつあるジュディーが、4年前の「ブルー・ウェンズデー」を思い起こし、ジョン・グリアー・ホーム(孤児院)をあらためて考える内容を含んでいます。
自己剽窃します。――
ペンギン・クラシックス版だと118ページ、4年生の3月5日の手紙です。この手紙の冒頭で、明日が3月最初の水曜日ということで、孤児院ジョン・グリアー・ホームを思い起こすわけです。それで、出だしも「おじさん」宛てではなくて「理事(評議員)さま」宛てです――
March Fifth
Dear Mr. Trustee,To-morrow is the first Wednesday in the month―a weary day for the John Grier Home. How relieved they'll be when five o'clock comes and you pat them on the head and take yourselves off! Did you (individually) ever pat me on the head Daddy? I don't believe so―my memory seems to be concerned only with fat Trustees.
Give the Home my love, please―my truly love. I have quite a feeling of tenderness for it as I look back through a haze of four years. When I first came to college I felt quite resentful because I'd been robbed of the normal kind of childhood that the other girls had had; but now, I don't feel that way in the least. I regard it as a very unusual adventure. It gives me a sort of vantage point from which to stand aside and look at life. Emerging full grown, I get a perspective on the world, that other people who have been brought up in the thick of things, entirely lack. (Penguin Classics, pp. 118-119)
(3月5日/理事さま
明日は月の第一水曜日――ジョン・グリアー・ホームでは憂鬱な日です。5時になって理事さんたちがみんなの頭をなでて立ち去ったときに皆はどれほどほっとすることでしょう! 理事さん(ご自身)は、私の頭をなでてくださったことがありましたか、おじさま? 私にはそうは思えませんけれど――記憶にあるのはみな太った理事さんたちばかりのようなのです。
ホームへ私の愛をお伝えいただければと存じます――本気の愛です。4年間の霞をとおして振り返ると、ホームに対するほんとうに優しい気持ちを感じます。大学へきたてのころ私はほんとに腹をたてていました。なぜってほかの女の子たちにあった正常な子供時代が自分には奪われていたのですから。でもいまは、少しもそんなふうには考えていません。とてもふつうじゃない冒険とみなしています。脇に立って人生を眺めるという利点を私に与えてくれています。十分に成長してから世に出てきたおかげで、豊かなモノに囲まれて育てられた他のひとたちにはまったく欠けている、世界を見とおす視座があります。)卒業を数ヶ月後に控えて、4年間の時の流れを読者に思い起こさせると同時に、作品冒頭の「ブルーな水曜日」のエピソードを思い出させてしみじみさせる一節なのですけれど、ここで、作家は月日と曜日を組み合わせて出してしまったわけです。「しまった」というのは、他にそういう箇所がないようだからです。
ということで、3月5日の「明日」は水曜日。よって3月6日は水曜日です。
ということで、カレンダーが1912年と1901年と合致するということは、前の記事でも書きました。そして、「ジューディーとジャーヴィー――ジュディーと冒険(3) Judy and Jervie: The Adventurous Judy (3)」で先走りすぎて書きそこねたようですが、2年生の夏にジャーヴィスとともに「たくさんの冒険」をした (“Such a lot of adventures we’re having! [83]) ジュディーは、他ならぬ「ロマンス」的なスティーヴンソンの詩を引用して、「世界」における「幸福」の秘密を語っており(85)、このあと、ジュディーの「冒険」観は修正を受けて、ジョン・グリアー・ホームをひとつの「冒険」として見る視点を得たのだと考えられるわけです。
さて、いっぽうで、この手紙は、ジュディーがあいかわらず「あしながおじさん」の正体がわからぬことを示し、ということはあいかわらず年寄りだと思い込んでいることも示しています(これを読むジャーちゃんは自己分裂に悩み悶えることでしょう)。
ああ、ジャーちゃん。
1901年(ジーン・ウェブスターのヴァッサー卒業の年)と1912年(『あしながおじさん』出版の年)の3月のカレンダー
March
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| __ | __ | __ | __ | __ | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
ジュディーの幸福論――3月5日の手紙(2) Judy on Happiness: The Letter of March Fifth (2) [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』4年生3月5日の手紙の残りは3段落ですが、まずは幸福論になっています。
I know lots of girls (Julia, for instance) who never know that they are happy. They are so accustomed to the feeling that their senses are deadened to it, but as for me―I am perfectly sure every moment of my life that I am happy. And I'm going to keep on being, no matter what unpleasant things turn up. I'm going to regard them (even toothaches) as interesting experiences, and be glad to know what they feel like. "Whatever sky's above me, I've a heart for any fate."
(自分が幸せなのだと決して知らない女の子をわたしはたくさん知っています(たとえばジュリア)。あまりにも幸せに慣れすぎて、感覚が死んでいるのです。でも、あたしはというと――人生の一瞬一瞬に自分は幸せなのだと確信しています。そして、これからもそうあり続けるつもりです、たとえ不快なことが起ころうとも。そういう出来事は(たとえ歯痛でさえも)おもしろい経験だと考えることにし、どういう感じのものなのか知識を得ることを喜ぼうと思います。「どんな空が頭上にあろうとも、わたしはいかなる運命にもむかう心をもつ。」)
1年生10月1日の手紙で「わたしとっても、とっても幸せです、時間の一瞬一瞬が興奮で、ほとんど眠れないくらいです」("I'm very, very happy, and so excited every moment of the time that I can scarcely sleep.") と書き、つづく手紙で「わたしが見たもっとも幸せな女の子たちです――そしてわたしがいちばん幸せ!」("These are the happiest girls I ever saw―and I am the happiest of all!") と書いていたジュディーは、幸福 happiness について何度かリクツをこねています。
ひとつは、2年生の夏にLock Willow から書いた手紙で、スティーヴンソンの詩を引いて、皆がhappy になれるはずだ、というところ(「ハッピー・ソート(幸せの想い)――スティーヴンソンの5度目の言及 Happy Thought: The Fifth Mention of R. L. S.」参照)。(しつこいようですが、この8月の土日にかけて書かれた手紙の前は、ロック・ウィローの土地と人々の退屈さや世界の狭さを嘆いていたのですけれど、ジャーヴィスの登場によって、世界を見る目が変わるのです)。
もうひとつは3年生1月11日の手紙で、過去や未来ではなくて今を生きることが幸せの秘訣だと論じるところ――「華麗で大きな喜び〔快楽〕がいちばん大事なのではありません。小さな喜びから多くのものを引き出すことが大事なんです。――わたしは幸福の真の秘密を発見しました、ダディー。それはいまを生きることです。過去を後悔し続けたり、あるいは未来に期待する〔思い悩む、かも〕のではなくて、この一瞬を最大限に生かすこと。〔・・・・・・〕一瞬、一瞬を楽しむつもりだし、楽しんでいるあいだ、楽しんでいる自分を知るつもりです。たいていの人々は生きていません。ただ競争しているだけ。地平線の遥か彼方のゴールに到達しようとして、行き着くことに必死で、息が切れてあえぐばかりで、自分たちが通ってゆく美しい穏やかな田舎の景色をすっかり見逃してしまいます。そして、気がつくと、年老い疲れきって、ゴールに着こうが着くまいが違いはなくなってしまう。わたしは、路傍に腰をおろしてたくさんの小さな幸せを積み上げることを決心しました、たとえ〈大作家〉に絶対ならなくても。わたしがこんな女哲学者になりつつあるとは知らなかったでしょ? 」 (Penguin Classics 97-98)
さて、3月4日の手紙ですけれど、ふたつめのセンテンスの "the feeling" というのはつまり happiness のことで (it は the feeling)、ここで、幸福感としての happiness と、幸福感の対象としての happiness がいささか混乱しているように思えます。happiness に慣れっこになっている人は happy なのか happy ではないのかパラドックスが生じています(ホントか?)。
つっこみを続ければ、歯痛をその経験の知の獲得ゆえに happy と感じることが可能だとしても、二度目三度目となれば、あるいは歯痛が恒久的に続けば happy とは感じられないだろうw。あるいは一瞬一瞬がhappy だったら差異のない世界になってしまいますから、結局 happy の意味が価値をもたなくなってしまうのではないでしょうか。うゎー、大人気ないつっこみだこと。
なんだか、「幸せは いつも 自分の心が決める」とか「いまが大事」とか言った相田みつを(せんだみつおではない)を思わせるところなきにしもあらずですが、快と不快、快楽と苦痛が逆転してしまう境地は仏教的なものに近いのかもしれません。
もちろん、いずれも心構えのことであって、それはジュディーだってわかっているでしょうし、わたし(モーリちゃんの父)だってわかってはいますけれどね。
そしてまた、幸福であることに気づかない人たちとして、3年生6月10日の手紙(ダディーが夏にヨーロッパへ行かせてあげようと申し出たのを断る手紙)では、ジュリアのみならずサリーも含められるのですが、そこに、そしてずっと後にまで、あるのは、孤児としての自分の生い立ちとの比較の意識です。――
You mustn't get me used to too many luxuries. One doesn't miss what one has never had; but it's awfully hard going without things after one has commenced thinking they are his―hers (English language needs another pronoun) by natural right. Living with Sallie and Julia is an awful strain on my stoical philosophy. They have both had things from the time they were babies; they accept happiness as a matter of course. The World, they think, owes them everything they want. (Penguin Classics 105-106)
(わたしを過度の贅沢に慣れさせてはいけません。誰でも、持ったことがなければ、それがないことを残念に思いませんが、一度それが彼――彼女の(英語にはもう一つ代名詞が必要です)自然の権利だと思いはじめたら、それなしですますのがすごく困難になります。サリーやジュリアと一緒に生活していると、わたしの禁欲哲学はすごいストレスを受けます。二人とも赤ん坊の頃からふんだんなモノを手にしてきました。幸せを当然のことだと思っています。この世界は、彼女たちは、欲しいものをすべて提供して当然なところだと考えています。)
思えば4年3月5日の手紙も、孤児院の回想から始まっているのであって、冒頭に引用した段落も、自分の生い立ちの意識と無縁ではありません、というか、孤児院生活を「冒険」と見る前段とつながっているわけでした。
この孤児意識はこの物語のエンジンみたいなものですから、結末までジュディーのキャラクターを支配しますし、それゆえにジュディーの発言は単なる人生訓にならずに胸を打つ、と言えるのかもしれません。素朴に泣かせるところもあるけれど、リクツっぽい箇所はなかなか複雑です。(さらにユーモアと諷刺が話を複雑に面白くしている・・・・・・あー、大叔父さんのマーク・トウェインに似ているかも。あるいはここで考えてもいいかもしれないのは、たとえばスティーヴンソンの『子供の詩の庭』は子供向けに書かれたものだけれど、『あしながおじさん』はそうではない、ということです)。
そういうわけで、ジュディーは卒業後の9月19日の手紙の追伸では、"PS. I'm very unhappy." と書くことになります。
Robert Louis Stevenson, "Happy Thought," (illustrated by Jessie Willcox Smith) A Child's Garden of Verses (New York: Scribner's, 1905), p. 84
/////////////////////////////
「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる 相田みつを ― 名言から学ぶ幸せのヒント -」 <http://meigen.shiawasehp.net/a/m-aida19.html> 〔本多時生さんの『幸せのホームページ』内〕
「相田みつを名言集」 <http://www.nicozon.net/player.html?video_id=sm9164023> 〔ニコニコ動画〕
「どんな空が自分の上にあろうとも、わたしはいかなる運命にもむかう心をもつ」――3月4日の手紙 (3) "Whatever sky's above me, I've a heart for any fate": The Letter of March Fifth (3) [Daddy-Long-Legs]
前の記事で引用した『あしながおじさん』4年生3月5日の手紙の一節の最後の引用符に入っている "Whatever sky's above me, I've a heart for any fate." (「どんな空が自分の上にあろうとも、わたしはいかなる運命にもむかう心をもつ」)について。
これは、早くに岩波文庫で遠藤寿子が「空が頭の上でどんな顔をしていようと、わたしはびくともしない覚悟だ。」と訳して、割注で「(バイロンの詩 "To Thomas Moore" の中の詩句)」と注記しているように、イギリスのロマン派詩人、バイロン卿 ジョージ・ゴードン・バイロンの詩の引用です。"sky" は日本語(英和辞典)だと「空模様」という感じかもしれません。もっとも、そう言い出すと、"heart" も「勇気」だと言い出しかねなくなりますけれど。
バイロン(George Gordon Byron, 1788-1824) の友人で、バイロンの文学管財人 literary executor (ポーに対するグリズウォルドみたいなもんです)に生前指名され、のちに書簡や日記を編纂し、(伝記は遺族によってダメ出しされ破棄しますが)回想記を出版することになる、アイルランドの詩人トマス・ムア (1779-1852) 宛の1817年7月10日付けの手紙に挿入されていた詩です。短いので全文引きます。――
My boat is on the shore,
And my bark is on the sea;
But, before I go, Tom Moore,
Here's a double health to thee!
Here's a sigh to those who love me,
And a smile to those who hate;
And, whatever sky's above me,
Here's a heart for every fate.
Though the ocean roar around me,
Yet it still shall bear me on;
Though a desert should surround me,
It hath springs that may be won.
Were't the last drop in the well,
As I gasp'd upon the brink,
Ere my fainting spirit fell,
'Tis to thee that I would drink.
With that water, as this wine,
The libation I would pour
Should be―peace with thine and mine,
And a health to thee, Tom Moore!〔太字強調付加。text は、たとえば "To Thomas Moore Analysis George Gordon, Lord Byron: Summary Explanation Meaning Overview Essay Writing Critique Peer Review Literary Criticism Synopsis Online Education" <http://www.eliteskills.com/analysis_poetry/To_Thomas_Moore_by_George_Gordon_Lord_Byron_analysis.php> (いまのところ書き込み一個もないんすけど〕
第2連3行目の And のあとの "whatever sky's above me," は(大文字を別として)全く同じですが、その次の行の "Here's a heart for every fate." はジュディーの "I've a heart for any fate." とビミョーに違っているのがわかります。
そこでアメリカ文学的におのずと思い起こされるのは、ちょっと遅れてきたアメリカのロマン派詩人ロングフェロー (Henry Wadsworth Longfellow, 1807-82)の "A Psalm of Life" (1838) という、たいへん有名で、よく朗誦された詩です。「人生讃歌」と訳されますが、詩の副題というか、冒頭に "What the Heart of the Young Man Said to the Psalmist" (若者の心が讃美歌作者に語ったこと) とあって、因習的なキリスト教の人生観を批判しているところがある(それゆえロマン主義的)とふつう考えられています。長いけど全文引いちゃいます。
"A Psalm of Life"
What the Heart of the Young Man Said to the Psalmist
Tell me not in mournful numbers,
Life is but an empty dream!
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.
Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou are, to dust thou returnest,
Was not spoken of the soul.
Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each tomorrow
Find us farther than today.
Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.
In the world's broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!
Trust no Future, howe'er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act, ―act in the living Present!
Heart within, and God o'erhead!
Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sand of time;
Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.
Let us then be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.〔太字強調付加。この詩はトロント大学の RPO: Representative Poetry Online に注釈付きで載っています <http://rpo.library.utoronto.ca/poem/1339.html> しかし "psalmist" を詩人自身としているところが解せませんが・・・・・・自己分裂ということですかね〕
9連からなるけっこう長い詩だし(この詩を対訳と注釈付きで入れている岩波文庫の『アメリカ名詩選』が見つからないので)、とりあえずでだしのところを(Web 上で訳が付いている紹介は「人生賛歌--ロングフェロー-ヘ短調作品34」 <http://blogs.yahoo.co.jp/fminorop34/48575467.html> など)――「わたしに言わないでくれ、悲しい調べで/ 人生はただむなしい夢だなど!/ 眠りこける魂は死んだも同じ/ ものは外見とはちがうのだから。// 人生はリアル! 人生は大事!/ 墓がそのゴールではない/ 汝塵なれば塵に帰るとは/ 魂について言われたことではない。」 旧約聖書「創世記」にあって、埋葬の祈祷の一節に用いられることでも有名な "In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return." (Genesis 3.19) の "shalt thou return" が、earnest と韻を踏ませるべく助動詞 shall を落として "thou returnest" に変えられてますけれど、聖書の教えへの言及は明白で、塵に帰るのは体的部分であって魂は違う、と主張すると共に、現世における生こそがリアルだ、とプラトン的=キリスト教的世界観に(一定程度は)異を唱えるわけです。まあ、そのさきで霊的な神秘主義にむかうわけではなく、むしろ現実を大事にすること、「人生という戦場で・・・・・・戦いの英雄であれ」(第5連)という現世肯定と進歩のメッセージが主眼なのですけれど。
そういう詩の最終第9連に、バイロンからの「引用」が出てきます。その2行目の "With a heart for any fate" は、バイロンそのもの("Here's a heart for every fate" )ではない。そして、むしろ『あしながおじさん』のジュディーの "I've a heart for any fate" に近いところもあります。あるのではないでしょうか。少なくとも詩全体のメッセージは、ロングフェローの「人生讃歌」のほうがジュディーには共振するところが大きいと思われます。
だとすると、このジュディーの「引用」の「原典」とのズレは、意識的なものであって、英文科の学生として英米の詩人を勉強したジュディーの成果がひそかに示されている、と言うこともできるのではないかと思ったりもします。
From A Psalm of Life (New York: E. P. Dutton, 1891), image via Wikimedia <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Psalm_of_Life.png>
- Footprints, that perhaps another,
- Sailing o'er life's solemn main,
- A forlorn and shipwrecked brother,
- Seeing, shall take heart again.
E-text:
A Psalm of Life (New York: E. P. Dutton, 1892) [illustrated] <http://www.archive.org/stream/apsalmlife00peirgoog#page/n8/mode/1up>
A Psalm of Life (New York: Lovell 1900) [譜面付き]<http://www.archive.org/stream/psalmoflife00long#page/n7/mode/2up>
"A Psalm of Life" は岐阜女子大のDEAPA (Digital English and American Poetry Archive) (科学研究費補助金(基礎研究C);「デジタル・アーカイブを用いた英語教育・異文化コミュニケーション教育の基礎的研究」)にも入っていました(岩波文庫の『アメリカ名詩選』の訳と注釈が組み込まれている様子です)――<http://dac.gijodai.ac.jp/studioM/deapa/poem_long01.htm#top>
ルソーのように5人子供ができても孤児院の玄関に置き去りにしたりはしない――3月5日の手紙(4) If I Have Five Children, Like Rousseau, I Shan't Leave Them on the Steps of a Foundling Asylum: The Letter of March Fifth (4) [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』4年生3月5日の手紙の、「3月5日の手紙 The Letter of March Fifth」と「ジュディーの幸福論――3月5日の手紙(2) Judy on Happiness: The Letter of March Fifth (2)」(と「どんな空が自分の上にあろうとも、わたしはいかなる運命にもむかう心をもつ」――3月4日の手紙 (3) "Whatever sky's above me, I've a heart for any fate": The Letter of March Fifth (3)」)で引用した箇所につづくパラグラフです。
However, Daddy, don't take this new affection for the J. G. H. too literary. If I have five children, like Rousseau, I shan't leave them on the steps of a foundling asylum in order to insure their being brought up simply. (Penguin Classics 119)
(でも、ダディー、このJ・G・H に対する新たな愛情をあんまり文字どおりに取らないでください。もしもわたしに、ルソーのように、5人子供ができるとしても、単に〔純真なる? simply ただただ?〕その成長を保証するためにと孤児院の玄関の踏み段に置き去りにするなどということはいたしません。)
ペンギン版のエレーン・ショーウォルターは、Rousseau に63番の注を付けています (Penguin Classics 353)。――
Rousseau: Jean[-]Jacques Rousseau (1712-1778), Swiss-born French philosopher and author of The Social Contract. Rousseau had five children with a servant girl and placed them in an orphan asylum.
(ジャン=ジャック・ルソー (1712-78) はスイス生まれのフランスの哲学者で『社会契約論〔民約論〕』[1762] の著者。ルソーは女中の娘とのあいだに5人の子をもうけ、孤児院にいれた。)
ショーウォルターは書いていませんけれど、伝記的なことがらは、ルソーの有名な『告白』に自ら書かれています。これはなかなかに微妙なハナシですので、長いのですが、該当箇所を書き抜いてメモっておきたいと思います。
その前に、簡単にルソーについて書いておきます。ルソーは1732年に故郷のスイスのジュネーヴを離れ、ヴィラン男爵夫人に庇護されて教育を受けました。愛人関係となった夫人と別れたのち、1740年からリヨンで家庭教師、そして1742年に新しい記譜法を発表してパリに出てディドロと親しくなります。1745年、下宿の女中テレーズを愛人とし、10年間で5人の子を産ませ、いずれも孤児院に送りました。
内気で皆にからかわれるテレーズ(ル・ヴァスール夫人の末娘)をかばったルソーもまた内気な性格で、「この共通した気質は、二人の間を遠ざけるようにみえながら、かえって急速にむすびつけ」る。母親はそれに気づいて腹を立て、娘を折檻しますが、その手荒な仕打ちのために二人の仲はさらに深まり、テレーズはルソーを保護者として頼るようになります。
彼女が身をまかす前に、口ではいえないで、察してもらいたそうにして、もじもじしている様子にわたしは気づいた。ところが、当惑の真の原因を想像するどころか、わたしはまったく的はずれの、しかも彼女の品行を侮辱するような原因を考え出したのである。病気がうつる危険を警告しているのだと思いこんで、わたしはとまどった。思いとどまりはしなかったが、数日のあいだ幸福感は害された。〔・・・・・・〕やっとたがいに心のうちを説明しあった。彼女は、ものごころのつくころ、自分の無知と、誘惑者のたくみさのために、一度だけあやまちを犯したことがあることを、涙ながらに告白した。彼女のいうことがわかったとたん、わたしは歓声をあげた。「処女なんて!」とわたしはさけんだ。「パリで、しかも二十歳にもなった女に、だれがそんなものを求めるもんか! ああ、テレーズ! ぼくはしあわせすぎる、貞淑で健康なおまえが、ぼくのものになったんだから。そして、ぼくが求めていなかったものが、見つからなかったんだから。」
最初は、ほんのなぐさみにするつもりだった。しかしそれ以上に深入りし、一人の伴侶をこしらえてしまったことに気づいた。このすぐれた娘と少し慣れ、また自分の境遇を少し反省してみて、ただ快楽ばかりを求めていたのに、それがわたしの幸福にも大いに役立ったことを感じた。消え去った野心のかわりに、心をみたしてくれる、なにかはげしい感情がわたしには必要だった。つまり、ママンのかわりがほしかったのだ。だが、今はもう、ママンといっしょに暮らすわけにはいかぬ以上、ママンの手で教育されたこのわたしといっしょに暮らしてくれるひと、ママンがわたしのうちに見出したような、素朴で従順な心のもちぬしが必要だった。(桑原武夫訳『告白』 (筑摩書房「世界文学大系17」) 203)
へたすると『カサノヴァ情史』的なノリです。ママンという、ふた昔、いや三昔前の少女マンガを思い起こさせる言葉(個人的)は、母親ではなくて、ヴィラン男爵夫人のことです。ルソーはテレーズを教育しようとしますが、うまくいきません。――
まず彼女を教育しようと思ったが、骨折り損だった。彼女の精神は自然がこしらえたままで、教養や配慮はききめがないのだ。打ち明けていうと、字はどうにか書けたが、読むことは満足にできなかった。ヌーヴ=デ=プチ=シャン街に移住したとき、窓の真向いにポンシャルトラン旅館の日時計があったが、その時間を教えこむのに一ヵ月以上も努力した。今でもまだ十分にわかってはいない。一年の十二ヶ月を順にいうことができず、どんなに努力して教えても、数字は一つもおぼえられない。
ルソーはテレーズのとんちんかんな言葉遣いを辞典にして、彼の交際している人たちのあいだで有名になったりもしますが、「こんなに愚かな女も、いざというときにはすぐれた助言者」となること、また高い身分の人のあいだでも「彼女の意見、良識、応答、ふるまいは一同の尊敬の的となり、またわたしは彼女の美点について、心からの讃辞をうけた」とも書いていますし、「わたしは世界一の天才といっしょにいるような楽しさでテレーズと暮らした」とも書いています (204)。
ルソーはこのころオペラの作曲をしたり、それから化学に関心を新たに示して本を書き出したりするのですが、1847年の秋にシュノンソー離宮に化学の本の共著者のフランクイユ氏と一緒に旅行に出かけます。で、そのあとに、記されているのが子供のはなしです。――
わたしがシュノンソーで太っているあいだに、パリではテレーズがべつの太りかたをしていた。そしてもどってみると、中途半端で投げ出しておいた事態は予想外に進行していた。今の境遇では、まったく困ったことになるところだったが、ありがたいことに、食事仲間がそこを切り抜ける唯一の手段をさずけてくれた。これは、あまり簡単に語ることのできない重要な物語の一つなのである。というのは、いちいち注釈を加えれば、自己を弁護するか、非難するかしなくてはならなくなるだろうが、そのいずれもわたしはここでやってはならないからである。
アルトゥーナがパリに滞在していたころ、わたしたちは飲食店には行かずに、近所の、オペラ座の袋小路とほぼ向かいあった、仕立屋のおかみさんのラ・セル夫人というひとのところに食事に行くことにしていた。ここは料理はまずいが、善良で確実な人たちが集まるというので評判がよかった。事実、ふりの客は入れず、常連のだれかの紹介が必要だった。礼儀正しく、機智にとんではいるが、猥談ずきの老遊蕩児グラヴィル三等騎士がその家に泊っていて、騒ぎ好きで派手な、若い近衛士官や近衛騎兵たちをひきつけていた。ノナン三等騎士はオペラ座の踊り子全部のナイトをもって自認していて、毎日、楽屋のあらゆるニュースをもたらす。退役陸軍中佐で、分別ある好老人のデュ・プレシと、近衛騎兵士官のアンスレの二人が、この青年たちのあいだにいくらかの規律をたもたせていた。ここにはまた商人や、金融業者や、軍の糧食御用商人らがやってきたが、いずれも礼儀正しく、正直な、同業者のうちでも目立った人たちだった。ベス氏、フォルカード氏、そのほかにもいたが、名前は忘れた。要するに、あらゆる職業のすぐれた人たちが集まっていた。ただ僧侶と法律家はべつで、これには一度もお目にかかったことがない。仲間に加えない約束になっていたのだ。ここの食事はかなりの大人数で、たいてい陽気だが騒々しくはなく、きわどい話もずいぶん出たが、下品にはならなかった。老三等騎士の話はすべてみだらな内容のものだが、彼はむかし身につけた宮廷の作法をけっして忘れることなく、なにか下品な言葉を口にしてもたいへんおもしろかったから、女のひとでも、とがめはしなかったにちがいない。彼のそうした調子が一座の規準となって、若者たちもみな無遠慮に、しかし品を落とすことなく、めいめいの色事を物語るのだった。しかも女の話は、すぐ近くにその倉庫があっただけに、ますます事欠かない。というのは、ラ・セル夫人のところへ行く小路に、有名な流行品店のラ・デュシャプトの店があり、当時きれいな娘を何人かやとっていたので、みなは食事の前後におしゃべりに行ったからである。もしわたしがもっと大胆だったら、この連中同様そこで楽しんだだろう。彼らと同じように入って行きさえすればいいのに、それがどうしてもできなかった。このラ・セル夫人のところには、アルトゥーナが帰って行ってからも、しばしば食事をしに行った。そこでおもしろい逸話をたくさんきいたし、また彼らのあいだで支配的な生活方針を徐々に身につけたが、さいわいにもその風習には染まらなかった。ひどい目にあわされた正直者、欺かれた夫、誘惑された妻、人目をしのぶ出産、こういったことがここでのごくあたりまえの話題だった。そして孤児院にいちばんたくさん子供をいれたものが、つねにもっとも賞讃されていた。こうした空気にわたしも感染した。まことに愛すべき人たち、そして腹の底はじつにまじめなこの人たちの間で行なわれている考え方をもとにして、わたしは自分の考え方をきめた。そしてこう思った。これがこの国の習慣なのだから、ここに住む以上はそれに従っていいはずだ、と。これこそわたしの求めている給与の策だったのである。わたしはなんのためらいもなく、敢然とそれにたよる決心をした。* ただひとつ克服せねばならないのは、テレーズの心配である。彼女の体面をまもるための、この唯一の手段を承知させるのに、なみなみならぬ苦心を要した。母親も、このうえ赤ん坊の世話までしなくてはならなくなるのをおそれて、わたしの味方になってくれたので、ついにテレーズも同意した。サン=トゥスターシュ街の角に住む、グアンという用心ぶかくて確実な産婆をえらんで、その手にテレーズのからだをあずけることにした。そしていよいよその時になると、テレーズは母親につれられてグアンのところへ行き、お産をすませた。わたしは何度か見舞に行き、二枚のカードにまたがるように頭文字の組合せを書いたのをもって行った。その一枚は赤ん坊の産着におさめられ、赤ん坊は、普通の形式にしたがって、産婆の手で孤児院の事務所にあずけられた。その翌年も同じ目にあい、同じ手段で切りぬけた。ただし頭文字を組み合わせたカードだけはやめた。今度はもうわたしも考えこんだりしなかったが、テレーズのほうは相変わらず、なかなか承知してくれなかった。彼女は泣く泣く従った。この宿命的な行為が、その後わたしの考え方や運命にどれほどのはげしい変化をもたらしたかは、おいおいわかるだろう。今はその最初の時期だけにとどめておこう。その結果が思いがけなく、また苛酷なものであった以上、わたしは後にもう一度このことに触れざるをえなくなるであろう。(219-220)
これが1747年と1748年、ルソー35歳のころの話です。桑原武夫は *印のところに歴史的注釈を付しています(原文の漢数字をアラビア数字に変更)。――
パリでの捨て子は多かった。当時人口約60万であったが、1740年には3,150、1745年には3,334 の捨て子があった。ビュフォンの『博物誌』によると、1772年には18,713 の出産があったが、うち7,676 人が孤児院におくられている。
つぎの第八巻のはじめのほうにつづきの話が書かれています。心情の悔恨を理性(つまりは頭=リクツ)の側にくみすることでおさえるような屈折した(ふつうに読めば身勝手な)文章です。――
人間の義務について哲学的考察をめぐらしているあいだに、ある事件がおこって、自分自身の義務についてもっとふかく反省させられることになった。テレーズが三たび妊娠したのである。行為によって主義を裏切るには、あまりにも自己に誠実で、またあまりにも誇り高い心をもつわたしは、自然と正義と理性の法則、さらには宗教の法則にてらして、自分の子供たちの前途や、その母親と時分との関係などを検討しにかかった。ところでこの宗教なるものは、本来はその創始者同様にけがれなく、神聖かつ永遠であるのに、人間がそれを純粋なものにするような顔をして、かえってけがしてしまい、勝手な方式にしたがってたんなる口先きだけの宗教と化してしまったのだ。実行しなくてもいいとなれば、不可能なおきてを定めることくらい、なんでもないことだから。
たとえ結果においてまちがっていたにせよ、わたしがそれに従ったときの落ち着きはらった気持は、まさにおどろくべきものである。もしわたしが、やさしい自然の声に耳をかさず、正義と人道との真の感情が心のうちにけっしてとざすことのない、そうしたたちの悪い人間の一人だったら、こうした冷酷さもごく当然のことであろう。しかし、この心情のあたたかさ、感じやすさ、すぐに愛着をおぼえ、それにしばられるはげしさ、愛着を絶たねばならぬときの胸をひき裂かれる思い、同胞にたいする生まれつきの親切心、偉大さ、真実、美、正義にたいする熱烈な愛、あらゆる悪への嫌悪、憎んだり害をくわえたりするだけでなく、そんな気をおこすことすらできぬ性質、すべて徳高いもの、寛大なもの、愛らしいものいっさいを目にすれば、はげしく快い感動をおぼえる心、――すべてこうしたものが、義務のなかでももっともこころよい義務までも容赦なくふみにじらせる堕落した心性と、同じ一つの魂のうちで結びつくことが可能だろうか。いや、わたしは感じる、そしてはっきりという、それは不可能だと。生涯の一瞬たりとも、このジャン=ジャックは冷酷無常な男、人道にもとる父親にはなりえなかった。わたしはあやまちをおかしたことはあるだろうが、けっして冷酷になることはできなかった。理由をあげだせば、きりがなかろう。それがわたしをあやまらせた以上、他人をもあやまらせることもあろう。わたしはこれをよむ若い人たちを、わたしとおなじあやまちにおちいらせたくないのだ。ただ、つぎのことをいうにとどめたい。すなわち、わたしはわが子を自分の手で育てることができなかったので、彼らの教育を社会施設に託し、将来、ごろつきや山師などよりも、労働者か百姓になるようにしておけば、それで市民および父親にふさわしい行為をなすことになると信じていた。そして自分をプラトンの国家の一員と思っていたのである。そのとき以来、一度ならず、心情の悔恨によって、自分がまちがっていたことをおしえられた。しかし理性はそんな注意をあたえてくれなかった。それどころか、自分の処置によって子供たちをその父親の運命から守り、また彼らをみすてなくてはならなくなったとき彼らをおびやかすにちがいない運命から、彼らを守ってやったことを、天に感謝したことがたびたびあるくらいだ。その後、デピネ夫人やリュクサンブール夫人が、友情からか、寛大さからか、あるいは何かほかの動機からか、子供を引きとってやろうといってくれたが、その手にゆだねたところで、はたして彼らはもっと幸福だっただろうか。あるいは少なくとも、もっとまともな人間に育っていただろうか。それはわからない。が、両親を憎み、おそらくは裏切るような人間になっていたことは確実である。それよりも、両親を知らなかったほうがはるかにましだ。
そういったわけで、三番目の子供も、はじめの二人同様、孤児院にいれられた。その後の二人も同様である。つまりわたしには全部で五人の子供があったのだ。この処置はたいへんよく、道理にかない、また正当であるように思えたが、それを大っぴらに自慢しなかったのは、もっぱら母親への気がねからである。だがわたしたち二人の関係をうちあけてあった人たちのすべてには、そのことをしゃべった。ディドロにも、グリムにも。また後ほどデピネ夫人に、さらに後にはリュクサンブール夫人にも、話した。だが、なにも必要にせまられてではなく、こちらからすすんで率直にしゃべったまでのことで、かくそうと思えば、だれにでも簡単にかくせたのである。というのは、産婆のグアンは正直な女で、たいへん口がかたく、わたしは信頼しきっていたからだ。友だちのうち、打ち明けて得をしたのは、医者のチエリだけである。彼には、テレーズが一度難産したときに手をかしてもらった。要するに、わたしは自分の行為をいささかも隠しだてしなかった。これは、わたしが友人にはなにごとも隠せない人間であるからだけでなく、実際、その行為をすこしも悪いと思っていなかったからだ。すべてを考慮した上で、わたしは子供たちのために最善の方法、あるいは自分で最善と信じた方法をえらんでやったのである。わたし自身、彼らと同じように育てられたらよかったと思ったし、いまでもそう思っている。(219-220)
ルソーの年譜を見ると、1747年ではなくて1746年の暮れに第一子の出産、そして捨て児があったようです。テレーズ・ルヴァスールとの関係が始まるのは1745年3月でした(ルソー32歳)。1748年、第二子の出生と捨て児。
ルソー自身は、1712年6月28日にスイスのジュネーヴに生まれますが、7月7日に母親が亡くなり、伯母に育てられます。10歳の1722年7月に父親が出奔、牧師の家に預けられました。ですから、ルソーも孤児でした。1724年にはジュネーヴに戻り伯父の家に住みますけれども、翌年には5年契約の徒弟奉公に入ります(彫金)。しかし1728年3月、15歳のときに(3月13日、散歩に出て市の門の閉鎖に遅れ、翌日に)ジュネーヴを去り、以後、彷徨と仮装の人生が始まります。
さまざまな女性と関係をもちながらも、テレーズとは1768年の8月に結婚しています(56歳)。1778年7月2日、散歩のあとテレーズと朝食、午前11時ルソー死す(享年66)。テレーズは翌年の9月に、ルソーの知己であったジラルダン公爵の従僕と再婚しました。
『告白』の記述を信じれば(つまり、他の資料も参照しないと確かなことはわかりませんが)、ルソーは孤児院に子供を送るのに、グアンという「産婆の手で孤児院の事務所にあずけられた」ということで、玄関口に遺棄するということはしなかったことになります。
もしかすると、「孤児院の玄関の踏み段に置き去り」というのは、ジュディー自身の体験の再現なのかもしれません。(あるいは単に記述を簡潔にしておもしろくするための改変かもしれません。あるいは事実を調べたのかもしれません。わかりません。)
ジュディーの遺棄については、2年生の9月25日の手紙で、クラスに外国の修道院校で子供の頃に3年過ごしたためにフランス語が得意な子がいることで、冗談めかして、"I wish my parents had chucked me into a French convent when I was little instead of a foundling asylum." (わたしの親が、わたしがちっちゃかったときに孤児院ではなくてフランスの修道院校に投げいれてくれていたらよかったのに)と言うところに間接的にほのめかされている可能性があると思うのですが、もろもろの訳書を見ると、なんかぜんぜん違う感じもするので、もうちょっと他の場所も読みなおしたり考えたりしてみます。
それから、引用文中の "[brought up] simply" は、訳者によってさまざまに解されています。「質素に育つ」というのが多いみたいですけれど。ルソーを読んだあとでは「強調」であると結論しました(自信89パーセント)。
よろしくと伝えて――ジュディーの幸福論 (2) Give Kindest Regards to: Judy on Happiness (2) [Daddy-Long-Legs]
流れで、『あしながおじさん』4年3月の手紙の最後のところです。
Give my kindest regards to Mrs. Lippett (that, I think, is truthful; love would be a little strong) and don't forget to tell her what a beautiful nature I've developed.
Affectionately,
Judy
(リペット先生にはジュディからくれぐれもよろしくとお伝えいただきたく(これがほんとのところだと思います。愛といったのではちょっと強いでしょう)、また、いかに美しい性質を開発したかを忘れずにお話しください。)
流れで書いていますが、特別なにか書きたい箇所というのではなくw しかし、そういうところで何かしぼり出す努力をすることによって世の中や人生は開けてくるのではないかという気もします(気がするだけですし、出てくる何かがおもしろいとは限りませんが・・・・・・だからこの世はおもしろいのか、も)。しかしこういう駄文を読むのを自分のなかの自分以外のひとに求めるのは申し訳ないような気がします。そこで申し訳に必要なのは誠実さなのかしら。あるいは/そして遊戯・演技なのかしら。
と無駄な前口上はそれくらいにしてっと。
まず英語の勉強ですかね(芸がない)。
カッコのなかの "that" は "my kindest regards" あるいは "regards" を、あるいは "Give my kindest regards to Mrs. Lippett" を指しています(選択肢多すぎだったら、最後のということになりますけれど、結局は「愛では強すぎる」といって "love" と対比されているものは "regards" に他なりません)。
この一文は、この3月5日の手紙のふたつ目の段落と呼応しています。
To-morrow is the first Wednesday in the month―a weary day for the John Grier Home. How relieved they'll be when five o'clock comes and you pat them on the head and take yourselves off! Did you (individually) ever pat me on the head Daddy? I don't believe so―my memory seems to be concerned only with fat Trustees.
Give the Home my love, please―my truly love. I have quite a feeling of tenderness for it as I look back through a haze of four years. When I first came to college I felt quite resentful because I'd been robbed of the normal kind of childhood that the other girls had had; but now, I don't feel that way in the least. I regard it as a very unusual adventure. It gives me a sort of vantage point from which to stand aside and look at life. Emerging full grown, I get a perspective on the world, that other people who have been brought up in the thick of things, entirely lack. (Penguin Classics, pp. 118-119: emphasis added)
(3月5日/理事さま
明日は月の第一水曜日――ジョン・グリアー・ホームでは憂鬱な日です。5時になって理事さんたちがみんなの頭をなでて立ち去ったときに皆はどれほどほっとすることでしょう! 理事さん(ご自身)は、私の頭をなでてくださったことがありましたか、おじさま? わたしにはそうは思えませんけれど――記憶にあるのはみな太った理事さんたちばかりのようなのです。
〈ホーム〉へ私の愛をお伝えいただければと存じます――本気の愛です。4年間の霞をとおしてふりかえると、ホームに対するほんとうに優しい気持ちを感じます。大学へきたてのころわたしはほんとに腹をたてていました。なぜってほかの女の子たちにあった正常な子供時代が自分には奪われていたのですから。でもいまは、少しもそんなふうには考えていません。とてもふつうじゃない冒険とみなしています。脇に立って人生を眺めるという利点をわたしに与えてくれています。十分に成長してから世に出てきたおかげで、豊かなモノに囲まれて育てられた他のひとたちにはまったく欠けている、世界を見とおす視座があります。)
ジョン・グリアー・ホーム孤児院には「愛」を伝えてほしいけど、院長先生には「愛」というのではちょっと強い。それでも、それでも、最上級の "kindest" とするところが、それ(その言葉)が形式的なものであれ、ジュディーの精一杯の心情を示しているのでしょう。泣けるところです。すこし。
それでも、こんなふうにマジメに考えるワタシは美しい性質を発展させつつあるような気もするくらいですが、なんだか作品に塗装されているユーモアの層をめくるというエッチなふるまいをしているような気もします。というか、めくるめくめくるならおもしろいかもしれないけれど、めくって顧みないという。めくったものとめくった下にあるものを同時に眺めるということをひとはなかなかできないものなのかなあと。(それにしても、ヒユに頭が進むことによって実体から離れるという誤りをおかしていますね、われながら。)
☆ジュディーが展開する性格についてのメモ
(1) 1年生の4月か5月の金曜日の手紙――
Did you ever hear of such a discouraging series of events? It isn't the big troubles in life that require character. Anybody can rise to a crisis and face a crushing tragedy with courage, but to meet the petty hazards of the day with a laugh―I really think that requires spirit.
It's the kind of character that I am going to develop. I am going to pretend that all life is just a game which I must play as skilfully and fairly as I can. If I lose, I am going to shrug my shoulders and laugh―also if I win. (Penguin Classics 38)
(〔ツイテナイ一日のあとで〕 これほどたてつづけにガックリする出来事が起こるって聞いたことありますか? 人格が求められるのは、人生における大きな困難ではありませんん。だれでも、危機に耐えることはできるし、押しつぶされそうな悲劇に勇気をもってたちむかうことはできますが、日常のささいな事故に笑いをもってむかいあうとなると――精神 〔"spirit" よくわからないです。フランス語の「エスプリ」みたいなもんでしょうか〕が必要だとわたしはほんとに思うんです。
わたしが開発しようと思っているのはそういう種類の人格です。人生はできるだけ上手かつフェアにプレイせねばならぬゲームにほかならない、というふうを装っていきたいと思います。負けたらば肩をすくめて笑います――勝ったときにも。)
(2) 1年生の5月30日の手紙――
I'm going to be good and sweet and kind to everybody because I'm so happy. And this summer I'm going to write and write and write and begin to be a great author. Isn't that an exalted stand to take? Oh, I'm developing a beautiful character! It droops a bit under cold and frost, but it does grow fast when the sun shines.
That's the way with everybody. I don't agree with the theory that adversity and sorrow and disappointment develop moral strength. The happy people are the ones who are bubbling over with kindliness. I have no faith in misanthropes. (Penguin Classics 40)
(誰にたいしてもいいひとでやさしく親切であろうと思います。なぜってわたしはとっても幸せだから。そしてこの夏は書いて書いて書いて大作家への一歩をあゆみはじめるつもりです。なんと高邁な姿勢ではないでしょうか? ああ、わたしは美しい人格を発展しつつあるのです! 寒さと霜のしたではちょっとうなだれますが、日が照ればがぜん成長するのです。
これは誰でもそうです。逆境と悲哀と失意が倫理的な強さを発展させるのだという説にはわたしは同意しません。幸せなひとは親切な思いであふれているひとです。わたしは人間嫌いのひとに信を置きません。)
ちょっと(2) の文脈を補足しておきますと、5月のキャンパスの自然の美しさを "paradise" のようだというジュディーは、もうすぐ夏休みだし、試験などもののかずではない、みんなのんびり楽しそうにしている、と書いて、幸福感を口にします。――
Isn't that a happy frame of mind to be in? And oh, Daddy! I'm the happiest of all! Because I'm not in the asylum any more; and I'm not anybody's nursemaid or typewriter or bookkeeper (I should have been, you know, except for you).
(これは幸せなこころがまえではないでしょうか? そして、ダディー! わたしがいちばん幸せ者です! なぜってわたしはもう孤児院にいないのですから。そしてだれかの子守りでもタイピストでも帳簿係でもないのですから(あなたがいなければ、そうなっていたでしょう)。)
孤児院にもはやおらないから⇒自分がいちばん幸せ、という論理の脆弱さを云々するのは大人気ないですw。 子守り、タイピスト、帳簿係云々というのは、5月27日の手紙で、リペット院長から、もうすぐ夏休みだけれど行くところもないだろうから孤児院へ里帰りして大学が始まるまで食費代わりに働くようにという手紙が来たことを書いていたことに関わるのでしょう(つまり孤児院での仕事)。そして、このあと、孤児院での過去の行ないを、どう読んでもユーモアをまじえて、反省し(砂糖つぼに塩を入れておいたこととか、理事たちのうしろでアッカンベーをしたこととか)、(2) の文章が続くのでした。(孤児院がらみで「幸わせ」の話が出るのは、4年3月5日の手紙と同じです。)
話が脱線気味ですが、5月27日の手紙では、"I HATE THE JOHN GRIER HOME."(わたしはジョン・グリアー・ホームが大嫌い)、 "I'd rather die than go back." (帰るくらいなら死んだほうがまし)と孤児院に対する強い感情を吐露していたのでした (Penguin Classics 38)。
ところで、訳語をそろえて不自然な日本語になっているだけでなく、実は英語がよくわからないです。(1) でいうと、人生はゲーム、というのを pretend するのは、結局人生はゲームではない、ということなのでしょうかね(pretend は主張の意味もありますが)。いや、もともと人生はゲームというのはヒユですから、ヒユというふるまい自体がそもそも pretense なのか。
ジュディーの5つのシークレット Judy's Five Secrets [Daddy-Long-Legs]
(このままだと卒業して話が終わってしまいそうなので、直線的な記事の進行を意識的に崩しますのその1. )
ジュディーが語る秘密と秘訣♪ (ほんとは秘密はひとつだけかも)
(1) 2年生3月5日(3月の風が吹く日)
"I never told you about examinations. I passed everything with the utmost ease―I know the secret now, and am never going to fail again."
(試験についてぜんぜん話していませんでした。わたし、すべてらくらく合格しました――秘訣がわかっていますし、もう二度と落とすことはありません。)
〔解説〕ジュディーは1年生の学年末試験でラテン語と幾何で落第点をとってしまい泣きました ("She receives two flunk notes and sheds many tears"――これは本文ではなくて絵の中に書かれているコトバ)。――
Daddy-Long-Legs (New York: Century, 1912)
残念ながらその秘訣をジュディーは語りませんが、When Patty Went to College (1903) から推すと、教師の身になってなんちゃら、というようなことではなかったかと思います(うろおぼえ)。
(2) 2年生8月の日曜日(ロック・ウィローからの手紙)
Isn't this a nice thought from Stevenson?
The world is so full of a number of things,
I am sure we should all be as happy as kings.
It's true, you know. The world is full of happiness, and plenty to go
round, if you are only willing to take the kind that comes your way.
The whole secret is in being pliable. In the country, especially,
there are such a lot of entertaining things. I can walk over
everybody's land, and look at everybody's view, and dabble in
everybody's brook; and enjoy it just as much as though I owned the
land--and with no taxes to pay!
(これはスティーヴンソンのですけれど、ナイスな想いじゃないでしょうか?
世界は数多くのものでとっても満ちあふれている
みんな王様のようにハッピーになるべきだと私は思う
確かにそうです。世界は幸福に満ちあふれ、動き回るのに充分です、ただ自分のもとにあるものを受け入れさえすれば。すべての秘訣はしなやかさです。田舎ではとりわけ面白いことがたくさんあります。誰の土地だって歩きまわれるし、誰の景色でも共有できるし、誰の小川でもパチャパチャはねをあげられます。そして自分がその土地の所有者であるかのように享受できるのです――税金は支払わずに!)
〔解説〕これは記事「ハッピー・ソート(幸せの想い)――スティーヴンソンの5度目の言及 Happy Thought: The Fifth Mention of R. L. S.」などでとりあげた箇所です。そして、「ジュディーの幸福論――3月5日の手紙(2) Judy on Happiness: The Letter of MarchFifth (2)」でも書いたように、ジュディーの幸福論につながるものです。
(3) 3年生12月7日の手紙
[. . .] Do you want me to tell you a secret that I've lately discovered? And will you promise not to think me vain? Then listen:
I'm pretty.
I am, really. I'd be an awful idiot not to know it with three looking-glasses in the room.
(最近発見した秘密を、わたしに話してほしいですか? でも、わたしのことを見栄っ張りだと思わないって約束してくれます? それではお聞かせしましょう――
わたし、きれいなの。
本当です。部屋に3枚も姿見があるのにそれに気づかなかったら、わたしはすごいバカでしょう。 )
〔解説〕 これはほんとの秘密です。
(4) 3年生1月11日の手紙
It isn't the great big pleasures that count the most; it's making a great deal out of the little ones―I've discovered the true secret of happiness, Daddy, and that is to live in the now. Not to be for ever regretting the past, or anticipating the future; but to get the most that you can out of this very instant. It's like farming. You can have extensive farming and intensive farming; well, I am going to have intensive living after this. I'm going to enjoy every second, and I'm going to know I'm enjoying it while I'm enjoying it. Most people don't live; they just race. They are trying to reach some goal far away on the horizon, and in the heat of the going they get so breathless and panting that they lose all sight of the beautiful, tranquil country they are passing through; and then the first thing they know, they are old and worn out, and it doesn't make any difference whether they've reached the goal or not. I've decided to sit down by the way and pile up a lot of little happinesses, even if I never become a Great Author. Did you ever know such a philosopheress as I am developing into? (Penguin Classics 97-98)
(華麗で大きな喜び〔快楽〕がいちばん大事なのではありません。小さな喜びから多くのものを引き出すことが大事なんです。――わたしは幸福の真の秘密を発見しました、ダディー。それはいまを生きることです。過去を後悔し続けたり、あるいは未来に期待する〔思い悩む、かも〕のではなくて、この一瞬を最大限に生かすこと。〔・・・・・・〕一瞬、一瞬を楽しむつもりだし、楽しんでいるあいだ、楽しんでいる自分を知るつもりです。たいていの人々は生きていません。ただ競争しているだけ。地平線の遥か彼方のゴールに到達しようとして、行き着くことに必死で、息が切れてあえぐばかりで、自分たちが通ってゆく美しい穏やかな田舎の景色をすっかり見逃してしまいます。そして、気がつくと、年老い疲れきって、ゴールに着こうが着くまいが違いはなくなってしまう。わたしは、路傍に腰をおろしてたくさんの小さな幸せを積み上げることを決心しました、たとえ〈大作家〉に絶対ならなくても。わたしがこんな女哲学者になりつつあるとは知らなかったでしょ?)
〔解説〕 これも記事「ジュディーの幸福論――3月5日の手紙(2) Judy on Happiness: The Letter of MarchFifth (2)」で日本語訳だけ引いた一節です。幸せの秘訣として、「いまが大事」ということを、たぶん宗教的な世界観・人生観への反発をひそませながら、論じています。
(5) 4年生4月4日の手紙(ロック・ウィローから)
What do you think is my latest activity, Daddy? You will begin to believe that I am incorrigible―I am writing a book. I started it three weeks ago and am eating it up in chunks. I've caught the secret. Master Jervie and that editor man were right; you are most convincing when you write about the things you know. And this time it is about something that I do know―exhaustively. Guess where it's laid? In the John Grier Home! And it's good, Daddy, I actually believe it is―just about the tiny little things that happened every day. I'm a realist now. I've abandoned romanticism; I shall go back to it later though, when my own adventurous future begins. (Penguin Classics 110)
(私の最近の活動はなんだと思いますか、ダディー。性懲りもない、と思われそうですけれど――本を書いているんです。3週間前に始めて、むさぼるように進めています。秘密をつかんだのです。ジャーヴィー坊ちゃまとあの編集部のひとは正しかった。自分のよく知っていることを書くときにいちばん人をうなずかせることができるのです。それで、今回は、わたしがじっさい知っていることについての話です――知り尽くしていることです。舞台がどこに置かれたかあてられますか? ジョン・グリア・ホームの中です! なかなかのできです、ダディー、実際そう思えます――ほんとに毎日起こる小さなことについて書いているのですが。今わたしはリアリストです。ロマン主義はやめました。でも、あとになって、わたし自身の冒険にみちた未来が始まったときに、ロマン主義に戻るでしょう。)
〔解説〕 これは記事「ジュディーと冒険 The Adventurous Judy [Marginalia 余白に]」で一部引いた箇所でした。本来 "adventurous" (6) で "wandering spirit" (59: cf. "Wanderthirst")をもち、そしてスティーヴンソンやロマン派詩人にひかれるところのあるジュディーの、一種の暫定的妥協的文学観みたいなものです。
なんとなく思うのは、(3) のジュディーがかわいいという発見はさておいて、幸せの秘訣と創作の秘密は、日常の細部に目を向けることによって生じるという点で通底しあったところがあるのではないか、ということです。そして、その発見こそが、孤児であったジュディーの、あれほど憎んでいた孤児院に対する見方が変化することと、密接につながっているのですし、そこにジュディーの人間としての成長もあるのではないでしょうか。(あ、まとめすぎた)
〔BGM〕 "Can You Keep a Secret"; 「ゆうべの秘密」;
センチメンタル・トミー Sentimental Tommy [Daddy-Long-Legs]
4年生の試験が終わってイースター休暇に、ジュディーはサリーと一緒にロック・ウィロー農場に行きます。4月4日付けの手紙の追伸で、農場のニュースが報告されているうちの最後に、猫の失踪が出てきます。――
Sentimental Tommy (the tortoise-shell cat) has disappeared; we are afraid he has been caught in a trap. (Penguin Classics 121)
(おセンチ・トミー(三毛猫の)がいなくなりました。彼がワナにかかったのではないかと心配しています)
センチなトミーは初登場です。"tortoise-shell" は「ベッコウ」(タイマイの背中を煮てつくる)、そして一般に「カメの背中」がもともとの意味で、なんだか「釣果の図」を思い出してしまいますが――
「釣果の図」参照
ネコです。日本でいう「三毛猫」に相当するとされています。三毛猫は、日本語ウィキペディアにも書かれているように、ほとんどがメスで、オスはめったにいない(いわゆる伴性遺伝)とされていますが、ロック・ウィロー農場のトミーは「彼」と呼ばれているように、明らかに男です。英語のウィキペディアを見ると、やはり "almost exclusively female" と記述されていますけれど、掲載されている写真は、日本の三毛とは様子がちがいます。なるほど、ベッコウという感じ。――


Tortoiseshell Cats, images via Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Tortoiseshell_cat>
ととろで、いや、ところで、"Sentimental Tommy" という、唐突に名指される名前ですが、もしかすると、ピーター・パンで有名なバリーの1896年の小説『センチメンタル・トミー』に由来するかもしれません。――
James Matthew Barrie, Sentimental Tommy: The Story of His Boyhood (London: Cassell, 1896) <http://www.archive.org/stream/tommysentimental00barrrich#page/n5/mode/2up>
1896年1月からアメリカの雑誌 Scribner's Magazine に連載、その年の秋に単行本として刊行されました。これの続編が Tommy and Grizel (1900) で、ピーターパンの原型的な少年が現われている、ともいわれています。
ピーターパンが登場するのは20世紀になってからで、この少年(続篇だと青年)Tommy Sandys の物語は、比較的初期の作品ということになりますが、バリーは既に作家として名を挙げていて、ジョエル・チャンドラー・ハリスが好意的なコメントを書いています("A work of fiction that is as original as it is fascinating. Here, indeed, is life itself and all the accompaniments thereof." )。そして、ピーターパン以降も再版が出されたり、ちょっとあとの話ですが、1915年(監督トビー・クーパー、英)と1921年(監督ジョン・S・ロバートソン、米)に映画化もされています。
ピーターパン関係の作品は、The Little White Bird; or, Adventures in Kensington Gardens (1902) の後半にPeter Pan 登場後、Peter Pan (play) (1904) 、Peter Pan in Kensington Gardens (1906) 、When Wendy Grew Up: An Afterthought (1908) を経て、1911年に小説Peter and Wendy が出版されるわけで、同時代の作品・作者であったのは確かです。
James Matthew Barrie, Sentimental Tommy: The Story of His Boyhood (New York: Scribner's, 1896) <http://www.archive.org/stream/sentimentaltommy00barr#page/n11/mode/2up>
男の子です(ひつこい)
///////////////////////
James Matthew Barrie, Sentimental Tommy (New York: Scribner's, 1896), E-text <http://www.archive.org/stream/sentimentaltommy00barr#page/n0/mode/2up> 〔Internet Archive〕
James Matthew Barrie, Tommy and Grizel (New York: Scribner's, 1900), E-text <http://www.archive.org/stream/tommygrizel00barruoft#page/n5/mode/2up> 〔Internet Archive〕
James Matthew Barrie, Tommy and Grizel (London: Cassell, 1900), E-text <http://www.archive.org/stream/tommygrizel00barrrich#page/n5/mode/2up> 〔Internet Archive〕
"James Matthew Barrie," Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/J._M._Barrie>
「ジェームス・マシュー・バリー」, Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC>
青空文庫 作家別作品リスト:バリ ジェームス・マシュー <http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person890.html> 〔『ケンジントン公園のピーターパン』と『ピーターパンとウエンディ』〕
"SENTIMENTAL TOMMY JM. Barrie 2 Vol Set AUTHORS ED 1896 - eBay <http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260492867808>
「三毛猫」, Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%AF%9B%E7%8C%AB>
"Tortoiseshell cat," Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Tortoiseshell_cat>
![]()
にほんブログ村 の新カテゴリ~♪
女性の高等教育への偏見――貧しい、干からびた説教 (2) Prejudice toward Women's Higher Education: Poor, Dry Sermon (2) [Daddy-Long-Legs]
『あしながおじさん』4年生2月17、18日ごろの日曜日の手紙(再掲)――
Just back from church―preacher from Georgia. We must take care, he says, not to develop our intellects at the expense of our emotional natures―but methought it was a poor, dry sermon (Pepys again). It does n't matter what part of the United States or Canada they come from, or what denominaton they are, we always get the same sermon. Why on earth don't they go to men's colleges and urge the students not to allow their manly natures to be crushed out by too much mental application? (Century 268; Penguin Classics 118)
(いまさっき礼拝から戻ったところです――ジョージアから来た牧師さんの説教でした。わたしたちは情緒的本性を犠牲にして知性を発達させることのないように注意しなければならない、というのです――さりながら、我思うに、貧しい、干からびた説教であった(またピープス)。合衆国でもカナダでもどこの地域から来ようが、あるいは宗派がなんだろうが関係なく、わたしたちは同じ説教を聞かされます。いったい、どうしてあのかたたちは、男子大学に行って、過度の知的傾注によって男性性をしぼりとられないようにしなさいと説得しないのでしょうか?)
日曜日に女子大に説教にやってきた牧師が「あなたたち」と壇上で呼んでいるのが「わたしたち」なので、わたしたちとは(その場にいなかった学生も含め)ジュディーの在籍する女子大の学生たちのことです。し、一般的には(とりあえず北米の)女子大生のことだということなります。時代は、作家ジーン・ウェブスター自身の学生時代を反映するところが大きいならば19世紀末、あるいは、作品自体の時代を考えると、1910年に近い頃(北米と書いたけれど、舞台としてはアメリカ東部)。
実は、師走に若い友人からアメリカの大学についての本を何冊か借りて、友愛組織・ギリシア文字クラブ (freternity と sorority)に対する偏見とか、女子大の歴史とか、カリキュラム改革とか、ちょろちょろちらちら読んでいたのですが、典拠としてとりあげようと思っていた著作がむつかしすぎるので、とりあえず、別の本から、女性の教育に対する偏見について、文章を引いておきたいと思います。
川端有子の『少女小説から世界が見える――ペリーヌはなぜ英語が話せたか』(河出書房新社, 2006)という本です。終章も入れると全6章からなる論考の第5章(177-98 +コラム「『続あしながおじさん』と『ジェイン・エア』の危険な関係) が『あしながおじさん』を扱っていて、そこにこういう文章があります。――
高等教育と女性
あしながおじさんに宛てた手紙のなかで、ジュディは自分の大学生活をことこまかに報告する。ラテン語、幾何、歴史の授業、試験など。ところが、この大学の日常のディテイルに終始すると見えるその生活ぶりのなかには、実は「女子大生」に対する世間の偏見に対抗し、「新しい女性」の健全さを主張する言説が隠されているのである。ヴァッサー大学が古い常識に拘泥する世間から非難を受けたのは、この急進的女子大が、ハーヴァード大学などの男子学生とまったく同じカリキュラムを、女子大生に用意したためであった。
大学生としてのジュディの生活が、今までの少女小説の主人公たちとはまったく違うのは当然としても、女性だけのこの世界で、彼女がのびのびと学業にいそしみ、スポーツを楽しみ、寮生活を謳歌していることは大変強い印象を残す。兄と同様にラテン語やギリシャ語を学ぶことを、女性の能力の範囲外であるとしてやめるよう諭された『ひなぎくの首飾り』(一八五六)のエセルの時代からは、想像もつかない進歩である。
しかし、医学的言説ではこの当時も、勉強をしすぎると女性独特の生殖力に悪影響があるとして、生理の始まった少女には、頭を使う勉強を禁じていた。『あしながおじさん』より十数年前にアメリカで出版され、広く読まれていた医学書にも、そのことは明記されている。二十世紀の初めになっても、大学に行った女性は、知性を使いすぎて女らしさを失い、子どもをもつことはおろか、結婚すらもできず、健康を害してヒステリー症候群に陥る、そんな考え方がまだまことしやかに広まっていた。
アメリカではヴァッサー、スミス、イギリスではガートン、ニューナムをはじめとして、いくつかの大学が女性の高等教育に門戸を開き、その重要性を訴えはじめていたが、まだまだ女子学生たちは、ひからびた青踏派として揶揄されることが多かったのである。 (188-9)
(いったい、揶揄であるとか、まことしやかな考え方とか、多かったとか広まっていたといっても、どの程度まで一般的だったのか、どの程度まで正論とされていたのか、よくわからないのですが・・・・・・)
川端さんはこの手紙に言及していないのですけれど、手紙のジュディーの抑制した反発の背後にあるのはこういう歴史的文脈だと思われ。
![]()
にほんブログ村 の新カテゴリ~♪
///////////////////////
"Female education," Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Female_education>
「女子教育」, Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E6%95%99%E8%82%B2>
"Higher education," Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education>
「高等教育」, Wikipedia <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2>

ウィンドウ・シート Window Seat [Daddy-Long-Legs]
(このままだと卒業して話が終わってしまいそうなので、直線的な記事の進行を意識的に崩しますのその2.)
外枠の「ブルーな水曜日」(そこまで戻るんかいw)。
4年生3月5日の手紙で回想する(明日が月の第一水曜日だということで)孤児院での月一のしんどい日の記述から作品は始まっておったのでした。朝の5時から立ちどおしで院長にしかられたりせかされたりしながら掃除や調理や理事たちの接待や、さらにふだんと同じく子供たちの食事の世話などをようやく終えて、ホッとしたジュディーは窓際に腰を下ろして、帰宅する理事たちの車を目で追って、想像力を働かせるのですが、そのときの席について一席。
Then she dropped down on the window seat and leaned throbbing temples against the cool glass. (Century 4/ Penguin Classics 5)
(それから彼女はウィンドウ・シートに崩れ落ち、ズキズキするこめかみを冷たいガラスに押しあてた。)
日本語で「ウィンドウシート」というと(飛行機などの)窓際の席のことを指すのだそうです――『やさしいエアライン・ホテル用語辞典』参照――(これはモーリちゃんの母にも確認しました)。あるいは、フィルムみたいな感じで、窓を覆うシール状のモノ――宮崎県延岡市の看板屋ホリタの「窓をデザインするウィンドウシート」参照――(このときは seat ではなくて sheet なのでしょう)。
ここでの window seat は、ベンチ状の窓下腰掛けだと思います。
イギリスの Greenhill Design "window seats" <http://greenhilldesign.co.uk/window_seats/> の三つの例を見ると、左のふたつは出窓型ですが、みっつめのものは、壁面よりはみだして(でっぱって)部屋の内部に置かれているタイプです。
ヴァージニア州の Scott's Woodworking の "Cedar Chest Window Seat" のページ <http://www.scotts-woodworking.com/portfolio/robin/window%20seat/seat.asp> は、構造と組み立てを解説しています。
アンティークのものを探すと、取り付け型ではなくて、移動可能なベンチ式のものが目にとまります(つくりつけのものだとそもそも取り外して取り引きするのが困難ということもあるかもしれません)。たとえばBrooklyn Museum のコレクション "Brooklyn Museum: Decorative Arts:Window Seat" <http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4736/Window_Seat> 19世紀前半のニューヨークのもの。
いろいろと眺めると、装飾性の高いものから、シンプルな板だけのもの、箱型から脚のあるベンチ式までさまざまあるようです。そして上にも書いたように、動かせるものもありますけれど、基本、造り付けないし据付けであって、あっちにもっていったりこっちにもってきたりするような類の椅子でないことは確かでしょう。
と、ここまで書いて、翻訳を見ると、「窓際の腰かけ」とか、「窓の腰掛」とか、ただの「こしかけ」とか、ただ「窓に腰掛けて」(!)とか、いろいろですが、どういう腰掛けなのか、イメジは沸きません。遠藤寿子のみ「窓框(まどかまち)」と訳していて、あー、そう言うんだ、と思って、確認すべく辞書を引いたのですけれど、框(かまち)というのは、ひとつにはユカ・トコ(床)などの端にわたす横木のこと〔「あがりかまち」というのはこれの例〕、もうひとつはト(戸)・ショウジ(障子)などの枠のこと、を指す言葉だとわかりました。
そして、少なくともふつうの中型ぐらいまでの国語辞典(『広辞苑』もふくめ)には「窓框」の語はないようです。ところが、ウィキペディアには、項目としてはあがっていないのですが、異常に「窓框」の語が使用されている項目群がありました。鉄道系です。窓框まで何センチみたいな記述がたいへん多い。しかし、どうやら、上のふたつめの意味の「ワク」のことだと想像されます。なんで窓枠といわずに窓框というかは知りませんが。
念のためさらに調べると、JAANUS: Japanese Architecture and Art Net Users System というところが "madogamachi 窓框" (「まどがまち」と濁っていました)を英語で説明しています。どうやら建築・技工系の専門用語なのかしら。――
The window frame into which a window sash is installed. The timber that surrounds a window.
(窓サッシが取り付けられる窓枠。窓を囲む建材)
ということは、マドカマチからアガリカマチ的に、腰をおろす場所を連想した自分でしたが、窓框が窓辺の腰掛けを意味するということは考えられないわけですね(自信97パーセント)。
自分のイメジでは、下のようなシンプルなのが孤児院などの建物内にはありかなーと。
image via Greenhill Design "window seats" <http://greenhilldesign.co.uk/window_seats/>
ところで、窓辺に腰をおろして外を眺めるのが好きだと思われるジュディーは、大学の寮の部屋の窓が高いので、自分でウィンドウ・シートをこしらえることになります。その工作・工程がよくわからないので、その話はまた別の機会に。
//////////////////////////////
「ウィンドウシート (Window Seat)」 <http://dictionary.tabig.com/a/2005/08/post.html> 〔『やさしいエアライン・ホテル用語辞典』 <http://dictionary.tabig.com/> 内。いろいろな「旅行用語集」に同じ項目・記述があるようで、これがオリジナルかどうかは不明〕
「窓をデザインするウィンドウシート/看板屋ホリタ/宮崎県延岡市」 <http://www.horita-net.co.jp/print/window/win.html>
"madogamachi 窓框" <http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/m/madogamachi.htm> 〔JAANUS: Japanese Architecture and Art Net Users System〕
「サッシ」、「さからはじまる 建築用語辞典」 <http://www.rakkensya.com/sites/sa/> 〔『楽建舎建築用語辞典』 <http://www.rakkensya.com/sites/about/a05/>〕――
【サッシ】
窓枠と窓框(まどかまち)の総称。工業製品としての建具。スチール製・アルミニウム製のものが多い。「サッシュ」ともいう。
慇懃になって真実を曲げることはしない Not Let Politeness Interfere with Truth [Daddy-Long-Legs]
ちょっとまじめに『続あしながじさん』(Dear Enemy) を細かく読みだしました。まだ続篇に進む気はないのですけれども、そしてこれまでは『あしながおじさん』以前の作品と『あしながおじさん』とのつながりみたいなのは書いてみようかな、とパティーとか小麦姫とかちょこっと書いてみたりしたのですけれど。あとのものもなるたけ言及するのが自然かとも思われ。
『あしながおじさん』2年生のおわりの9月10日の手紙で、ジャー(ヴィー坊)ちゃんが手厳しく作品の批評をすることをジュディーが語るところ――
Master Jervie read them [six stories and seven poems] ―he brought in the mail, so I couldn't help his knowing―and he said they were dreadful. They showed that I didn't have the slightest idea of what I was talking about. (Master Jervie doesn't let politeness interfere with truth.) (Penguin Classics 88)
「ジャーヴィー坊ちゃん」という方は、ほんとうのことをいうと失礼にあたるなんて、遠慮なさる人じゃありません。(遠藤寿子訳『続あしながおじさん』 (岩波少年少女文学全集12) 98-99)
『続あしながおじさん』のサリー・マクブライドからジュディへの7月金曜日夜11時30分の手紙――
Our Sandy does not let politeness interfere with truth! (Penguin Classics 283)
あの先生は、じぶんのほんとうの気持ちを、礼儀のために曲げるなんてことをしないひとなのよ! (遠藤寿子訳『続あしながおじさん』 (岩波少年少女文学全集12) 318)
この表現は引用なんでしょうか。不詳ですが、ともかく同じ表現が両作品に出てきます。
『あしながおじさん』の年代の確定 [Daddy-Long-Legs]
『続あしながおじさん Dear Enemy』(1915) の3月6日付のジュディー宛の手紙 (Penguin Classics 156-158) には、サリーが "Betsy Kindred, 1910" にジョン・グリアー・ホームの仕事の手伝いを頼んだことが報告されています。――
Do you remember Betsy Kindred, 1910? She led the glee club and was president of dramatics. I remember her perfectly; she always had lovely clothes. Well, if you please, she lives only twelve miles from here. I ran across her by chance yesterday morning as she was motoring through the village; or, rather she just escaped running across me.
I never spoke to her in my life, but we greeted each other like the oldest friends. It pays to have conspicuous hair; she recognized me instantly. I hopped upon the running-board of her car and said:
"Betsy Kindred, 1910, you've got to come back to my orphan-asylum and help me catalogue my orphan."
And it astonished her so that she came. She's to be here four or five days a week as temporary secretary. She's the most useful person I ever saw. (157)
(1910年度のベッツィー・キンドレッドを覚えてる? グリークラブのリーダーで演劇部でも部長をしていたのだけれど。わたしはよくおぼえてるわ。いつもすてきな服を着ていたのですもの。でね、驚いたんだけど、ここからわずか12マイルのところに住んでいるの。きのうの朝、彼女が自動車でこの村を通り抜けようとしていたときに、ばったり出会ったの。というか、もうすこしで轢かれるところだったわ。
これまでいちども口をきいたことがなかったのだけれど、おさななじみの友だちのように互いにあいさつしました。目立つ髪の毛をもっているのって、得だわ。すぐにわたしとわかってくれた。自動車のステップにとびのって、わたし言ったわ。――
「1910年のベッツィー・キンドレッドさん。あなたはわたしの孤児院にとってかえして、孤児たちのカタログをつくる手伝いをしてくださらねばだめよ。」
彼女はあんまりびっくりしてついてきました。臨時の秘書として、週に4日か5日かきてくれることになりましたが、なんとか臨時じゃなくさねばなりません。わたしがこれまで見てきたなかでいちばん役に立つ人です。)
"Betsy Kindred, 1910" の 1910 は大学の卒業年です。
つづく「水曜日」の(サリーの婚約者)ゴードン宛の手紙では、キンドレッドについて、"Betsy and I were in college together" (ベッツィーとわたしは大学で一緒だった)と説明しています。
これだけでは、ベッツィーとサリー(とジュディー)が同級だったのか、先輩後輩だったのか、はわかりません。けれども、『あしながおじさん』4年生3月5日の手紙で、翌日が月の第一水曜日、とジュディーが書いたのを根拠としてカレンダーを確認したところでは、3月6日(水)というのは、(a) 『あしながおじさん』が出版される1912年か、(b) 作家のジーン・ウェブスターがヴァッサー大学を卒業する1901年に合致しているのでした(そのあいだの1902~1911年はあてはまりません)。〔「デートと万年カレンダーによるジュディーの誕生日の推定はほんとにあっていたのか? Was the Supposition of Judy's Birthday from Dates and the Perpetual Calendar True」参照〕
そうすると、やっぱり(b) の1912年に卒業というのが正解だったのかな、と思われました。ベッツィー・キンドレッドは2年上なのではないか、と考えられ(同学年だったらそれなりの書き方があるような気もしますし)。
仮にジュディーの日付に現実の時間との対応という正確さがないとしても、1910年と重なるころに、ジュディーやサリーの大学生活は設定されていることは確認されるのでした。
ちなみに、『続あしながおじさん』ではジュディーとジャーちゃんに娘ができていて、一緒に南へ旅行していますし、あとで出てきてやはり孤児院経営を助ける同級のヘレン・ブルックスは、大学を卒業後に結婚・男児出産・愛児の死亡・離婚・実家との口論・ニューヨークに出て出版社勤務、という人生経験をつんでいます("Since her graduation she has been married, has had a baby and lost him, divorced her husband, quarreled with her family, and come to the city to earn her own living." 302)。ですから、『続あしながおじさん』の物語が始まるときには、数年が経過している、と推測されます。
『あしながおじさん――4幕の喜劇』 Daddy Long-Legs: A Comedy in Four Acts [Daddy-Long-Legs]
記事「『あしながおじさん』 Asa の謎 Asa Mystery」でつぎのように書きました。――
そして、調べてみると、1914年というのは、ウェブスター自らが小説『あしながおじさん』の脚本を書いて舞台に乗せた年だったのでした。さらに最近調べたところではヴァッサー大学の "Jean Webster McKinney Papers" (McKinney というのはWebster が結婚してあらたまった姓です)という資料の Box 12, Folder 5 には、この芝居に関する作者の文書が保存されているようです。ただし、まとまった脚本として残っているのか不明です。少なくとも公に刊行された形跡は見当たりません。
ペンギン・クラシックス版の序文で、エレイン・ショーウォルターは、ヴァッサー大学のウェブスター・ペイパーズには、各幕の記述と主要登場人物の要約が残されている、と書いています("Webster's papers at Vassar College contain her descriptions of each act and her summaries of the main characters." (xiv))。そうして、一人称書簡体という制約から解放されてジーン・ウェブスターは大胆かつ明確に意図を示すことができたのだ、と指摘しています。とりわけジュディーの天賦の才について――
While the "orphans as a body represent a dead level of mediocrity, the result of bad environment and in some cases bad heredity . . . Judy stands out in striking contrast." She "rises out of the mass, original, resourceful, courageous. . . . She emerges from her dark background, throws off the trammels that have bound her down and daringly faces life. . . . There is an element of revolt in her nature, a spirit of fight which makes her a fierce little rebel against injustice." (Elaine Showalter, Introduction, Daddy-Long-Legs and Dear Enemy)
(孤児たちが、一団として、悪しき環境の結果、またある場合には悪しき遺伝による、凡庸の水準をあらわしているのに対して・・・・・・ジュディーは際立った対照を示す。」 彼女は「集団から上昇し、独創的で、才能にあふれ、勇気がある。・・・・・・彼女は暗い背景から現われて、自分を束縛していた拘束物を投げ捨て、勇敢に人生に向かう。・・・・・・彼女の性格には反抗の要素があって、その闘争精神により彼女は不正に対する激しい反抗者となる。)
それで、ヴァッサーに行って資料を見せてもらうしかないなあ、と思っていたのですけれど、ところがところが、死後の1922年に、ニューヨークのサミュエル・フレンチという、この劇の上演権をもっていたらしい出版社が、脚本を出版しているのが見つかりました。
Jean Webster, Daddy Long-Legs: A Comedy in Four Acts
Daddy と Long-Legs のあいだにハイフンがないのが気になりますが、コピーライトのページには小説の1912年から上演の1914年もちゃんと並んでいます。――
第1幕の舞台はジョン・グリアー孤児院の食堂、第2幕は大学の寮内の部屋、第3幕はロック・ウィロウ農場の部屋、第4幕はジャーヴィス・ペンドルトンの書斎が舞台となっています。
冒頭の "Scene" のところに "A plan and full description of the scene will be found at the end of the play" と書かれていますが、確かに巻末に舞台見取り図とくわしい設定が記されています(ただし舞台の図面を見ても、『あしながおじさん』でなじみのジーン・ウェブスターのヘタウマ的な絵との類似はよくわからず。それに "Daddy Longlegs" と題が付されているので、たぶん別のひとによる図ではないかと思われ。いや、そんなこと言ったら、脚本の本文中でも "Daddy Long-Legs" となっており、テクスト自体がアヤシイです)。
ジャーヴィス・ペンドルトンは第1幕から姿を見せます。そしてこの孤児院を舞台とする部分は、114ページある脚本の37ページまでが1幕であることからわかるように、けっこうな分量がありますし、ジャーヴィス以外の理事(例の、ジュディーの作文をおもしろがってジャーちゃんに教えた女性 Miss Pritchard)も2幕以降も登場します。この舞台の成功が、孤児院問題についての世論の高まりを呼んで、いっぽうでウェブスターは現実世界で自ら社会改良運動にさらにコミットしていきますし、もういっぽうで続編『続あしながおじさん Dear Enemy』 (1915) を書いて孤児院の問題&遺伝・環境問題を掘り下げることになったのではないかと思われます。
1914年の舞台でジュディー役をつとめたのは、まだ映画で活躍する前の、はたちそこそこのルース・チャタートン Ruth Chatterton, 1893-1961でした。大ヒットとなりニューヨークののち東部をまわり、カリフォルニアへ、さらにロンドン公演も行なっています。ヴァッサーの学生たちの要望により、ポーキプシーのオペラハウスで特別公演も行なったのだそうです(Showalter xiv)。
ルース・チャタートン扮するジュディーは、センチュリー社のリプリント版のダスト・ジャケットに使用されました。――
.jpg)
Jean Webster, Daddy-Long-Legs (New York: Century, n.d.)
ううむ。初版を出した出版社のくせに、Daddy Long Legs と、まったくハイフンがないですねぇ。やれやれ。
/////////////////////////////////
Jean Webster, Daddy Long-Legs: A Comedy in Four Acts [French's Standard Library Edition] (New York: Samuel French, 1922[?]) <http://www.archive.org/details/cu31924021717933> 〔Internet Archive〕; PDF (2.99 MB)
『あしながおじさん』のテクスト問題 (1) ――イギリス版を使っているらしいプロジェクト・グーテンベルクの電子テクスト Problems of Texts in Daddy-Long-Legs (1): Project Gutenberg E-text [Daddy-Long-Legs]
実は前から気になっていたのですけれど、プロジェクト・グーテンベルク Project Gutenberg (以下 PG)の『あしながおじさん』のE-text <http://www.gutenberg.org/files/157/157.txt>は、冒頭に "Copyright 1912 by The Century Company" と書かれているけれどもセンチュリー版のテクストではないです。
のちに青空文庫で復活されることになるさまざまなE-text やオリジナルの翻訳を作成したosawa さんには、「足長父さん : PG 版とCentury 版の比較」と題するたいへんな労作があって、テクスト間の異同がリストアップされています(osawa さんの仕事については「osawa さんの足長父さん@物語倶楽部 Daddy-Long-Legs Trans. by osawa@StoryClub」を参照)。おそらく2001年か、2002年ごろの仕事だと思われ、その後にPG のテクストも若干の修正があったかもしれないのですが(というのは "Release Date: June 9, 2008 [EBook #157]" と現在のPG はなっているので)、まず、基本的な以下の特徴は変わっておらない。――
(1) 引用符がPG はシングル、Century はダブル。
(2) PG は "cheque" "favour" "grey" "humour" "theatre" "towards" などのイギリス綴り、Century は "check" "favor" "gray" "humor" "theater" "toward" とアメリカ式の綴り。
この2点から、あっさりと、プロジェクト・グーテンベルクはアメリカ版ではなくてイギリス版を使用している、と結論できます。そして、この2点だけならば、綴り字とパンクチュエーションの英米の歴史的な違い、という範疇におさまるので、それほど大きな問題ではない、といえるかもしれません。
しかし、英米の違い、ということでは次のような語彙・表現の差異もあります。これには、たぶんイギリスの読者にわかりやすくする、あるいは自然に読ませるための改変が含まれていますが、著者によるもの(つまり、いわゆる "authoritative")だとは思われず。――
(3) 'sauced' a Trustee [PG]/ "sassed" a Trustee [C]; a few cents [PG]/ a nickel [C]〔ニッケル=5セント玉〕; Clothes-Prop [PG]/ Clothes-Pole [C]〔ものほしざお物干し柱〕; really too bad [PG]/ sort of too bad [C]; it's great fun [PG]/ it's sort of fun [C]; rather monotonous [PG]/ sort of monotonous [C]; everywhere else [PG]/ every place else [C]; talk plainly [PG]/ talk plain [C]〔形容詞の副詞化というアメリカニズム〕; Goodbye [PG]/ Good-by [C]; she didn't get in [PG]/ she did n't make it [C]; fail again [PG]/ flunk [C]〔「落第する」のアメリカニズム〕; to post this off now [PG]/ to the mail chute and get this off now [C]; fifty-yard sprint [PG]/ fifty-yard dash [C]; very consequential [PG]/ very up and coming [C]; brought in the post [PG]/ brought in the mail [C]; with tremendously big drops [PG]/ with drops as big as quarters [C]〔クウォーター=25セント玉〕; bad work in maths and Latin [PG]/ bad work in math. and Latin [C]; I'm LONGING to go back [PG]/ I'm crazy to go back [C]; in the street [PG]/ on the street [C]; aesthetic [PG]/ esthetic [C]; letters [PG]/ mail [C]; post [PG]/ mail [C]; box [PG]/ chute [C]; outdoor world [PG]/ outdoors world [C]; in advance [PG]/ ahead of time [C]; ask for more than twenty-five [PG]/ ask more than twenty-five [C]; still at collge [PG]/ still in college [C]; PS. [PG]/ P. S. [C]
(4) また、上の LONGING = crazy にうかがわれるように、PG版は、本の斜字を、大文字にすることで示そうとしていますが、それが不徹底なところがあります。どうやら強調を示す斜体を大文字にして、フランス語やラテン語などの外国語を示すイタリックは、変更しないままにしているようですが、だとしても、強調のイタリックが大文字に変換されていない箇所がいくつもあります( I'm not a Chinaman の not とか)。いずれにしてもそういう方針では、原文のありようを示すことが不完全なのは明らかです。
(5) そして、単純な誤植が生じている、あるいは残ったままです。―― shiny sticks [PG]/ shinny sticks [C]/ JUCIEST [PG]/ juiciest [C]; Comers [PG]/ Corners [C]; Acceptez mez compliments [PG]/ Acceptez mes compliments [C]; juniors [PG]/ Juniors [C]; clear me [PG]/ dear me [C]; downs [PG]/ clowns [C]; Patrici [PG]/ Patricia [C]; a absurd [PG]/ an absurd [C]; an more than [PG]/ any more than [C]; Rhode island Reds [PG]/ Rhode Island Reds [C]〔ニワトリの品種〕; an I think [PG]/ and I think [C]; meet me or a surprise [PG]/ meet me for a surprise [C] などなど。もとの版がわからないので断定はできませんが、少なくとも一部はスキャンの読み誤りによって新たに生じたものではないか、と推測されます。(5b) 改行の不全もあります。(5c) パンクチュエーション(上述の引用符はさておき、コンマやピリオドやダッシュの使用)の不備もあります。
ここまでをまとめますと、そもそも第一にイギリス版を使用することの妥当性の問題があり、第二に、PG 自体の内在的問題があります。
そして、自分が別の次元で気になったのは、もとにしたらしいイギリス版の、テクストとしての価値です。どういうことかというと、イギリス人たちが慣れ親しんだかもしれないイギリス版をE-text にしたい、というなら、それはそれで意味はあるでしょう(その場合でもきちんとその旨を情報として書く必要はありますけれど)。しかし、イギリス版にもいろいろな版があり、歴史があるはずです。
どうやら1912年の秋にアメリカ版がニューヨークのセンチュリーから出版され、まもなくイギリス版が出版されているらしい(現物を見ていないので推定です。どうやらロンドンのHodder and Stoughton 社が出しているらしい)。
WorldCat で検索してみても、たいした情報は得られないので、古本屋のコンソーシアムの AddALL で検索すると、1913年の日付でイギリス版初版があがっています(でも、こういうので断定はできません)。――
First English Edition. A very good copy in the original grey pictorial cloth, spine heavily scarred, boards marked. Scarce. Publisher: Hodder & Stoughton, 1913 Hodder & Stoughton, 1913
100ドルで売られています。しかし、同じ出版社がその後も永らく版を重ね、あるいはペーパーバック版を出して、1949年には73刷になっています。そして、いつ版が変えられたかはわかりませんけれど、少なくとも1970年のハードカヴァーは190ページで、これは初版のハードカヴァー(249ページあったらしい)とは違いますから、組み換えが行なわれたのは確かでしょう。
また、次のような記述のテクストもあります。――
Publisher: (London: Hodder and Stoughton: 1916) The Renee Kelly Edition Illustrated from Photographs of the Play. Cl. pp. 249. Frontispiece and seven other plates in addition to the usual text illustrations.
Publisher: (London: Hodder and Stoughton: 1931) A Hodder and Stoughton H and S Yellow Jacket. Pictorial wrappers (that is, paper covers) pp. 128 (209 x 140 mm) Illustrated. Front wrapper says ‘See Janet Gaynor in this FOX Picture’ and has a picture of her in costume.
そうすると、これらが実在し、記述が正しければ、同じHodder and Stoughton 社でも128 ページ、190ページ、249ページの版が、ときおりジャケットや図版の改変を行ないながら、存在してきた、ということになります。
で、話が長くなりましたが、自分が気になったことというのは、PG のテクストから判断して、これはイギリス版であっても、初版ではなくて、後のリプリントをもとにしているのではないか、ということです。
その根拠の主たるものは、ひとつには today やtomorrow のつづり方、もうひとつには縮約形の印刷の仕方です。
一点目。PG は一貫してtoday、tomorrow と綴っていますが、センチュリー版は一貫して to-day 、to-morrow と綴っています。しかし、これはアメリカだけのスタイルではなくて、第一次大戦が終わって1920年代くらいまでは英米とも to-day のようにハイフンを入れるのが一般的でした(自信98パーセント)。もちろん今日ハイフンを入れるのは "old-fashioned" になっています。
たとえば17世紀のサミュエル・ピープスはもちろん to-day と綴ります。しかしPG版は、地のジュディーの文章における to-day、to-morrow だけでなく、引用符に入っているピープスの日記の "To-day came home my fine Camlett cloak . . . ." の "To-day" も "Today" となっています。これが何を語っているかというと、一貫した変更が行なわれ、誤って引用文中の単語も直してしまったということです。そして、一貫した変更は、なるほど今日のようなコンピューターでこそ簡単に行なわれる、と考えられるかもしれませんが、いやしくも公開のe-text を作成する人間が、よほどのバカか歪んだ言語観をもった狂人かでない限り、その種の変更を勝手に加えるということは考えられません。しかし、出版社、とりわけ一般書を出す出版社が、時代にあわせてつづりを「現代化」するということは考えられます。
2点目。センチュリー版は、たとえば didn't という縮約形を did n't というふうに、n'tの前にスペースを入れています。これは下のセンチュリー版のページを見ていただくとわかるように、 It 's とか she 'd [=she had] とか、 there 's とか、I ’m とか、We 've とか、That 's とか、すべてそうです(can't や don't はちがいます――それはたぶん音と綴りと読みの関係の問題)。
Jean Webster, Daddy-Long-Legs (New York: Century, 1912) <http://www.archive.org/stream/daddylonglegs00websrich#page/64/mode/2up>
この習慣について、自分はちゃんとした知識がありません、恥ずかしながら。個人的にこういう印刷を見たのは高校生の頃、ペンギン版の『不思議の国のアリス』でした。その後、1900年前後のアメリカ文学のテクストでも(たとえばノリスの『マクティーグ』)、初版では同様に狭いスペースが入っていたことは知りました。イギリスでもアメリカでも、かつてはこういう印刷のされかたをしていた、ということは確かです。
よくわからんのですが、常識で考えると、ふつうにスキャンすれば、もとのテクストの語と語のスペースは残るはずですから(だって、スペースが自動的に閉じてしまうならば、縮約形の連語のみならずすべての語と語の間のスペースがなくなっててしまうことになる)、やはり、依拠した本が既にスペースをもっていなかった、ということになるのではないでしょうか。今日、「本」にするときには、この種のスペースは保存しないで、詰めて編集してしまうであろうことは承知していますが。
ということで、Project Gutenberg の Daddy-Long-Legs のE-text は、信用でけへん、というのが結論です。残念ながら、あちこちに増殖しているのですけれど。それだけに、たいへん問題だと思うのです。
脚の話 (1)――百足図 Leg Stories: Centipede Pictures [Daddy-Long-Legs]
「カリフォルニア時間」というブログを2008年4月に始めたころに、ブログのありようについていろいろ教えを受けた、アメリカ在住の美女が、昨年日本に一時里帰りして、そのときにはじめは大人数で飲んでいたのが、何段もハシゴをして(たぶん5段くらい)、なぜか明け方までつきあってもらって、ふたたびブログのありようを相談させてもらった際に、口から半分は出まかせで、『あしながおじさん』は脚の話である、というようなことを言いました。それと合わせて、『あしながおじさん』における神問題と脚の話がつながる、という予感めいたものを語り、いずれにしてもいずれもぜんぜん同意を得ることなく終わった(まあカラオケで歌った「恋の予感」みたいなものだったし)のですけれど、これから書くから、と無謀な先生いや宣誓をしたような記憶がかすかに罪悪感めいたものと共に残っているのでした(です)。
以上で前口上は終わり。
あ、いや、もう少し書くと、そのときブログについて別に話したのは、自分(モーリちゃんの父)的には、「カリフォルニア時間」を読み返してみると、自分でおもしろいのは、モーリちゃんとのクイズみたいな記事であって、それを書けなくなったいまの「学問」的状況はなんだか自縛的で問題かなあ、ということでした(たしか)。アメリカにいたから書けたということと、(それと同じことですが)生活状況が変わってしまって日常生活を書くと、日本の個人的状況・人間関係があらわになってイヤだな、みたいな。ブログは日記だと規定した自分であったはずなのに。ああそれなのに。
閑話休題(自爆)。
それなりに論理を組み立てたいのですが、まだ思案中w。でも、(1) と書いたからには突き進みますよ、はい。できうるならば自分を崩しながら。
まずはカタイ話ではなく、図から。
8本足のザトウムシ(アシナガオジサン) (Penguin Classics 8) と昆虫のコガネムシに擬せられる理事 (Penguin Classics 41) のあいだに出てくる多本足の存在はムカデです。漢字では百足、英語は同様に「百の足」を意味する "centipede" です。実際にはさまざまな本数のムカデが存在し、100というのは「多数」の意味でしかないのは承知しておりますが、下の引用にあるように、「百本足」という名称にのっとった記述をジュディーはしています。
寮(ファーガスン・ホール)は、建物が古いのと、ツタが壁を覆っているために、いっぱいムカデがいて、学生たちを悩ませているのですが、このときは、手紙を書いているジュディーのそばに天井から落ちてきて、ジュディーとびのく拍子にふたつカップをテーブルから落としてしまいます。叫び声を聞きつけてサリーとジュリアのみならず廊下のむかいの4年生もジュディーの部屋に入ってきて、サリーがヘアブラシ(ジュディーの)でムカデを叩き、マエのほうは死んだけれど ("killed the front end")、うしろの50本 ("the rear fifty feet")はたんすの下へ逃げていきます。
ジュディーは、ムカデを "dreadful creatures" と呼び、ベッドの下にトラがいるほうがまだましだ、とも書きます(Penguin Classics 36)。
これが1年生4月か5月の月曜日。ところが、1年後の5月か6月の木曜日の手紙 (Penguin Classics 72) では、小鳥とリスとムカデと一緒にお茶をしていて、ムカデにむかって、「ムカデ夫人さん、おひとつ、おふたつ?」("My dear Mrs. Centipede, will you have one lump or two?" と言いながらカップをさしだす絵が描かれています。
手紙の本文は短いもので、この絵を導入するダッシュの前に、実験棟から戻ったら、リスがティーテーブルに「座って」ひとり勝手にアーモンドを食べていたことを書き、「天気が暖かくなって、窓が開けはなしなので、こういう種類の訪問者たちの接待をわたしたちはしています――」("These are the kind of callers we entertain now that warm weather has come and the windows stays open―") と記して、あとは上の絵が載っているのです。
now that = since (理由)
"we" と書いてはいますけれど、チャイナ服のように見える服を着たわたし=ジュディーが接待しているのは明らかで、ムカデとの和解はなぜ起こったのか(理由)、がひとつの問題なのですが、それはマタにして、百足図で気になるのは、第一に、頭がでかく描かれていることです。これはムカデの知性を認めたということなのでしょうか? それとも最初の図は、そもそもサリーによって分割されたのちも生き残った半分を描いていたということなのでしょうか? それと付随して、第二に、足の向きの問題があります。第二のムカデ図を見ると、椅子に腰掛けて、垂直に立っている部分は、重力によって、足が下向きになる、ということは考えられますが、椅子の上の水平部分も、足の折れ方は同じ方向です――
(頭 〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈
〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈 尻)
そうすると、第一のムカデ図で、左側が頭の側で、右側が尻の側、ということにならないでしょうか。なりますね。ならば、やっぱり頭がなかったのでしょうか? あと、じゃあ、右の端のコックさんの帽子みたいなかたちに丸まっているのは小さい頭ではなくて、何?
はい、数をかぞえました。第一のムカデ図の上半分にある足の数は31本、下半分は34本。
あらためてテクストを読むと、 "It was caused by a centipede like this:" と書かれています。「それ〔叫び声〕は、こんなムカデによって引き起こされたのでした――」。そうすると、この図は半分になる前のムカデだった、と考えるのが自然だと思われます(100に満たないのは、上下の足数が合わないことでほのめかされるように、アバウトな絵だから)。
ちなみに第二のムカデ図では、むかって左側の足の数はおよそ20本くらい、右側は24~25本くらいしかないようです(目が疲れました)。しかし、これが、同様にアバウトさ故なのか、それとも一年前に生き残ったムカデの半分だということを示唆するものかどうかは不明です。
ううむ。これが脚の話で、神問題にどうやってつながるのでしょう(我ながら不安だわ~w)。